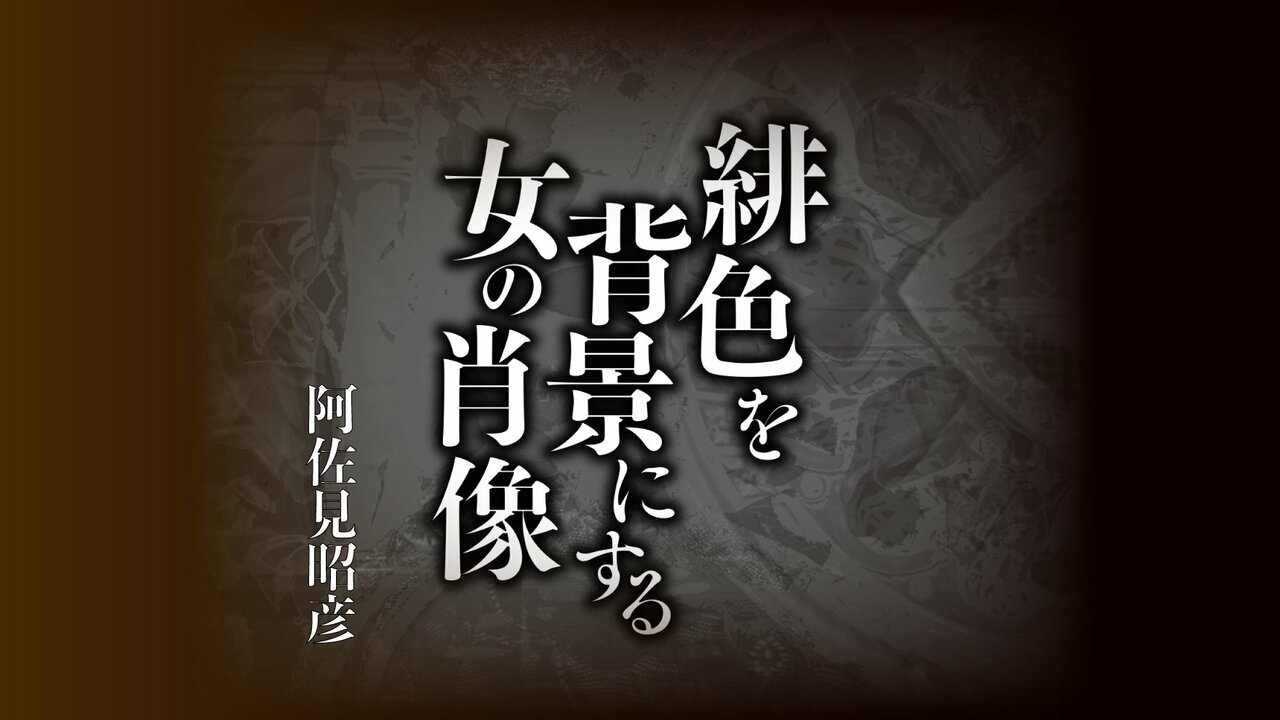6
ラウンジに戻り、テイスティング・ラウンジの端に置かれたテーブルに着くなり、カウンターの中にいた若い女性従業員が二人に向かって来た。テーブルにボトルが四本と二組のグラスが、それぞれ四個ずつ置かれ、まず二つのグラスに淡い琥珀色の液体が注がれた。静かな室内にコク、コク、コク、と透明な音が響き渡った。
「白の五年ものです」
半日近く動き回って、少し膝と腰に張りを感じていたが、こうやってグラスを合わせると、既に周囲の空気を支配していた芳醇な香りが、今度は口一杯に広がり、心地よい刺激が徐々に身体中を巡り始めた。
「白もなかなか好い味ですわ」
「ポルト・ワインもなかなか良いものですね。この甘さが疲れを取ってくれそうです」
「赤の五年ものです」
別のグラスに深いルビー色の液体が注がれると、宗像は前に置いたグラスに白を少し残したまま、赤の方を口に含んで一気に飲み干した。
「芳醇さは白に勝るとも劣らない感じですが、白に対する赤い色彩の強さが実際以上に、味覚を、強く、深く、濃厚に感じさせるようですね?」
「凄い批評ですね。目で感じる赤の強さは白に勝りますものね」
エリザベスが感心したように頷いた。
「十年ものの赤です」「十五年ものの赤です」
テイスティング・ラウンジは、ワインを味わう者、購入の手続きをする者など、大勢の観光客で混み始めていた。
「ところでエリザベスさん、ロンドンではどのようなお仕事を?」
「はい、再来年ロンドンにオープンする、ある商業施設の立ち上げに向けた仕事をしておりますの。デベロッパー、建築家、商業コンサル、商環境デザイナーなどがまとめたコンセプトに対して、私たちの事務所がサイン、ロゴ、パッケージ、ポスター広告などのデザインやコピーライトを担当しています。
英国の不動産業者に米国の資本。フランス人の建築家にイタリア人のデザイナー。それに私たち。国際的なコラボレーションというわけで、やりがいがありますわ。保守王国と言われるイギリス。そしてその首都ロンドンに登場するのはアッと驚くコンセプト」
エリザベスは得意満面の面持ちだった。
「最後のテースティングとなります。赤の二十年ものです、どうぞごゆっくり」
若い娘は笑みを浮かべながら言った。光の反射でキラキラ光る二つのグラスに赤色のポート・ワインが注がれ、一層濃厚で甘い香りがテーブル全体を包み込んだ。
「五年刻みで次第に濃厚に、そして芳醇になっていきますわ。飲み分けられるかしら?」
「僕にはとても自信がないですね」
エリザベスはグラスに顔を近づけ、その芳しい香りを十分に堪能した後、ワインを一口含んだ。頬を膨らませて味わうと、にっこりと微笑んで言った。
「私には分かりそうですわ……ええ、確かに」
いつのまにラウンジに来ていたのか、アンホドロが頃合を見計らったように二人を促した。
「さあそろそろカフェ・マジェスティックへ移動しましょう。旧市街地ですよ」
ドン・ルイス一世橋を渡る時、左側を見下ろすと、遥か下のドウロ川沿いには中世の町並みが、ジグソーパズルのように広がっていた。サン・ベント駅を右折し、急勾配の坂道を一気に駆け上がって左折すると、間もなく一目でそれと分かるモデルニスモ・スタイルのカフェが視界に入ってきた。
この時間、観光客らしいグループはほとんど見られず、店内は空いていた。気に入った席でも見つけたのか、エリザベスは先頭に立って中ほどまで進むと、壁を背にした椅子を指差し、ここで良いかと目配せをして座った。
「本当はこれ秘密なんです。でも宗像さんは日本人ですし、御職業からも差し支えないと思って。
“二十一世紀の新しい船出、新たなる大航海時代に、あなたが発見できるものは?”
というコピーライトが基本コンセプトです。このプロジェクトは私の事務所が国際コンペティションに勝利して受注しましたの」
「おめでとうございます。オープンしたらぜひ拝見させていただきたいものですね」
「ええもちろん、ぜひ。ご案内いたしますわ」
装飾的な金色のフレームによって区切られた壁の中に、大きい鏡が連続してはめ込まれているカフェは、実際以上に広く見えていた。日差しが斜めに傾き、その強さを若干弱め始めたとはいえ、街路を行き交う人達の服装は、その白さをさらに増したように輝いていた。
「十時近くにならなければ真っ暗にはなりません」
眩しそうに目を細める宗像の視線に気づいてアンホドロが言った。