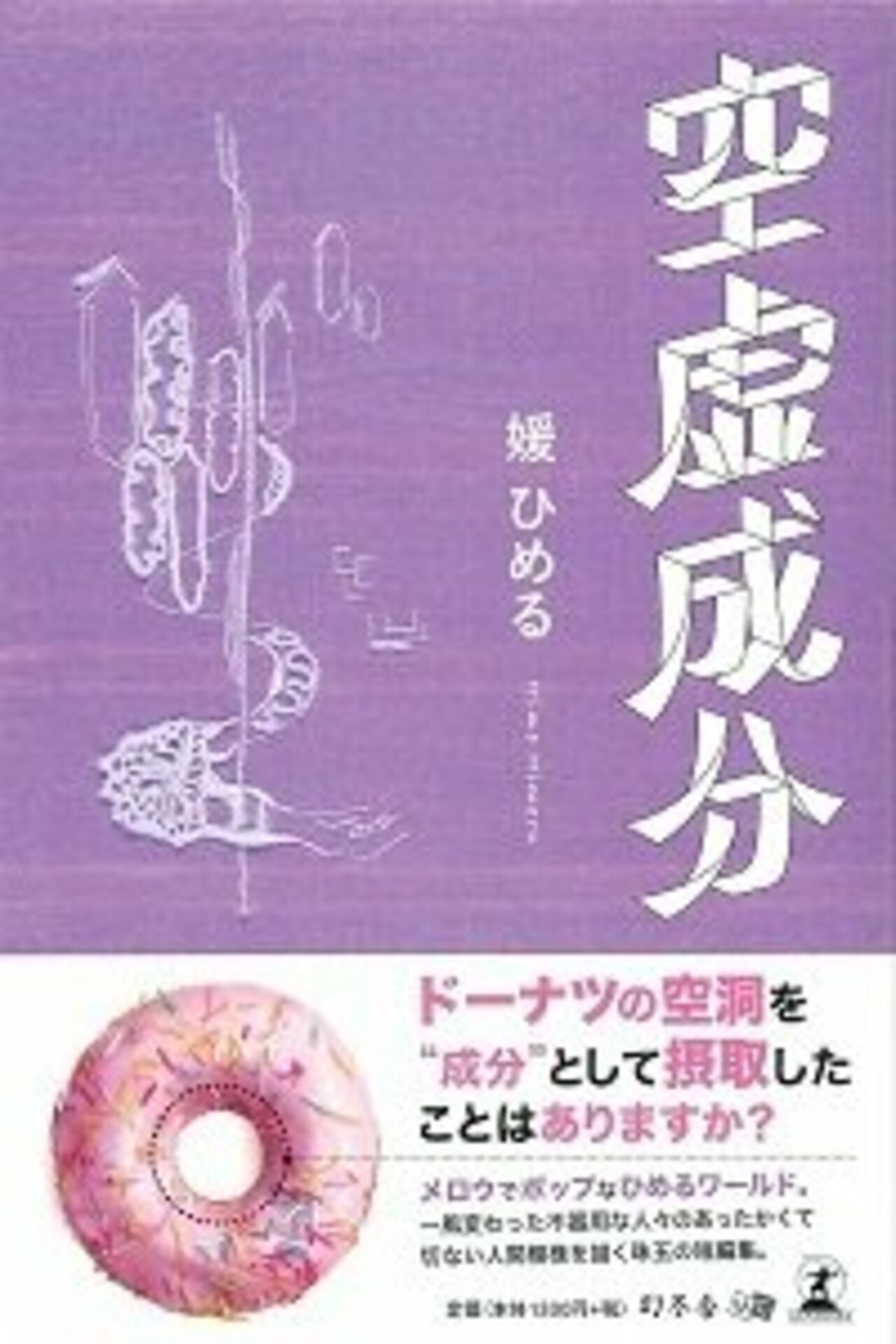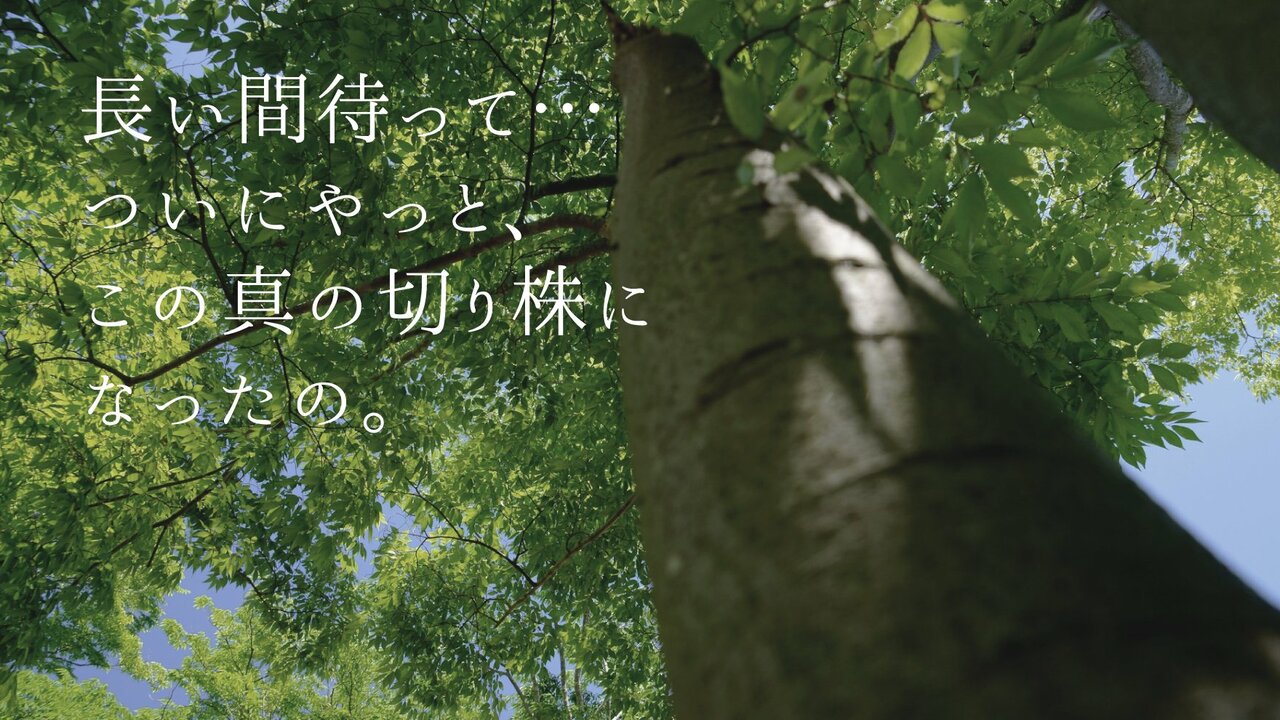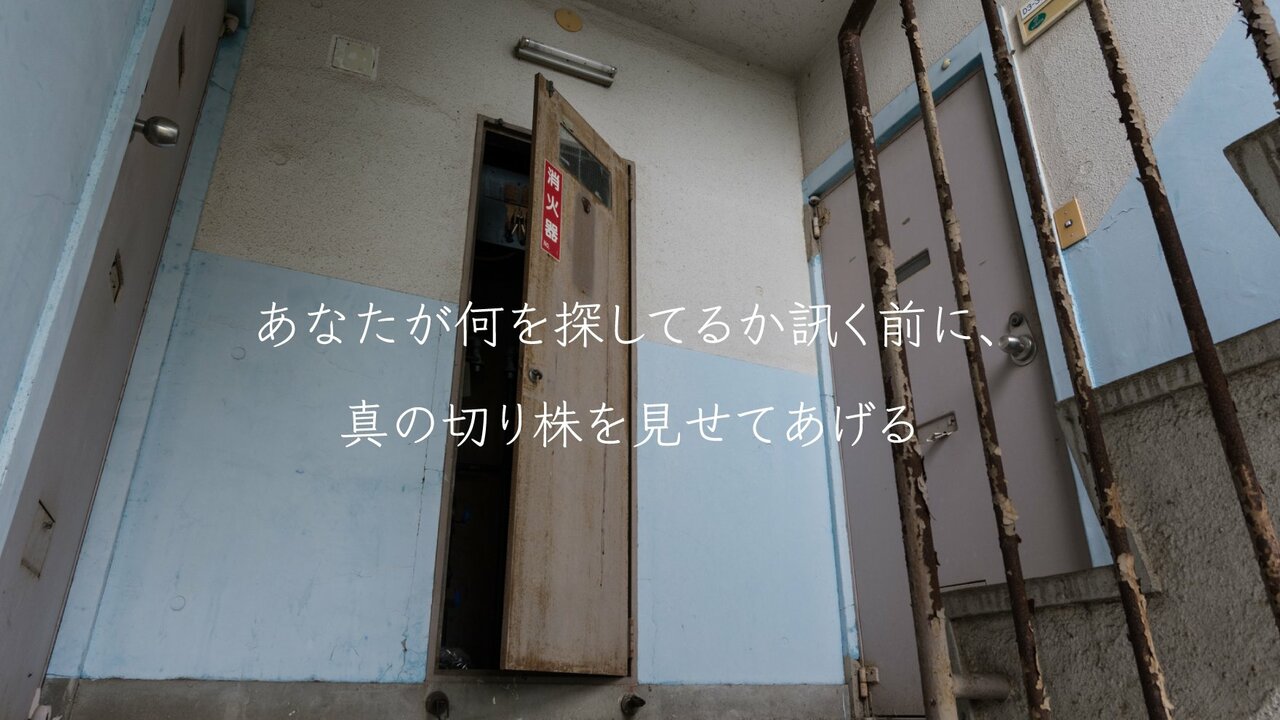岳也の家はどっしりとした二階建てで、壁は淡いモスグリーン、屋根は濃い緑色だった。芝生の庭には鉄製の白いイスが二つと、丸いテーブルが置かれてある。緑の芝生に白が映えて、なかなかおしゃれだと洋一は思った。
全体的に、岳也の家はとてもアメリカンに見えた。洋一が素直な感想を述べると、
岳也は「ああ」と納得したようにうなずいて、
「うちのおやじがアメリカのホームドラマが大好きでさ、ドラマに出てくるようなオープンで明るい家庭を作りたいってことで、こういう家になったんだ」
ガレージは家のすぐ横にあった。家と同じくらい幅があり、広々している。そんなところもいかにもアメリカ的だ。くしゃみさんって金持ちのぼっちゃんだったんだ、と洋一は思った。
ガレージの中には、ロイヤルサルーンという、少し懐かしい感じの車があった。壁際にはカワサキの赤いバイクと、ビアンキというペパーミントグリーンの自転車が一台、あとカゴ付きの黄色いママチャリが置かれてある。埃をかぶった水色のスクーターも一台隅に置かれていたが、現在は使われていないようだ。
くしゃみのサンプリングをしているという機材は、ガレージの結構なスペースを占めていた。小型のボーズのスピーカーに、洋一にはなんだかよく分からない黒っぽい機材と旧式の大きなパソコンが一台。それらが蔦のようなコードでつながっている。なかなか立派で、洋一は感心した。
「ちょっと待ってろよ……」
岳也がパソコンの電源を入れて準備をしているあいだ、洋一はルービックキューブをいじっていた。休みの日に外出するときは、ほぼ必ずといっていいほどルービックキューブを持ち歩いている。ちょっと時間が空いたときや手持ちぶさたなとき、くるくると回す。すると不思議と気持ちが安定するのだ。
幼い頃からの癖のようなものである。ルービックキューブを家に置き忘れた日は、なんだかずっと落ち着かない。ぼーっとしていると、手がムズムズしてきて無意識のうちに動いてしまう。
「たいしたもんだな」
岳也の声で、洋一は我に返った。「え?」
「それ。ルービック」パソコンを置いたデスクに軽くもたれると、岳也は腕組みをした。「六面、どれくらいでできちゃうの?」
「計ったことないから分からないです」
「しかしかなり早いよな」岳也は大げさに目を見開いて、「すげぇ。俺なんて一面すらできないのに」
「よかったら教えますよ」
「いや、いい」即答だった。「俺、そういうの根っから苦手なんだ。だってそれ、理数系だろ?」
「理数……」洋一は首をひねる。「そうなのかな」
「そうだよ。幾何学とかの分野でしょ。俺そういうの大の苦手だから。教えてくれても、多分永遠に理解できんよ」
パソコンから音がした。準備ができたらしい。岳也は素早く体の向きを変えるとマウスを操作し始めた。
洋一はルービックキューブを回し続ける。手の平に馴染んだ立方体は心地良い。指の動きに合わせて、面はなめらかに動く。ろくに手もとも見ず、洋一はただ手を動かし続ける。
ふいに周囲の音が消えた。無音の中、声が聞こえてくる。こうやって半ばぼーっとルービックキューブをいじっているとき、たまに聞こえてくるのだ。実際に空気を震わせて、鼓膜を通して入ってくる声ではない。声は直接、洋一の脳に飛び込んでくる。テレパシーみたいなものかもしれない。
初めて声を聞いたとき、洋一は特に驚かなかった。そういうのがあってもおかしくないかもしれない、と素直に受けとめられた。無心にルービックキューブをいじっているときは、意識がキンと研ぎ澄まされる。神経が拡張されて、キャッチできる音が広がるのかもしれない。