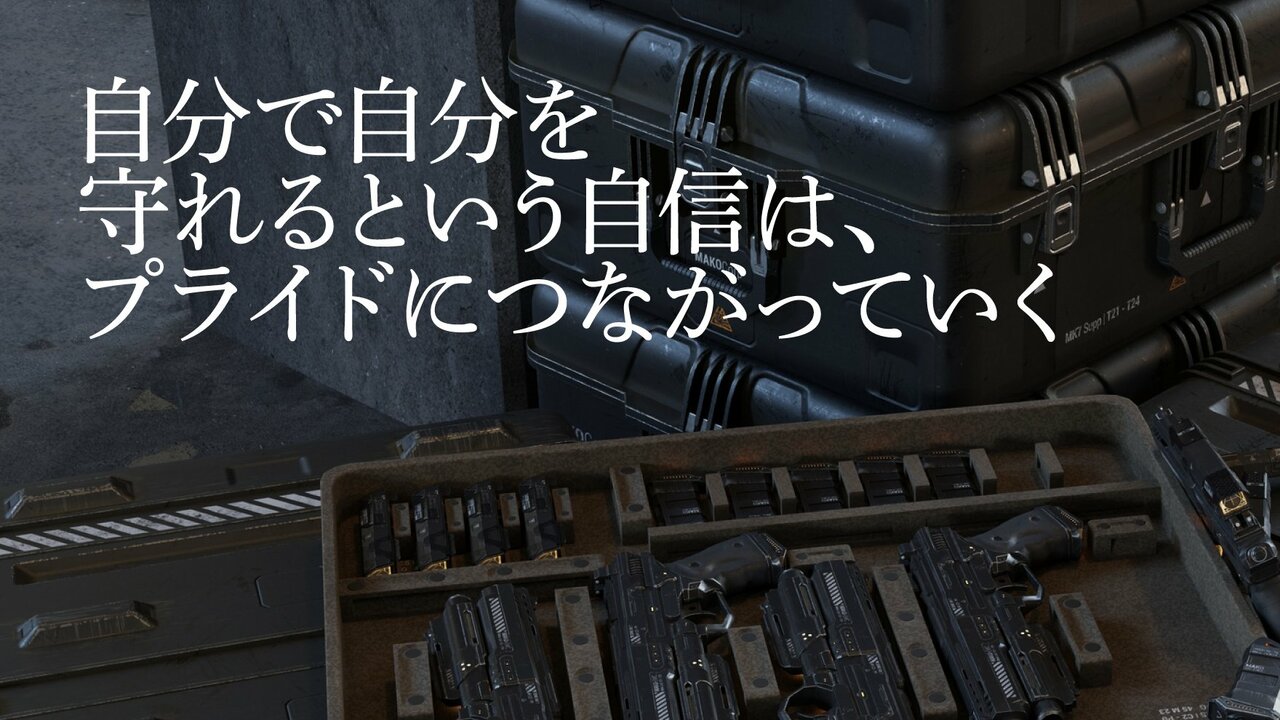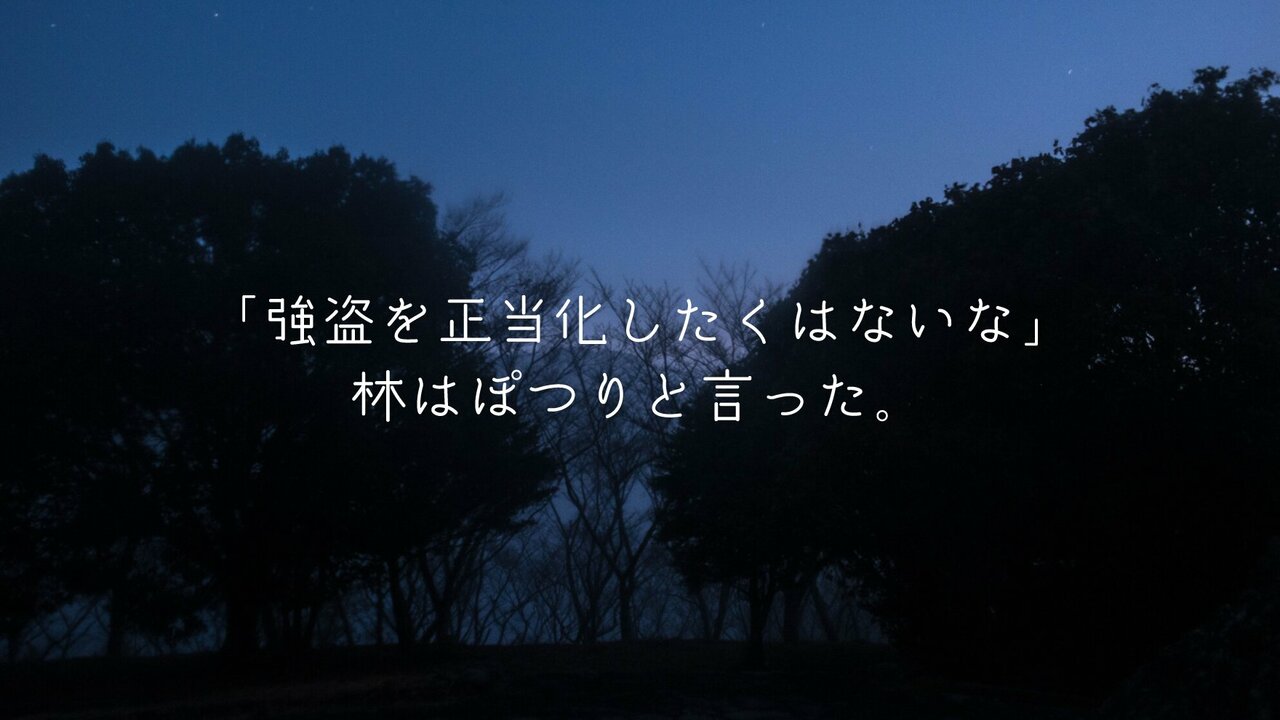Chapter6 理想と現実
ユヒトは穴の底に手を伸ばしウサギの耳を掴むと、木の槍から抜き取って高々と掲げた。痙攣するウサギの身体から、だくだくと血が滴(したた)っている。笹見平の若者たちは面を覆った。
彼らは肉屋の店先の肉は見ても、動物が殺される現場を見たことは無かった。むろん、肉食のために動物の犠牲が払われていることは知っていたが……。
ユヒトはいつまでもウサギをぶら下げていた。手の下でウサギはいつまでも痙攣していた。イマイ村の若者たちに「楽にしてやる」という発想は無いようだ。ユヒトもイニギもスソノも笑顔だ。動物愛護の精神など皆目ない。
「はい、きみたちに」
ユヒトは血だるまのウサギを林に差し出した。林はあまりにも無残で直視することもできなかった。
「うれしくないの?」
「いや、その……ありがとう」
林はそう言うので精一杯だった。
すると、傍らから中学生の女子がひとり進み出て、ユヒトからウサギを受け取った。彼女は持っていた麻袋にウサギをつっこみ、口を絞って両手でつかむと、ブンブン振り回して近くの木の幹に叩き付けた。それを五回ほど繰り返し、袋の中を覗き込んだ。そして
「もう大丈夫よ」と表情を変えることなく言った。
「何が大丈夫なの?」林は目を丸くした。
「私、おじいちゃんちが畜産農家で、いろいろな動物を絞めるのを見てきたの。イノシシやシカ、タヌキやウサギもね。出荷しないでウチで食べる分は、みんな最後にとどめを刺してあげるのよ」
「トドメ?」ユヒトが尋ねた。
「とどめというのは、やさしさよ」女子はユヒトに目を移した。「私たちは――笹見平の私たちは、動物が痛い目に遭っているのを見ると、まるで人間が痛い目に遭っているように感じてしまうの。ゲンダイに生まれた人は、みんなそう。だから、さっきみたいにこの子が苦しんでいたら、早く楽にしてあげたいと思うわけ」
ユヒトは首を傾げていたが、女子が何度か説明するうちに、半分くらいは理解したようだった。その上で、ユヒトは彼らが抱いている生命についての考え方を説明した。
「動物を殺すことにためらいは無い。狩りでためらっていたら逆に攻撃されるかもしれないからね」
「目の前で苦しんでいる動物に哀れみを感じないの?」
「イマイ村では多くの仲間が獣に殺され、食べられてきた。獣たちは哀れんだりしない。生きるために、獣も人間も真剣。お互いさま」
「でも……」
「哀れむくらいなら、最初から食べようと思わないことだ」
一行は、穴を片付けて引き揚げた。
若者たちは太陽が中天に差し掛かる前に笹見平に帰り着いた。引き続き、参加者はユヒトからウサギの解体を習った。皮を剥ぎ、身を裂き、内臓を取り出して、血を抜く。石包丁を扱うユヒトの手捌きは見事だった。まな板も水道も無いのに、きれいな桃色をした肉が取り出される。その肉を小分けにして串に刺し、火に炙る。一筋の煙が立ちのぼる。
「いい匂いがするなあ」
狩りには参加せず杭打ち工事をしていた盛江が、汗を拭いながらやってきた。匂いにつられて人が集まり、火の周りに人垣ができた。みんな鼻の孔をヒクヒクさせている。
「懐かしい匂いだ。なんだっけ、これ?」
「もしかして肉じゃないか?」
「肉? 肉って、あの食べる肉?」
歓声が高まっていく。林はみなに目をやり、
「今日のお昼は焼き肉だよ。今朝ユヒトたちと狩ってきたんだ」
「なんだって? 焼き肉? 一体何か月ぶりだろう!」
「でもウサギだよ」
「かまわないよ! 食べ盛りの若者が、肉も喰わずに肉体労働ができるかってんだ!」
そのままウサギ肉バーベキューが始まった。匂いを嗅ぎつけた連中はすさまじい勢いで肉に群がった。けれども、狩りに参加した面々は肉に手を付けなかった。彼らの目蓋の裏には、痙攣する血まみれのウサギが焼き付いている。
自分たちが生きていくために必要な犠牲と知りつつも、ショックを隠せない。ただ一人、ウサギにとどめを刺した女子中学生だけが、美味しそうに肉を食べていた。