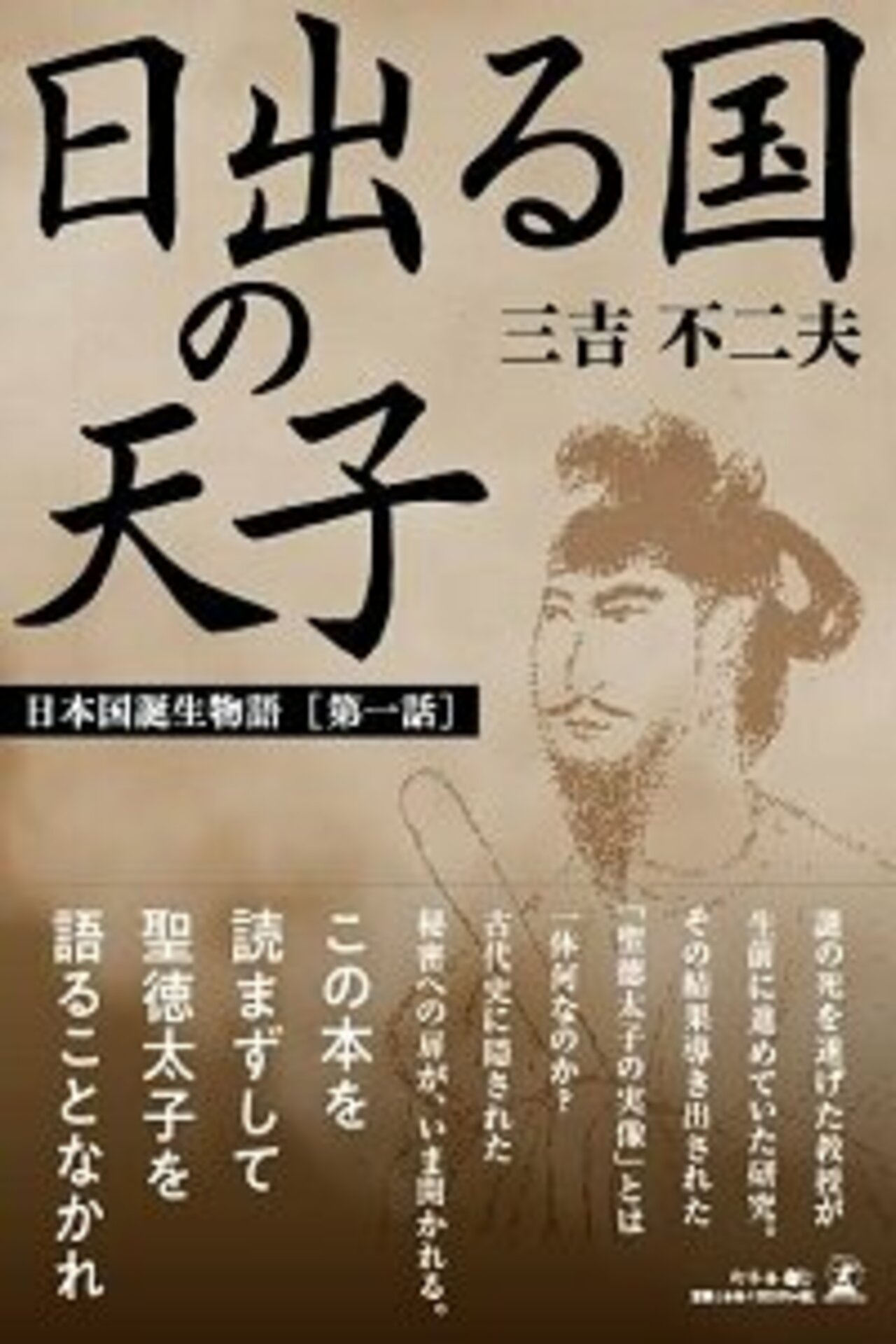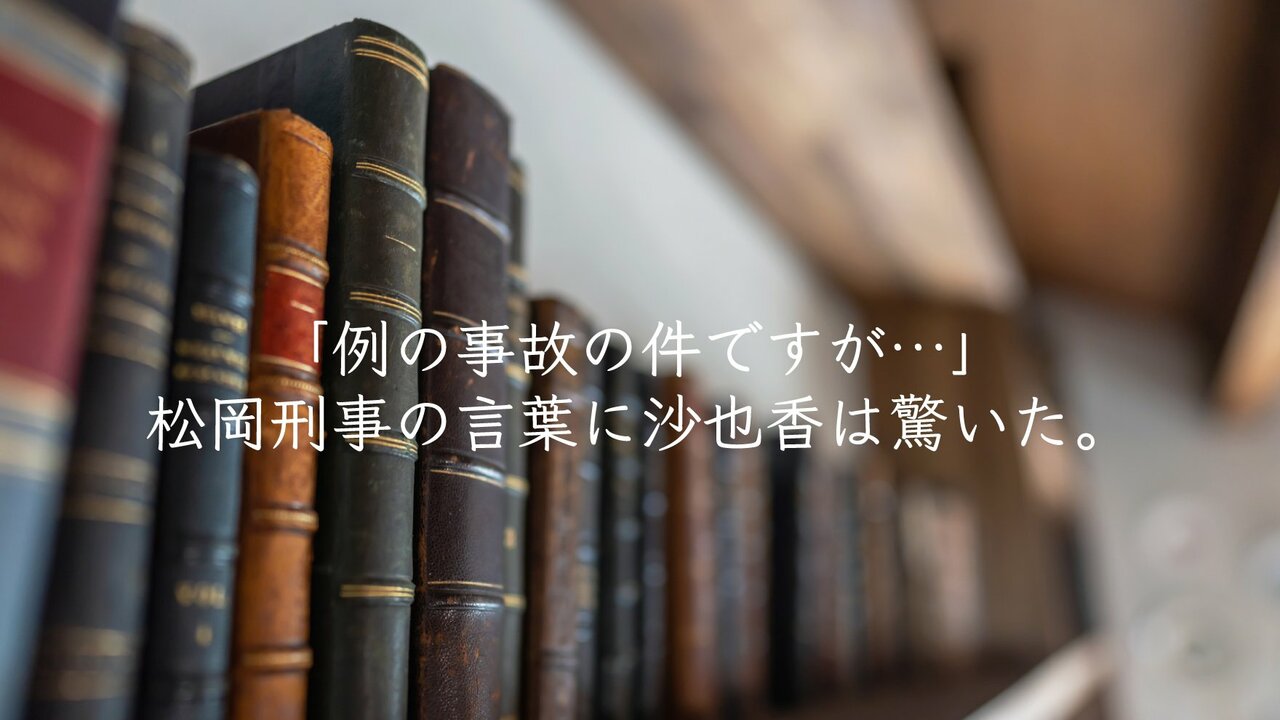第二章 日本のジャンヌダルク
1
眠い目をこすりながらまゆみがようやく起き出したのは、五時二十分になろうとするころだった。目覚ましは五時にかけていたのだが、二度三度とベルの停止ボタンを押し、惰眠をむさぼっているうちに二十分近くが過ぎていた。
あわてて跳ね起き、隣のベッドを見ると、沙也香の姿はない。そのままリビングに出ると、すでに着替えを済ませた沙也香がソファーに座ってテレビを見ていた。テレビは朝のニュース番組を流している。
「あれ? 沙也香さん、寝なかったんですか」
まゆみは驚いて聞いた。
「ううん、寝たわよ」沙也香はにっこりと笑った。「だけど、あなたみたいにぐっすりとは眠れなかったけどね」
「えっ、わたし、そんなにぐっすり寝てました?」
「そうよ。だって目覚ましが鳴っても起きなかったじゃない。わたしはあの音で目が覚めたんだけど、まゆみさんはなにかぶつぶついいながら、目覚ましを抱え込んでまた寝ちゃったでしょ。だからよっぽど眠いんだなと思って、起こさなかったのよ」
「やだ! そんなとこ見てたんですか。恥ずかしいなあ」
「いいじゃない。それだけ眠れるってことは健康な証拠よ」
沙也香は笑いながら冗談めかしていったが、もし自分がまゆみの立場だったら、もっと眠りこけているかもしれないと思う。自分と彼女とでは立場が違うのだから。
ガイド役を引き受けてくれた坂上慎二(さかがみしんじ)が、ホテルのロビーで待っていた二人の前に姿を現したのは、約束の七時きっかりだった。彼は沙也香を見ると、ぺこりと頭を下げた。
「大鳥沙也香さんですね。わたしは坂上と申します。どうぞよろしゅう」
「あ、はじめまして。大鳥です。こちらは松風出版の沢田さんです」とまゆみを紹介し、「今日は厚かましいお願いを引き受けていただき、ありがとうございます。今日一日、よろしくお願いします」
沙也香は丁寧にあいさつした。案内してくれる人がいるといないのとでは大違いだ。
「いやいや、こちらこそ」といって、坂上は改まった口調になった。「ところで、高槻教授は、大変な災難でしたなあ」
「そうですね。わたしはお会いする予定でしたのに、けっきょく、一度もお会いできませんでした。奥さまからうかがったんですが、坂上さんは高槻教授とおつきあいが深かったそうですね」