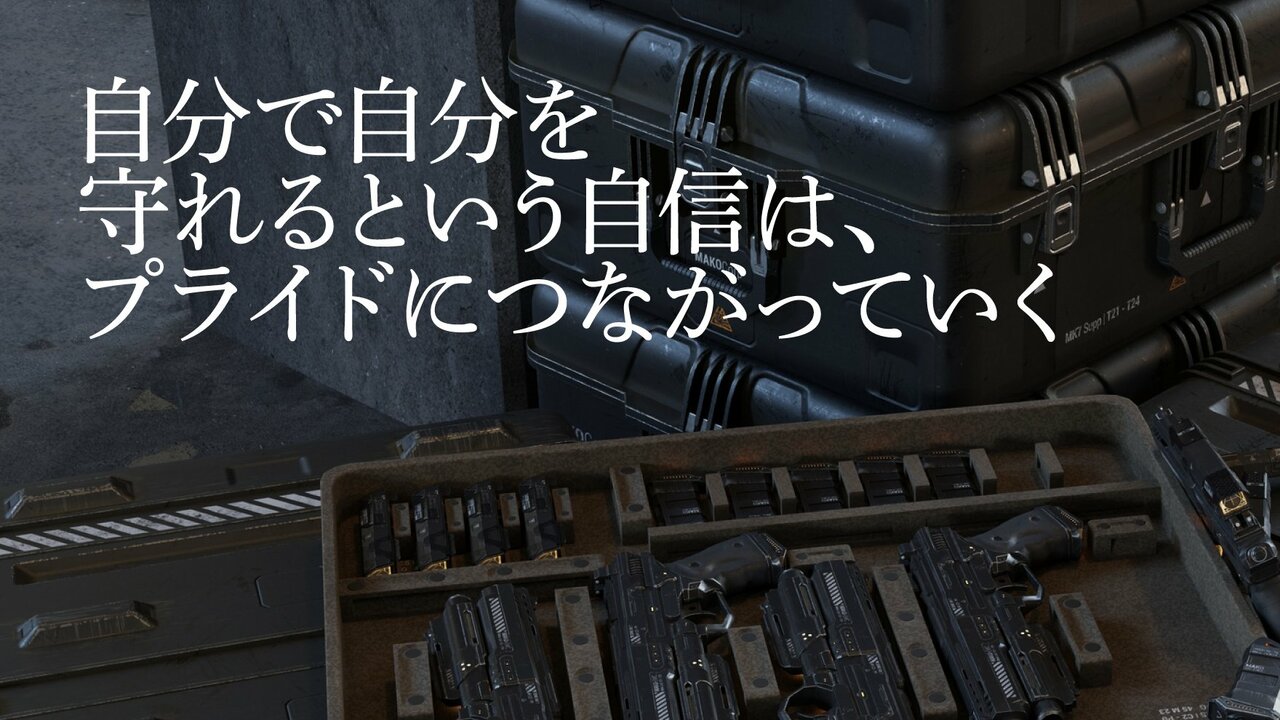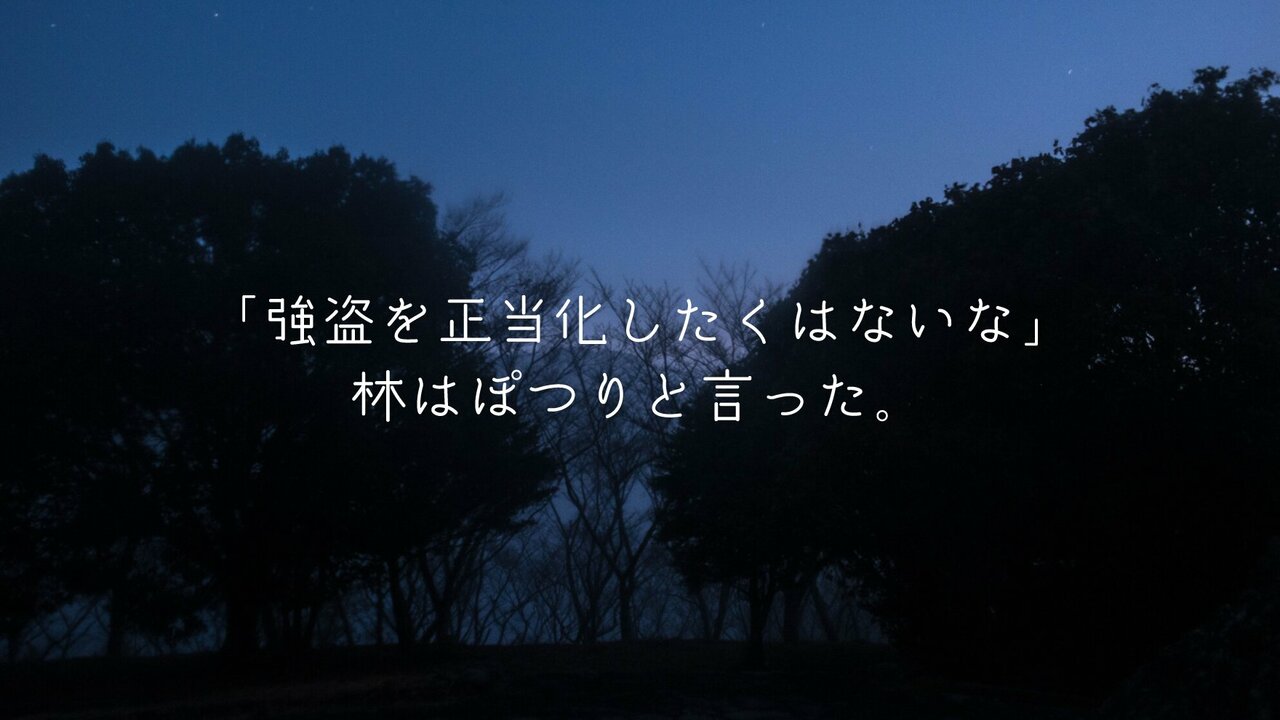Chapter5 対立
盛江の踊りは続いた。しばらくすると、数軒はなれた竪穴式住居の中から、真っ黒に日焼けした麻布姿の老人があらわれた。
長身で白髪白髭。細長い手足は、骨と皮ばかりで、筋が浮いている。痩せこけているが、肌艶はよく、節々ががっちりしている。皺だらけの顔に、細い目が埋め込まれている。老人は盛江らを見て顔の皺を忙しく動かした。
未知の連中の出現に驚いたようである。だが、子どもたちが陽気にしているのを見て、徐々に冷静さを帯びていった。
そうしている間に、他の住居から一人また一人と、大人たちが集まってくる。ほとんどが女性で、男性は老人が数人。麻布を全身にまとっている者もいれば、腰巻だけで胸をはだけている者もいる。人の数はみるみる増え、あっという間に周辺は雑踏と化した。彼らはいちいち老人に何か言った。どうやらこの老人は、集落のリーダー格であるらしい。
大学生たちはニコニコしていたが、本当は自分の心臓の鼓動が聞こえるほどドキドキしていた。
「林」砂川が耳打ちした。「今だ、スイカだ」
「え?」
「土産用に持ってきただろ!」
「そうだ、そうだった」
林は袋を広げ、中の藁を払ってスイカを取り出した。深緑に見事な雷模様を描くそれは、光を受けて堂々と黒光りした。
「これ……、その、お土産です」
丁寧に捧げ、前に進み出る。しかし縄文人たちは後ずさりするばかり。砂川は林に耳打ちした。
「今思い出したけど、スイカが日本に伝来したのは室町時代だった。みんなスイカを知らないんだよ」
「頼むからそういうことは早く言ってよ」
林は額の汗を拭い、スイカにかじりつくジェスチャーをした。
ガブリ、モグモグ、笑顔。
ガブリ、モグモグ、笑顔。
これを繰り返す。スイカが食べ物で、しかもおいしいということを伝えたかった。しかし反応は無かった。訝しい視線が注がれるだけ。
「毒を疑っているのかもしれない。食べて見せるしかない」
砂川は鞄からバールを取り出し、柄の尖った部分をぶすりと刺すと、力を入れてスイカを真っ二つにした。中には真っ赤な果肉が、皮ぎりぎりまで詰まっている。砂川はそれを指先で少しほじくりだして口に運び、大仰に「おいしー」と言い、縄文人に笑顔を向けた。
林も砂川と同じことをして見せ、長老に目をやり、おいでおいでの仕草をした。
長老はじりっじりっと歩を進め、スイカの前に辿り着いた。砂川と林を一度ずつ見ると、自分も果肉に指をつっこんで、すくって口に運んだ。すると、
「んっ、あァーッ!」
長老は叫んだ――眩しい笑顔とともに!
長老は村の衆に手招きをした。人々はスイカに殺到し、我も我もと指を突っこんで口に運んだ。大盛況である。
林と砂川はホッと息をついた。
集落の人々がスイカでにぎわっている中、林ら大学生は長老に近づき、両腕を開いてうやうやしく頭を下げた。長老は笑みを浮かべた。そして林らと同じように頭を垂れ、なんと、その後、手を差し伸べた。握手の習慣があるとは――林は丁寧に手を握り返した。