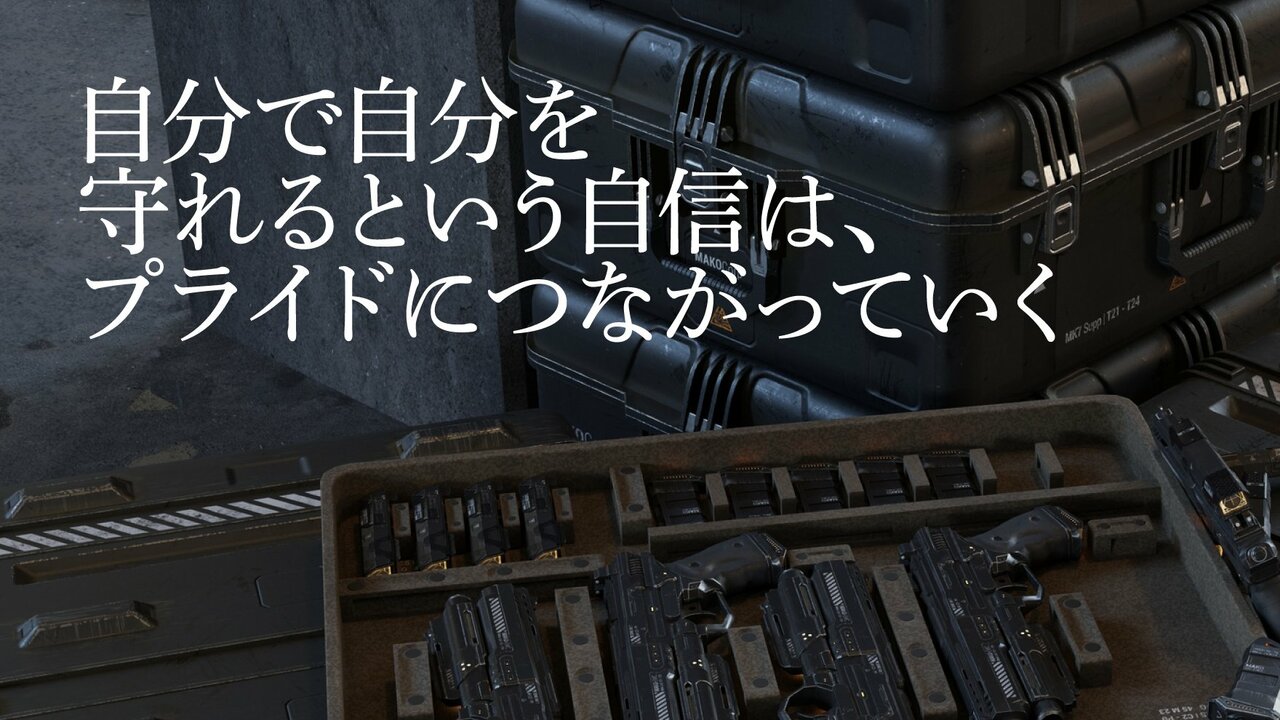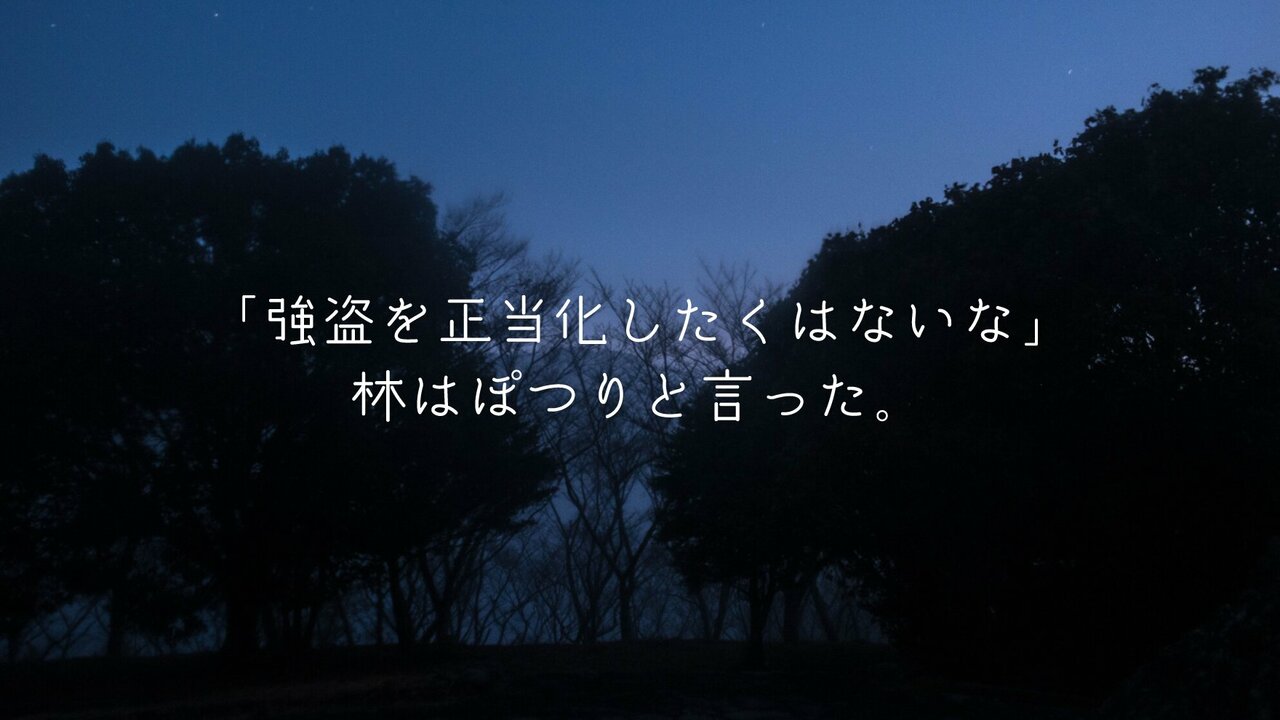「あの時計は原子時計を受信して正確な時間をはじき出すはずだ。完全に狂って、ただの電池の時計になっている」
「狂ったにしてもあんまり大幅過ぎるよね」
「林」
早坂は声を殺して言った。
「このことはまたいずれ考えよう。今はやるべきことがたくさんある。ヘタにみんなに言って不安がらせても何の得も無い。黙っておこうや」
★
キャンプは三日目を迎えた。もはや参加者にキャンプの意識は無い。はっきりしたことは分からないが、とにかく日常から切り離されたことは中学生にも分かった。
急にいろいろな不安が持ち上がってくる。水はどうする? 食料は?
持ち込んだ食材には限りがある。このまま食べて行けば、いずれなくなるだろう。五〇人もの大所帯が生きながらえるには、相当量の調達が必要だ。
真っ先に起きたのがトイレ問題だった。観光案内所には中と外に二つのトイレがあった。両方とも汲み取り式で、タンクに水を足せば水洗の機能を果たした。
みな何も考えずに使っていたが、二日目に便槽が容量を超え、汚物が溢れ出た。仕方なくめいめい草むらにするようになったが、近場の茂みなど場所は限られている。たちまち悪臭が漂うようになった。
乾きと飢えと不衛生。帰れる見込みの無い不安。全員の顔が憂鬱(ゆううつ)にかげっていく。
「くよくよしても仕方が無い。むしろこれこそキャンプの醍醐味だよ」
林は呼びかけた。彼も不安には違いなかったが、リーダーがそれを顔に出すわけにはいかない。健気に振る舞うリーダーの姿を、中学生リーダーの川田と木崎は真っ直ぐに受け止めた。
林には早坂や盛江に無い独特なムードがあった。それは他人をして「この人を放っておくわけにはいかない」と思わせる、頼りなさとも可愛げともいえる雰囲気だった。
それでなくても、二人は「自分らが中学生をまとめなければ、大学生の足手まといになる」という意識を持っていた。つい三日前まで口も利かない非行少年・少女だったのが見違える成長である。この三日でにわかに協力的になった中学生に大学生は感心した。「この子たちを守っていかなきゃ」という思いが日増しに強くなった。