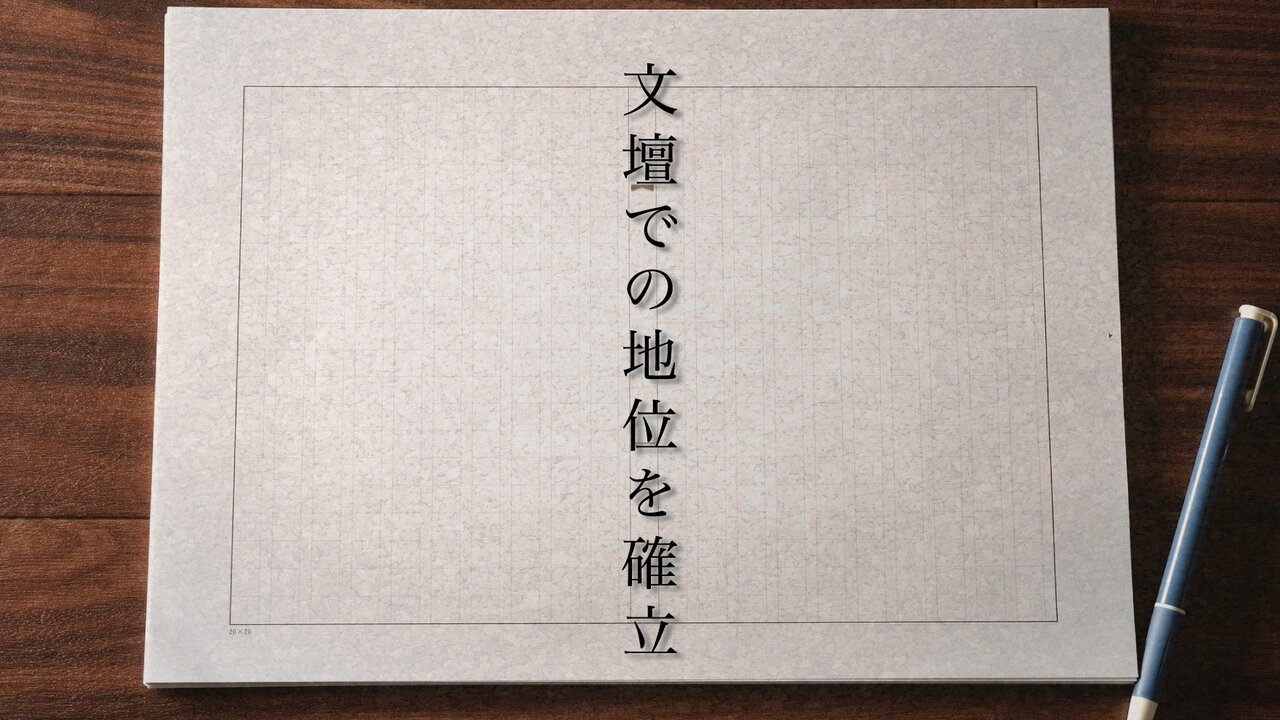天才の軌跡② 谷崎潤一郎の精神分析(視覚の無意識的意味)
二十四才の時、彼は月謝滞納で大学を退学させられている。しかし同じ年に彼は『刺青』を書き、翌年永井荷風が、「谷崎潤一郎氏の作品」を三田文学に発表し、中央公論に『秘密』が掲載されて文壇での地位を確立している。
彼の処女作『刺青』には、短篇であるのにもかかわらず、彼の病的傾向のすべてが書かれている。すなわち、サディスト的傾向、マゾヒスト的傾向、フェティッシュ的傾向である。この小説の冒頭の一文中彼は「女定九郎、女自雷也、女鳴神、――当時の芝居でも草双紙でも、すべて美しい者は強者であり、醜い者は弱者であった」と書いている。
そして、「清吉という若い刺青師」は娘の背に針を刺している間は強者であるのだが、女郎蜘蛛の入墨を刺し終わると「折から朝日が刺青の面にさらして、女の背は燦爛とした」のであり、強者と弱者の立場が入れ換り、弱者となった刺青師は「肥料」になってしまうのである。
筆者は、この処女作の中に、眼という器官に対する作者の無意識的意味が明確に表されているのではないかと考える。「刺青師に堕落してからの清吉」は当然谷崎潤一郎の分身であるが、彼は「光輝ある肌を得て、それへ己れの魂を刺し込むこと」の望をかなえた後、彼は「真っ白な」素肌を持つ娘の背が「燦爛」とするきらめきの中では、「肥料」でしかないのである。
この小説は「絢爛」「潤沢」「金色の波紋」「燃えるように照った」座敷、「反射する光線」「しらしらと白み初めた時分」等というまばゆい光の世界である。そして、この光を象徴するものは、「剣のような瞳を輝かした」女なのである。
谷崎潤一郎にとっての美の原型は「錦絵に描かれるほどの美人」であった母である。そしてこの母は自叙伝的作品といわれる『異端者の悲しみ』を信ずれば、夫を「親子の者が、こんな長屋住居をするようになったのは誰のお蔭だ!」とだまらせる気の強さもあり、「一遍でも自分で朝飯を焚いたことがなく」、夫が朝食の用意をした頃「蒲団を這い出して来る」ような女性でもあったという。
これが明治時代であったということを考えると稀有なことであったと言えるであろう。これらのことを総合してみると、谷崎潤一郎は、美しいが気の強い母親を恋しく思う(『母を恋ふる記』)と同時に、自分と離れてあるまばゆい存在として恐れつつ見ていたのではないだろうか。『刺青』の中の女が、剣のような瞳をもっているのは、ギリシャ神話のメデューサの、見た者を石に変える力、怖さを感じさせ、見ることの恐ろしさを連想させる。
清吉が、「肥料」となるのも、この剣のような目のためとも考えられる。つまり視線には人間を対象物化(あるいは非人間化)させる力があり、谷崎潤一郎にとって、目が見えるということは、自分と母の隔たりを明確化するものであり、母の視線は、自分を物体に変え、母とのつながりを絶つものと感ぜられたに違いない。
このことについての描写は、『春琴抄』でさらに明らかになっている。これは九才の時に失明した春琴とその弟子の佐助(温井検校)の物語であるが、この佐助は、春琴が熱湯をあびせられたあと、無残な火傷を見ないようにと、「我が目の中へ針を突き刺し」盲目となる。
そして、「今まで肉体の交渉はありながら師弟の差別に隔てられていた心と心が始めて犇(ひし)と抱き合い一つに流れて行くのを感じた」という。すなわち美しい春琴は醜くくなり、佐助は目をつぶして初めて二人は「一つ」になったのである。