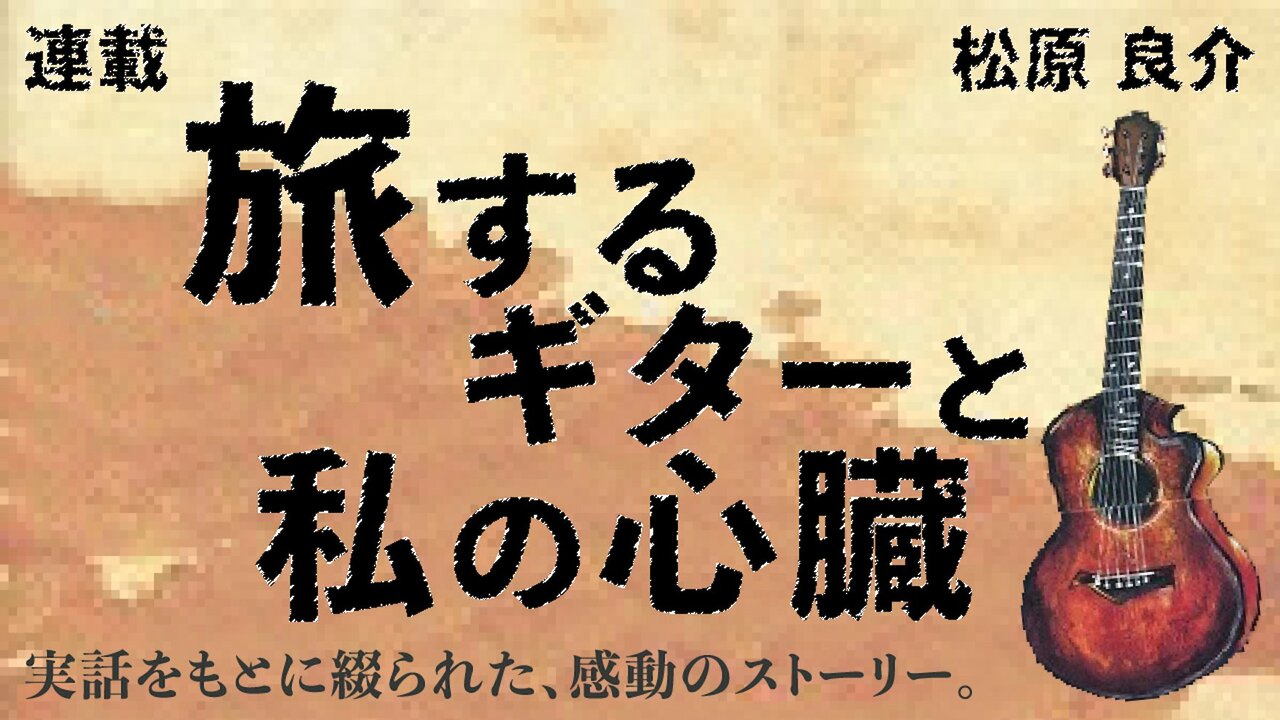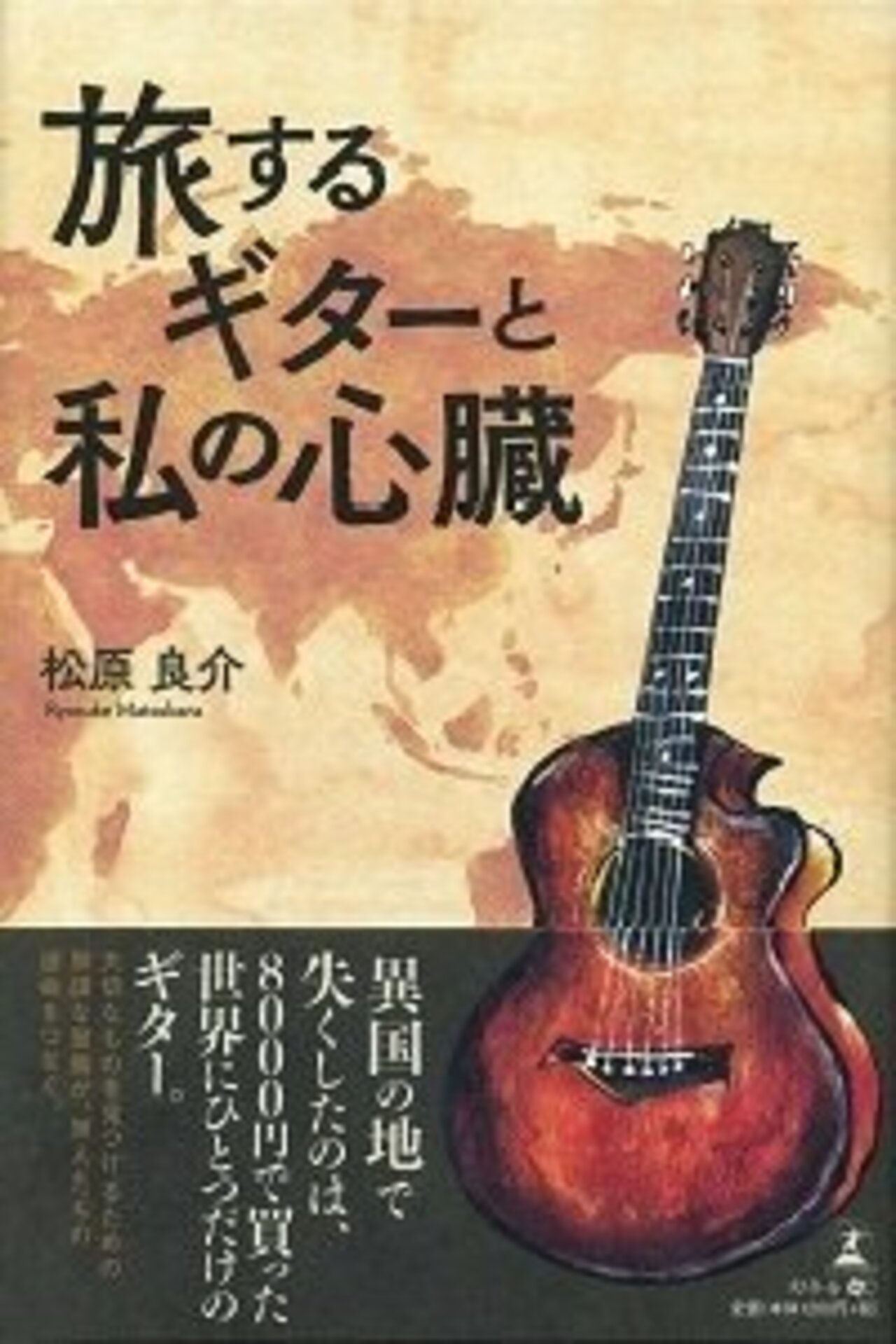世界で一番おいしいタイティー(山平遥)
翌日、遥はバンコク市内の市場を一人で訪れた。
何か目的があって来たわけではなかった。ただ、下がってきたモチベーションを取り戻すため、外に出て街の活気に触れたかった。遥は市場の人と一言二言会話を交わすだけでワクワクした。自然と足が軽くなる。
遥は小物入れとピアスを買った。麻で作られたピンクと赤の縞模様の小物入れは財布の代わりにするつもりだ。
もともと雲行きの怪しい空模様だったが、昼を過ぎた頃になると、雷鳴とともにそれまで雲の上にため込んでいた雨が降り始めた。
遥はうんざりした様子で近くにあった大衆食堂の屋根の下に避難した。幸い雨には濡れなかったが、空に広がる灰色にくすんだ雲を眺めて遥もどんよりした気分になった。
市場の露店は慌ただしく片付けを始めていた。
「あらら、結構降ってるね。あれ? 遥さん?」
遥の後ろの大衆食堂から、ひょっこり祐介が出てきた。
「あ、祐介さん!」
遥は思わず祐介に驚いた口調で話しかけた。
「ほんと、ここのところずっとこんな感じなんですよね」
遥は雨を吐き出す黒い雲に目を向けて、つまらなそうに言った。
「これはしばらく止まないね」
「そうですね。せめて、どこかゆっくりできるところに移動できるといいんですけど……」
雨宿りをする二人の足元にも、徐々に水たまりができ始めた。
「あ、そうだ! 祐介さん、ギターの話まだですよ!」
遥はここぞとばかりに、昨日聞きそびれたギターのことを話題に出した。
祐介は話したくないのか「あー、それね」と、作り笑いでごまかした。
「ちょっと! 私も話したんですから、祐介さんも話さなきゃだめですよ!」
「ギターの話かぁ……」
祐介は少し考え込むような顔をしてみせると、
「ねぇ、遥さん、世界で一番おいしいタイティー飲まない?」
少し伸び始めた無精ひげを触りながら言った。
「世界で一番おいしいタイティー? 何ですかそれ?」
スコールの音で聞き間違えたかと思った遥は聞き直した。
「うん、あそこなんだけど」
祐介は20メートルほど離れたところにある一軒のカフェを指さした。
「あそこのタイティーは世界で一番うまいんだ」
祐介は淡々と話した。
「え? ほんとですか?……って話を変えようとしてもダメですよ! そもそもタイティーのおいしさに世界一とかあるんですか?」
疑うように遥が尋ねると、祐介はあたりをキョロキョロして何かを探し始めた。
そして近くにあった大きめの段ボールを拾い上げると、それを頭上に掲げた。
「はい、そっち持って」
頭上の段ボールの右端を祐介が持ち、もう一方の左端を遥が持つと、それはちょうど二人が入れるくらいの傘になった。祐介は遥と目を合わせて、もう一度雨の降る先に目をやった。通りに走っている車はなく、歩いている人もいない。
「よし、いくよ!」
祐介の掛け声で、二人はスコールのなかに飛び出した。
頭上の段ボールを容赦なく雨が叩いた。
何度か水たまりに足を突っ込んだが、遥はそのたびに子どものような笑い声を上げた。
やがて二人は、メインストリートに面した「95」という文字が看板に書かれたカフェに到着した。なかに入ると店内はオレンジと黒を基調とした欧米風の作りになっており、ショーケースの中にはお洒落なケーキが並んでいた。こういうカフェにずっと行きたかった遥は、すっかり気を良くしていた。
祐介が「通りが見えるから」と言いながら2階席に向かったので、遥もそれについて行った。2階に着くと、そこにはカウンターが4席とテーブル席が5席あり、今は欧米人の若いカップルが一組しかいなかった。二人の衣服や髪は濡れており、彼らも我々と同じく、雨宿りのためにここに飛び込んだのだろうと、遥は思った。
遥と祐介の二人は空いている窓側の席に向かい合って座った。店内はエアコンが効いており、雨に打たれた後だったので少し肌寒く感じた。二人は上着を椅子にかけて乾かしながら、お互いの情報を交換した。
年齢や、出身地、家族のこと、日本での仕事のこと。ちなみに遥は自分のことを“遥さん”と呼ばれると恥ずかしいということも伝えた。注文したタイティーが二人の前に運ばれてきた頃には、二人は歳の差を忘れてすっかり打ち解けていた。
「おいしそう! これが世界で一番おいしいタイティー?」
屋台などで売っているタイティーとは少し違い、上品なグラスに注がれたタイティーの上には生クリームが乗っており、さらにその上にはミントが添えられていた。
遥はスマホを取り出して、それを写真に収めた。その様子を祐介は笑って見ていたが、後になって結局自分もタイティーの写真を撮っていた。
遥は世界一のタイティーを味わってみた。ストローから上がってくるオレンジ色の液体が口のなかに入ってくると、紅茶の風味と濃厚な甘さが口いっぱいに広がった。
「おいしい! すっごく濃厚ですね!」
「あ、ホントだね。おいしいね」
とぼけた様子で祐介が言った。