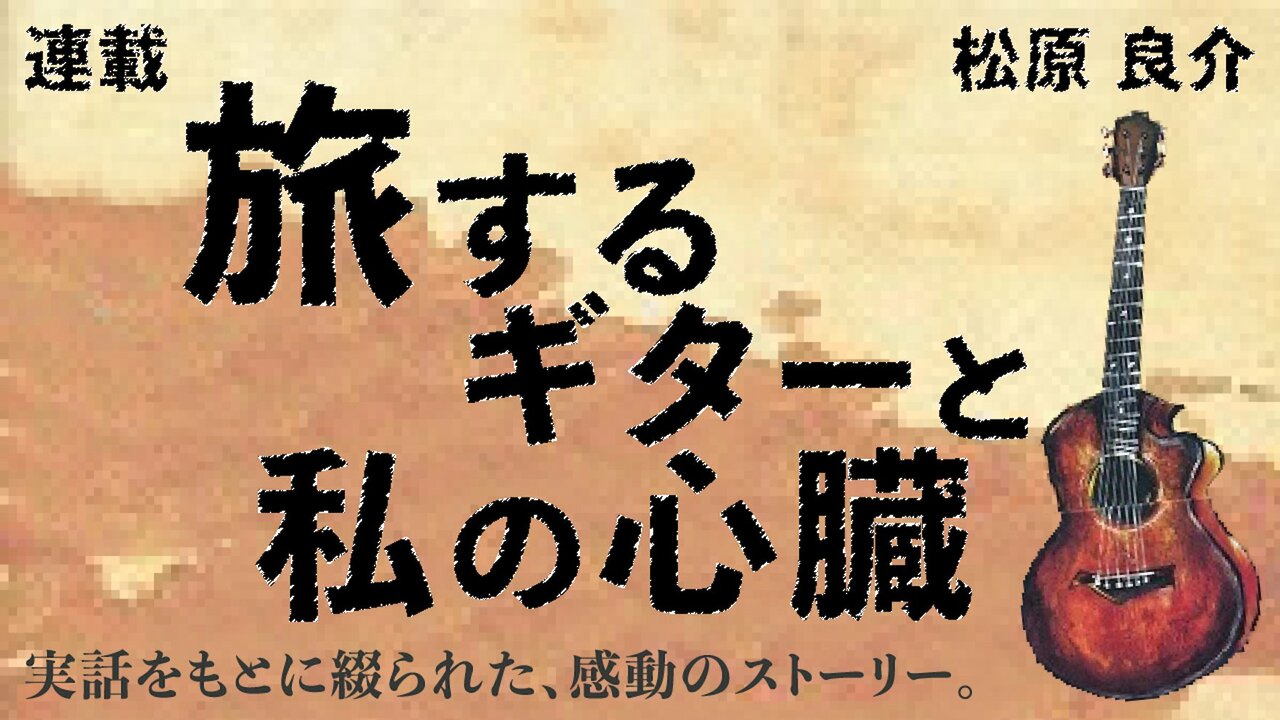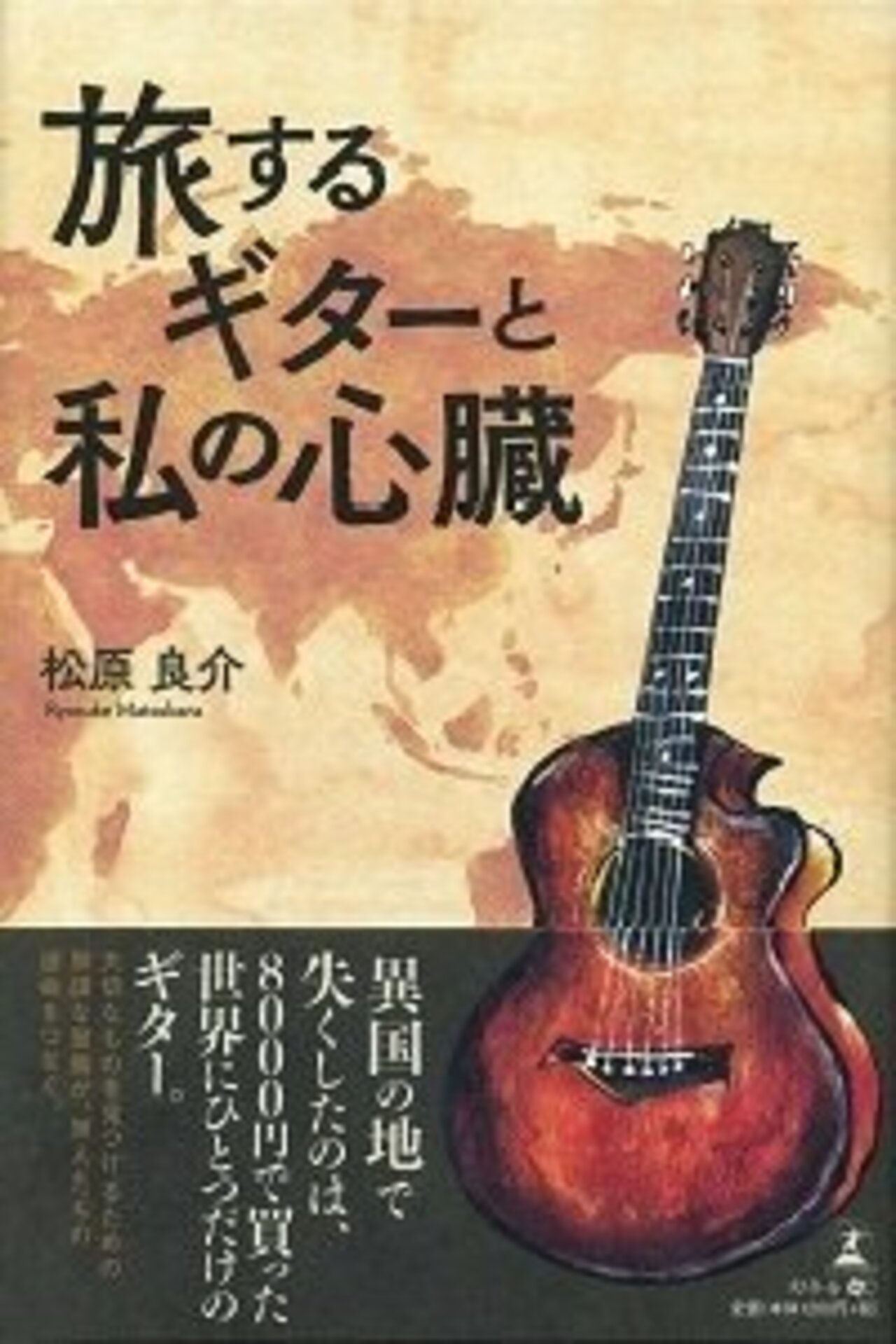〈宇山祐介の事情〉 友の旅立ち
2013年5月。
「今さらこんなこと言うのも変だけど、お前ほんとに行くのか?」
私(宇山祐介)は成田空港の国際線に向かう電車のなかで、哲也に尋ねた。
退院したばかりの哲也が “旅に出る”と話したとき、周囲の人間は冗談だと思って苦笑いするだけで、私もそのうちの一人だった。
“心臓に障害を持った自分が異国でギターを教えながら旅をする様子をブログで発信する”それが哲也の出した結論だった。
「制限がある今の俺の人生だからこそ、できることがあると思うんだ。俺と似たような境遇で悩んでいる人たちが、新たな可能性を見つけて一歩を踏み出すきっかけになってくれれば、俺が旅することに意味はあると思うんだ」
哲也は本気で言っているようだった。
そのときは、何かにすがりたいのであろう彼の気持ちを察して、皆「そうか」と曖昧な返事を返すことしかできなかった。まさか本当にこの日が来るとは誰が考えただろう。
海外に長期で旅行する場合、もしものことを想定して海外旅行保険に加入する。心臓に疾患を抱えた哲也は、普通なら保険など入れるはずもなかったが、どこでどう探してきたのか、一社だけ彼を受け入れてくれる保険会社を見つけてきた。
彼は着々と旅の準備を進め、マニラ行きのチケットを購入し、あとは出発するだけとなった。ここまでくると彼を止められる者は誰もおらず、無事を願って送り出すだけだった。
空港では大きなバックパックがかぶさるように哲也の背中を覆っていた。その見慣れない姿は見送りに来た者の気持ちを不安にさせた。隣にいた大谷はその雰囲気を壊そうとやけに饒舌だった。
「お前が旅の途中で野垂れ死んでも、教室は俺が引き継ぐから、安心して行ってこい」
昔と変わらない口調で大谷がそう言うと、哲也は拳を作って軽く大谷の胸をたたいて笑った。
搭乗手続きを済ませると、哲也と大谷、私の3人で近くのカフェに入った。
2階にあるこのカフェに行くときも、哲也が息を切らせながら階段を上がる様子を見て心配になった。店内は少し混みあっていたが、タイミング良く空いたテラス席に3人は腰を下ろした。テラス席からはチェックインカウンターが一望でき、大きな荷物を持ったさまざまな人たちが列に並んでいた。
今まで海外旅行にそれほど縁がなかった私は、そこに座っているだけで異国にいるような浮わついた気持ちでいた。隣のテーブルでは、これから旅行に行くであろう4人組の若い女性が写真の撮り合いをしていた。哲也はぼんやりその様子を見ていた。
これから哲也がフィリピンへ旅立つというのに、3人で話すことは大して内容もないことばかりで、ほとんどが大谷の調べてきたフィリピンの夜遊びや風俗の話ばかりだった。
まとわりつくようなまったりとした時間は心地良く、3人でテーブルを囲んで、くだらない話をしていると、20年前に時間がスライドしたような錯覚を感じた。
「すみませーん。写真を撮っていただけますか?」
急にカメラを持って話しかけてきたのはショートカットの元気のいい子だった。隣の席にいた4人組の女性の一人だ。おそらく大学生だろう。
「もちろんです」
と隣の大谷が得意げに名乗りを上げた。
大谷は女性からカメラを奪うように取り上げると、逆光にならない場所まで彼女たちを誘導した。それから、慣れたように写真のアングルについて指示をだすと女性たちもまんざらではない様子で従っていた。
「なんか懐かしいな、こういうの」
私は椅子にもたれながらボソッと言った。哲也はニヤニヤしながら何も返さなかった。
大谷が写真を撮り終えると、
「よかったら写真撮りましょうか?」
と、ショートカットの女性が、まだ幼さの残る笑顔をこっちに向けて言った。30を過ぎた我々は顔を見合わせて困った顔をしてみせた。
それから30分ほどするとカフェの客はほぼ入れ替わり、さきほどの女性たちも少し前に会釈をして出て行った。
「俺もそろそろ行くよ」
哲也はパスポートを取り出し、挟んである航空券に記載されている時間をもう一度確認してから言った。
「見送りって保安検査場の手前まで行けるんだよな?」
大谷がジャケットを羽織りながら言った。
「ああ、別にここでもいいけど」
と哲也は突き放すように言ったが、大谷はまるで聞こえていないようにテーブルの上にある3人分のコップを片付け始めた。大谷にさっきまでのふざけた雰囲気はなく、隠しているようだったがピリッとした緊張感をまとっていた。
私には心臓に爆弾を抱えた哲也が無事に旅から帰ってこられるとは考えられなかった。口には出さなかったが、これが最後の別れになることすら頭をよぎる。大谷もおそらく同じことを思っているだろう。
保安検査場に到着すると、そこにいた二人のスタッフが、乗客のパスポートと航空券を確認していた。
「ありがとな、見送りしてくれて」
そう哲也はぎこちなく言ったが、私は何を話していいのかわからなかった。
「じゃあ、いくよ」
と言って哲也はこちらに右手を差し出した。
シャツから除く哲也の右腕はやせ細っていて、とてもこれから旅を始めるような身体ではないことが一目でわかった。別れ際に握手をするとその手は冷たく感じた。「じゃあな」というあっさりした別れの言葉を残して哲也は背中を向けた。
パスポートと航空券を大事そうに持った彼は一度もこちらを振り返ることなく、キョロキョロしながらゲートの奥へと消えていった。私も大谷もお互いの持つ不安を口に出せないまま、しばらくそこに立ちすくんでいた。