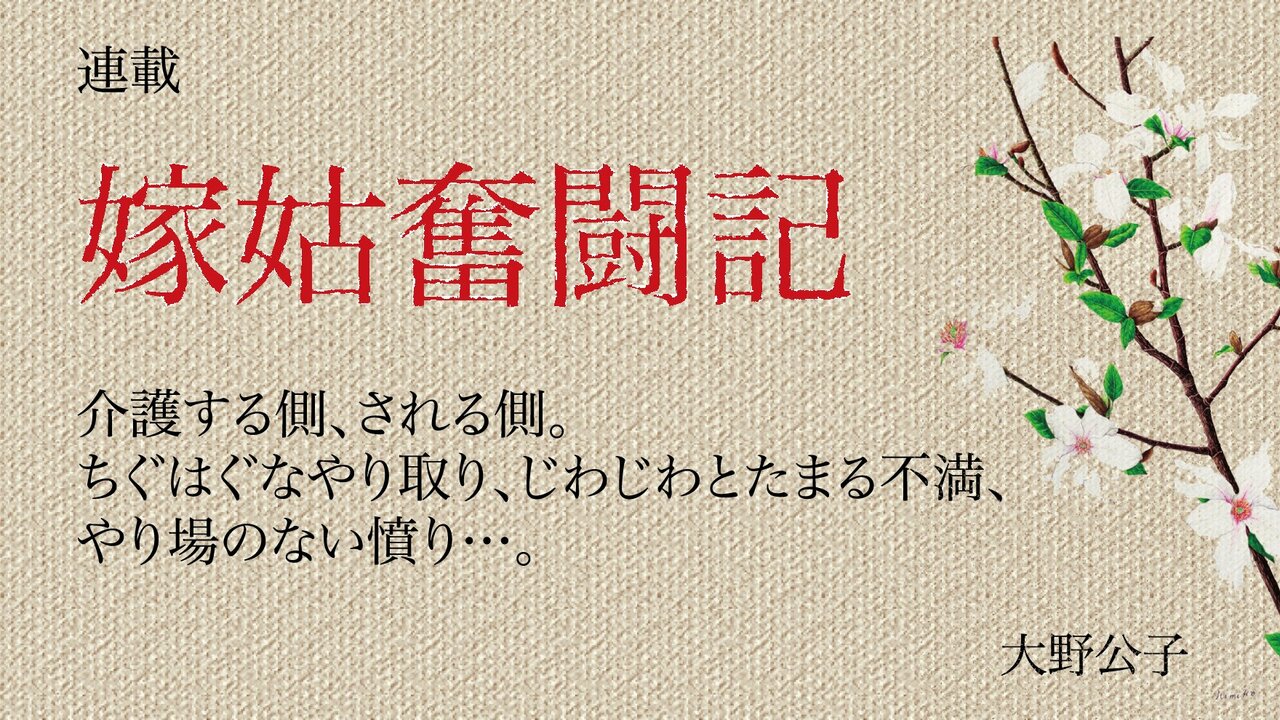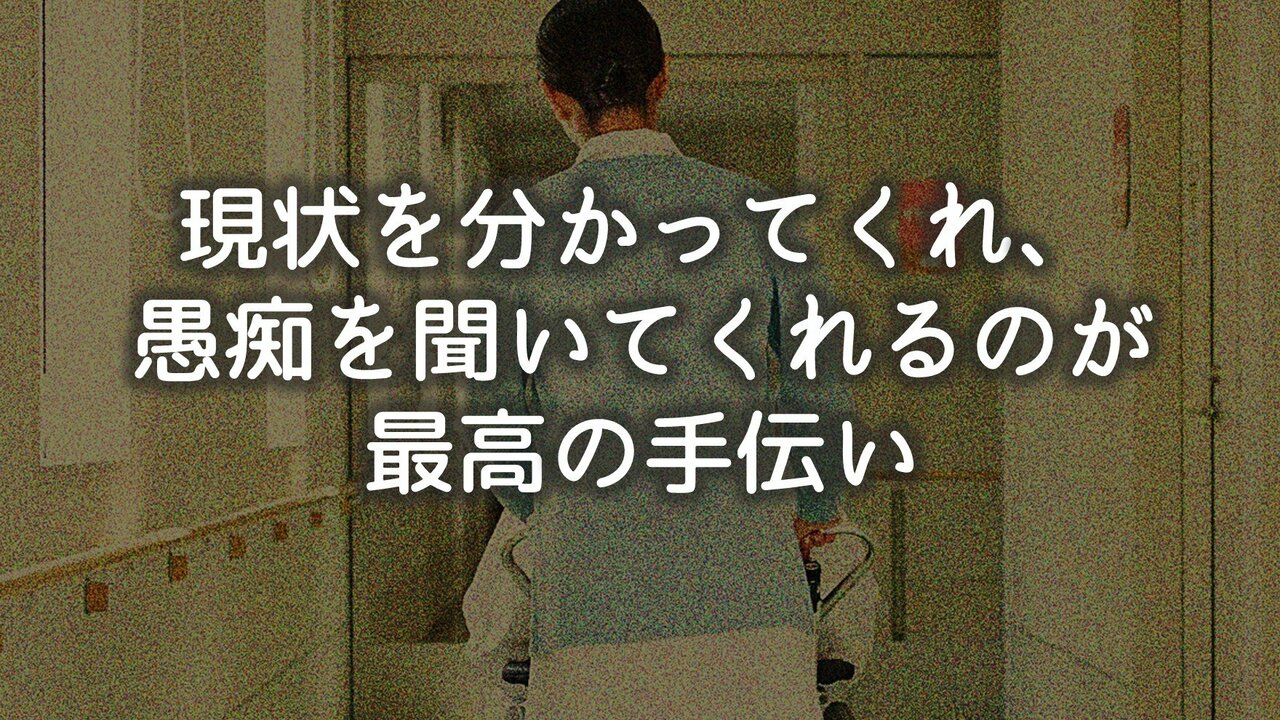第一章 嫁姑奮戦記
この時改めて悟ったのだ。人には潜在的にすごい能力が備わっていることを。しかしどうして、こういう時にその力を発揮するのだ。自由になりたい一心からか。
その夜は夫と娘が付き添う。明け方まで妄想が強く、店をまた始めるとか葬式の段取りはどうなっているかと言ったり、相変わらず動き回るし点滴は抜こうとするし、自分たちが休めないので手を縛ったそうだが何度も解かれ、その集中力にはまいったとのこと。やはり潜在能力のなせる業だ。
滅多に居ない息子が様子を見に来る。義妹は何かと気を使ってくれ、勤め帰りによく立ち寄り食べ物や花を持って来てくれたり、行き帰りに便利なように自転車を貸してくれたりする。おかげで後々までずいぶん助かる。
私も帰ったら帰ったで用事が多い。今年の四月は季節はずれに暑いので草花も一月ほど成長が早い。いつの間にか花を咲かせている。皆も水はやってくれるが私がそれどころではないので、やはり可哀想だ。
二日続けて夫が泊まってくれたので、久しぶりに花の世話や姑のタンスの衣類の洗濯、整理などする。私の姉たちが見舞いに来ると言うので夫と交代する。さぞ二晩大変だったことだろう。
「おかんの元気なのには俺も付いていけへんわ。一晩中手すり持って起き上がるわ、点滴は抜こうとするわ、手すりの紐は解くわで一時も目が離されへん。俺も寝んと体もたんから、手しっかり縛って寝させてもろたわ」と陽気に言う。
深刻に思ったらとてもやっていけないのだ。元々楽天家なのだが。手すりはあらゆる所を紐で縛ってある。そうしないとすぐ外してしまうからだ。右脚を引っ張っているので手すりを外したら逆さ吊りになりかねない。この元気を私たち介護人に分けてほしいものだ。
姉たちが来ると丁寧に礼を言い、話をする。普通と変わらない。しかし、二、三時間も居ると異常さが分かり、顔を見合わせている。
「これじゃやりきれないわねえ。介護する側が潰れないようにしなきゃ。何か手伝うことがあったら遠慮しないで言って」と言ってくれる。看病や介護する者にとって、現状を分かってくれ、愚痴を聞いてくれるのが最高の手伝いなのだ。相手にとっては迷惑なことだろうが、こちらはそれで元気を取り戻し、また介護が出来るのだ。
ひとめ見て、「こんな患者さんなら楽だ。親を看るのは当然と違うか」など言った見舞い客が帰った後は心穏やかならぬものがあり、見舞品を捨ててしまえと思ったほどだ。
その日の夜中におむつに手を突っ込み手がうんちまみれ、当直の看護婦さんと洗浄したり消毒したりシーツを替えたり大変だった。本人は夜中のことはからきし覚えていない。
私が翌日そのことを言うと、「うち、ちゃんとトイレに行ったで」と言う。「看護婦さん二人と三人で大変だったのに覚えてないの?」と言っても、そんなことするかいなと、おむつに手を突っ込む。「それ、そんなことするから手に付くのやないの、やめて」と言うと、突っ込んでへんでと言い張る。
無意識にするのだろう。これでは言っても仕方がない。困ったものだ。これがショックだったのかどうか分からないが、この日は日中もかなり混乱する。「今日はお祝いの膳やから全部食べなあかん」と今まで食べるのを嫌がった食事をぺロリと平らげる。
「何のお祝いなの?」と聞くと、「今日は成人式やろ」と言う。およそ冠婚葬祭、祝祭日には無関心、不参加を通して来た姑が入院してから異常なほど関心を持つのはどうしてなのか、不思議でならない。