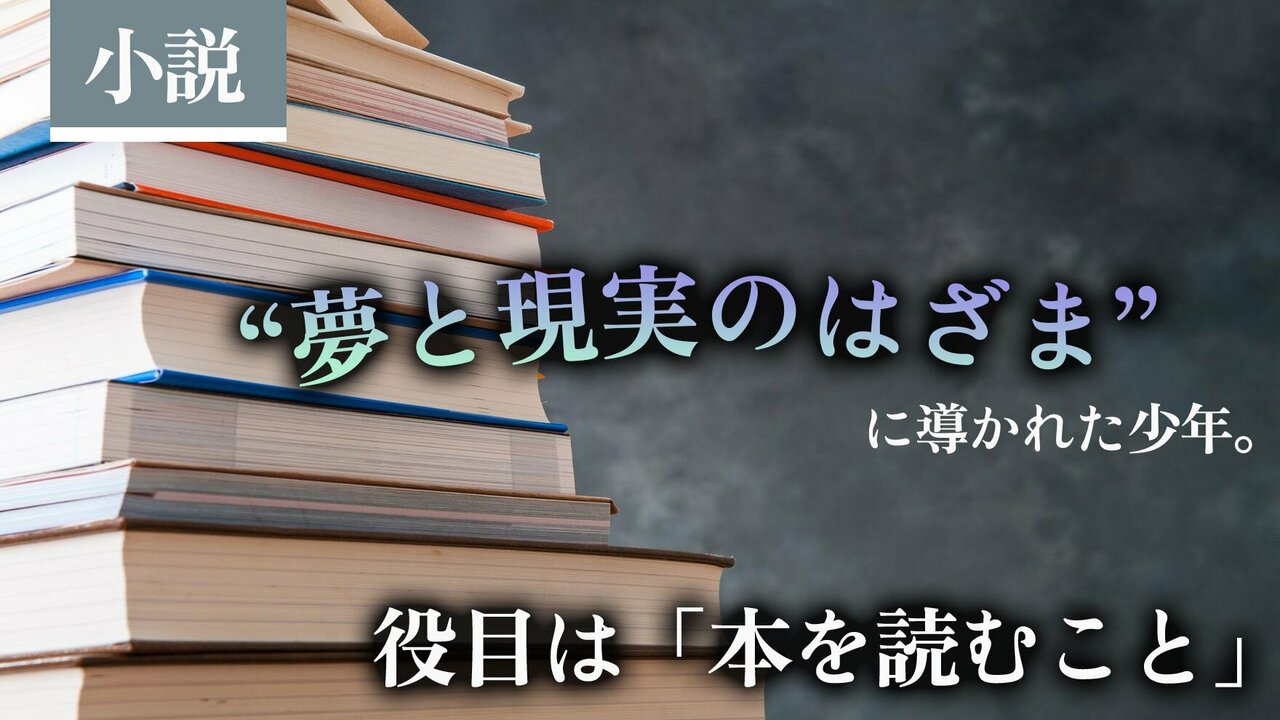僕は、先ほど読みかけていた本の続きを読み始めた。物語に出てくる彼女が最初に描いたのは、とある湖のほとりだった。彼女が描き切るまでの葛藤がよく伝わってくるのか、映像のように脳内で彼女が動く。彼女の声までもが、脳内で再生される。優しい声だ。
そんなふうに読書にのめり込んでいる時だった。突然扉が開いて、人が入って来た。気にしなくて良いと言われていたが、チラリと視線だけを向けた。おじいさんだった。彼は、パズルを眺めていた。容姿は、小さなサンタクロースと木こりを足して二で割ったといった感じだ。彼が、ロジャーという人物だろうか?
彼は、中央のジグソーパズルに近づいた。ガラスの蓋を開け、服の内ポケットらしきところから杖を取り出した。そして、杖を振りながら何やら呟く。すると、ジグソーパズルがぱぁっと光り輝き、宙に浮いた。そして、一度バラバラになったかと思うと、光がすうっと消えると共に、またゆっくりと元の位置に戻っていった。
今目の前で起きた光景に、本を読む手を止めて見入ってしまった。しかし、彼は僕が見えているのかいないのか、こちらを見ることもなく出て行った。彼は一体何者なのか?
今何をしたのか?
頭が混乱していた。
「今のは一体……」
慌ててジグソーパズルを覗き込みに行く。明るい太陽があったはずのジグソーパズルには、満月の浮かんだ星空が広がっていた。
しかし、よく見るとやはり一部ピースが欠けている。
──ここは、その日飾られた“空”というものによって決まる
──エドワードの言葉を思い出し、慌てて外に出る。明るかったはずの空には、満月とぽつぽつと浮かんだ星空が、ジグソーパズルと同じように広がっていた。
見渡していると、やはりところどころピースの形に真っ黒な部分があった。
「これが、“空”……」
僕は、目の前の現実に呆然としながら、空を見上げていた。