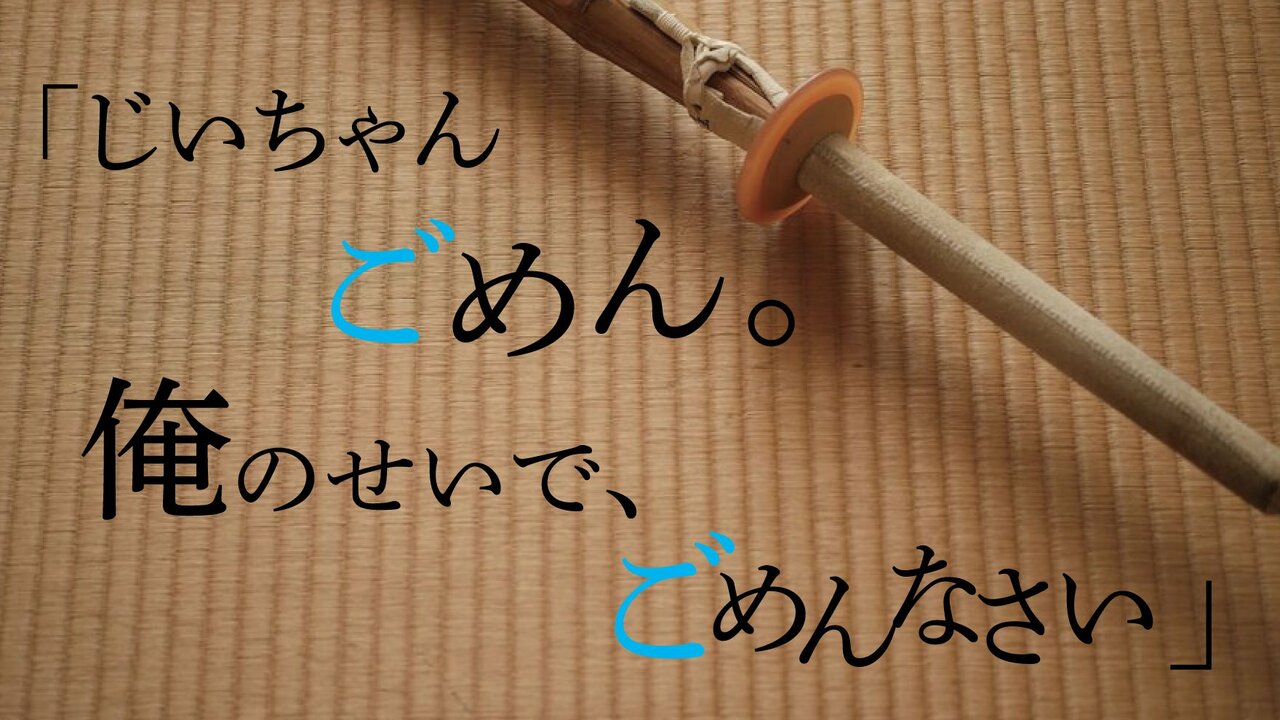「うわあああっ」
成木を滅多打ちにしてしまったらしい。最後は足をかけて転がし、倒れたところをさらに打ち続けてしまったそうだ。
らしい、そうだ、というのは憶えていないからだ。慌てて止めに入った小曽木さんを振り払い、左片手突きで突き倒したところで我に返った。背中を流れる汗が冷たくなっていた。
「虎次郎」
父の声に心臓が跳ね上がり、そろそろと振り返ったところに本家本元、鬼の左片手突きが炸裂した。吹っ飛ばされた先の壁で後頭部と背中を強打して目の前が暗くなり、気がついたときは自分の部屋で寝かされていた。
次の日の夕食後、緊急家族会議が開かれた。
「脇腹のアザはどうした。よもや机の角にぶつけたなどと、たわけた嘘はつくまいな」
父の威厳のある低い声が強い圧力となって胸を押してくる。
剣道形で吐いたときに連れて行かれた灰倉駅の近くにある大きな病院で脇腹のアザを見られてしまった。そのときは机の角にぶつけたと、とっさに嘘をついた。しかし、トレーシングペーパーより薄っぺらい嘘で父を欺けるはずもなく、もはやこれまでと観念してすべて白状した。
「そんな、だからあんなことに。早くお医者さんに診てもらわなきゃ」
「どうしてすぐに言わなかったの」
母は慌てふためき、祖母は詰問調で責め立てる。
どうしてすぐに言わなかったかだって。言える訳ないじゃないか、こんなこと。過剰防衛で警察沙汰にでもなれば、家族や道場、学校に迷惑をかけてしまう。高校入学だって取り消されるかもしれない。それより何より、父さんが怖かったんだ。
「明日、病院に行く。いいな」
反論の余地は微塵もなく、再び連れて行かれた病院でPTSDと診断された。
「先生と話があるから、お前たちは外で待っていなさい」
診察室から追い出された母と俺は心療内科の待合室で無聊を託っていた。
「長いわね。ちょっと様子を見てくるね」
母が診察室に入るのを見届けて自販機コーナーに向かった。無糖の缶コーヒーで胸中の苦みをごまかそうとしたが上手く行かなかった。