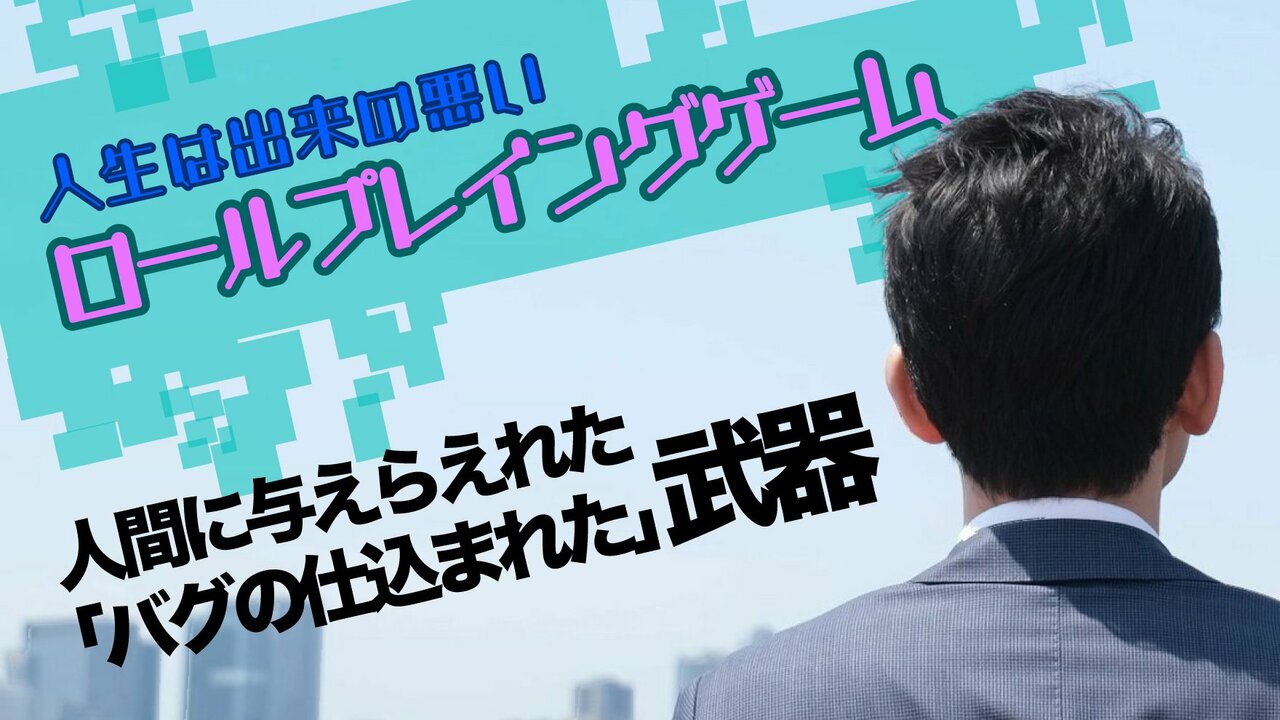タバコがなくなったことに気が付き、僕の不毛な思考実験は途切れた。足元には十本あまりの吸い殻が転がっている。僕は空っぽになった煙草の箱を握り潰してポケットに突っ込んだ。
ニコチンと抽象思考ですっかり現実味を失った意識を埋めるように、理沙のイメージが立ち現れる。そうだ、理沙だ。僕には理沙がいる。このどこまでも無意味で干からびた世界で、僕が唯一求める具体的な他者。それが理沙だ。分からず屋だらけの世界の中で、彼女だけが僕の思想を理解してくれる。僕の言葉に耳を傾け、受け入れ、優しく微笑んでくれる。
このどん詰まりの思想の出口を求めて、僕は彼女に語り掛ける。彼女は何も答えない。けれど、僕が語るとき、彼女の曇り無い大きな瞳はその輝きを増す。そして、静かに顔を寄せ、僕に接吻を与える。その温かな唇は百万言の賛辞にも勝る完璧な同意の証だ。
唇を重ねたまま、僕はそっと体重を乗せて理沙をベッドに横たえる。簡単に折れてしまいそうなか細い腕。小さく柔らかい胸の膨らみ。そして絡みつく両足。彼女の全身が有り余る僕を受け入れる時、僕は言葉から解き放たれる。
彼女を抱いている時だけ、僕はあらゆる夾雑物を排して、世界と直につながることができる。僕は、僕の外に世界が本当に存在することを心の底から感得する。彼女は僕を世界に繋ぎ止める、か細いへその緒のような紐帯だ。
全てが静止したような夜の静寂。六畳一間のパイプベッドには、一糸纏わぬ二人の男女だけが横たわっている。理沙の静かな寝息を聞きながら、僕は思う。この小さな部屋だけが現実の全てだ。今この瞬間、僕は自由だ。この一瞬の価値は永遠に等しい。しかし、この瞬間は音もなく消え去り次々と過去となってゆく。この瞬間を凍結する術を、僕は知らない。
時間が自由を突き崩す。束の間の充足が蜃気楼のように消え去り、捉えようのない不安が、再び僕の心を満たし始める。理沙はいずれこの世界から消え去る。僕もまた消える。全ては過ぎ去り、消え去り、無へ帰る。真正な思いも、完全な瞬間も、何もかも初めから存在しなかったかのように消滅する。
僕たちがこの地上に生きたことも、出会ったことも、抱き合ったことも、宇宙的視点から見れば微小なエネルギーの一瞬の揺らぎでしかない。僕たちはどうしようもなくちっぽけで、全ては忘却の海に沈んでゆく。このあまりにも残酷で無関心な世界を相手に、僕は一体どうすればいい?