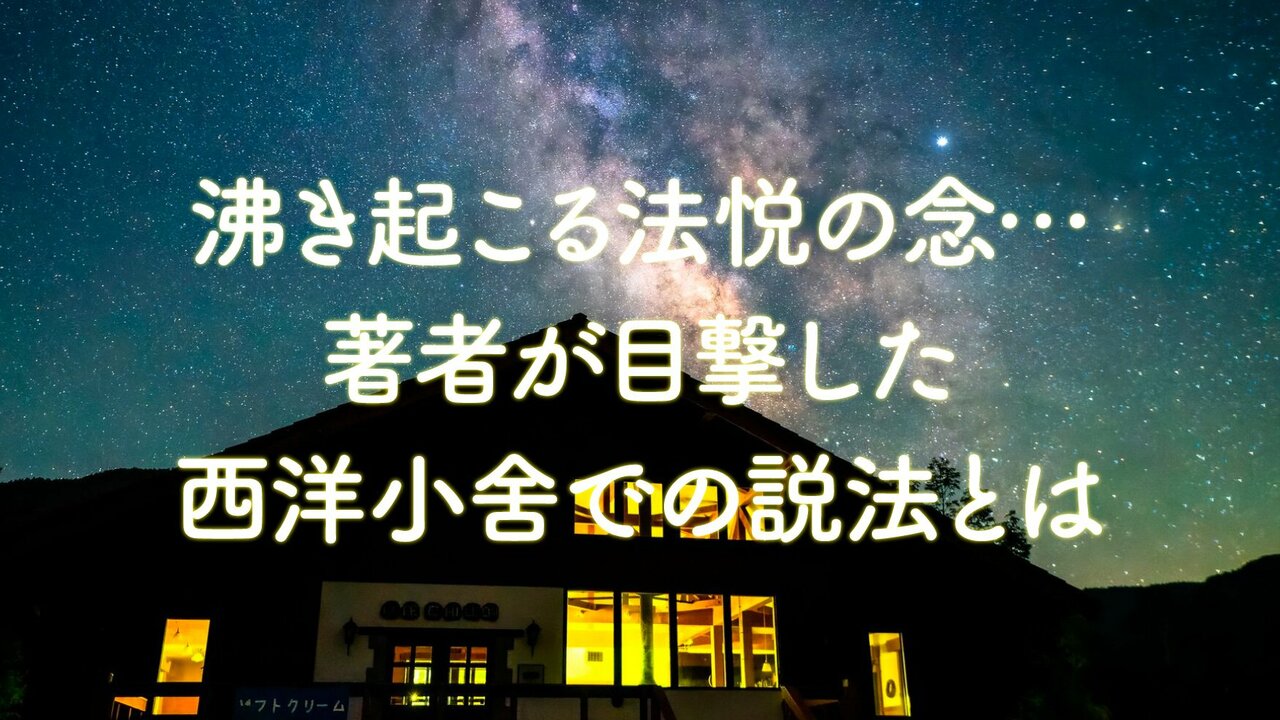【前回の記事を読む】「まるで別世界に放り出されたよう」西洋を旅した当時の日本人
西洋小舍の佛壇
本文
吾々二人の間斷のない語草を、この美しく行列したような幾萬株の葡萄の古樹が恰も凡べての心の底からの聽手者の如く、ひつそり靜かに聽いてゐる、そして久しく二人とも、霧雨降る欝陶しい而も大きい髙い建築の爲めに太陽を知らず全く、朝夕の氣分を忘却してゐた吾々は、漸く甦つたような氣分で、違く夕色を帯びた山脈のうねりや、夕やけのふわふわした雲を眺めるにしても、近くの小川が滾々と水泡をのこして流るゝのを見ても、何んとも云へぬ懷鄕の念が知らず知らずにセンチメンタリズムを呼び起す、そして黄昏るゝ夕色の空氣のさはやかな感觸のすべてが何とも云へぬ尊い心で莊重な讃美を繰り返した。
やがて、纏つた村の少ない、あちらこちらの地平線上に散ばつたペンキ塗の小さい三角棟が見えた、天を摩するが如き楡の古木が宙天に伸びて、靜謐な自然の內に微かに息を呼ふてゐる、近くの水昇器が風もないのにごとんごとんと音をたてゝ、自然の波動をあらはに破つてゐる、而して日の暮るゝ頃に漸くとある一つの三角棟の西洋小舍に導かれた。
薄暗の中で數頭の黑い豚に殘飯を食はせてゐた忙しそうな西洋頭巾を冠つて黑いスカートを着けた肥つた主婦さんに、『今晩』と氏が云つたので、それまで何も知らなかつた彼女は、始めて氏の訪れを知つて狼狽えたように急いで慇懃に御禮を述べた。
この二棟の西洋小舍は、日本移民の最初に來た老夫婦と二人の息子と、他の一棟は同じく邦人の勞働者の十二三人の傭人の住む小舍である、吾々二人が老夫婦の暖い饗應で質素簡易な夕餐を大變うまく頂いた、食後早速開敎師は穢苦しい小舍の一隅に正座した、
そして小さい佛壇が安置されてある事を始めて知つた時、何んとも云ひぬ感銘を興へられた、軈て氏は徐ろに佛壇の戶扉を開いて其の內から御敎の本を取り出して、悠々朗々と廿分餘も佛書を誦した、氏の後方には老夫婦を始め十幾人の傭人迄ずらりと正座して南無阿彌陀佛を繰﨤してゐる、御經が終つた後一同を土間の汚ない食堂に集めて説敎が始まつた、
其の話題は『現實の地獄と未知の地獄』と云ふ通俗的題目であるが、其の説敎の折々に、夫等の老夫婦を始め十三人の傭人の中には、如何に感じたものか叫ぶが如く南無阿彌陀佛を繰﨤す人もあつた。