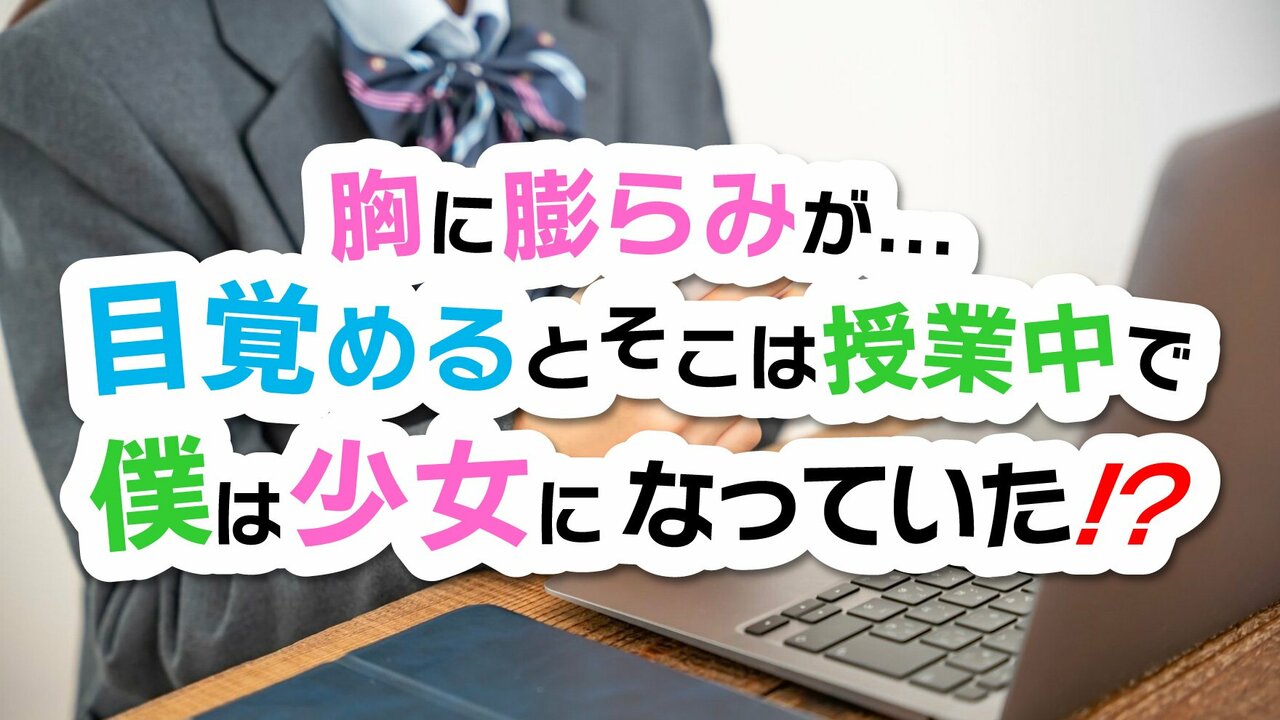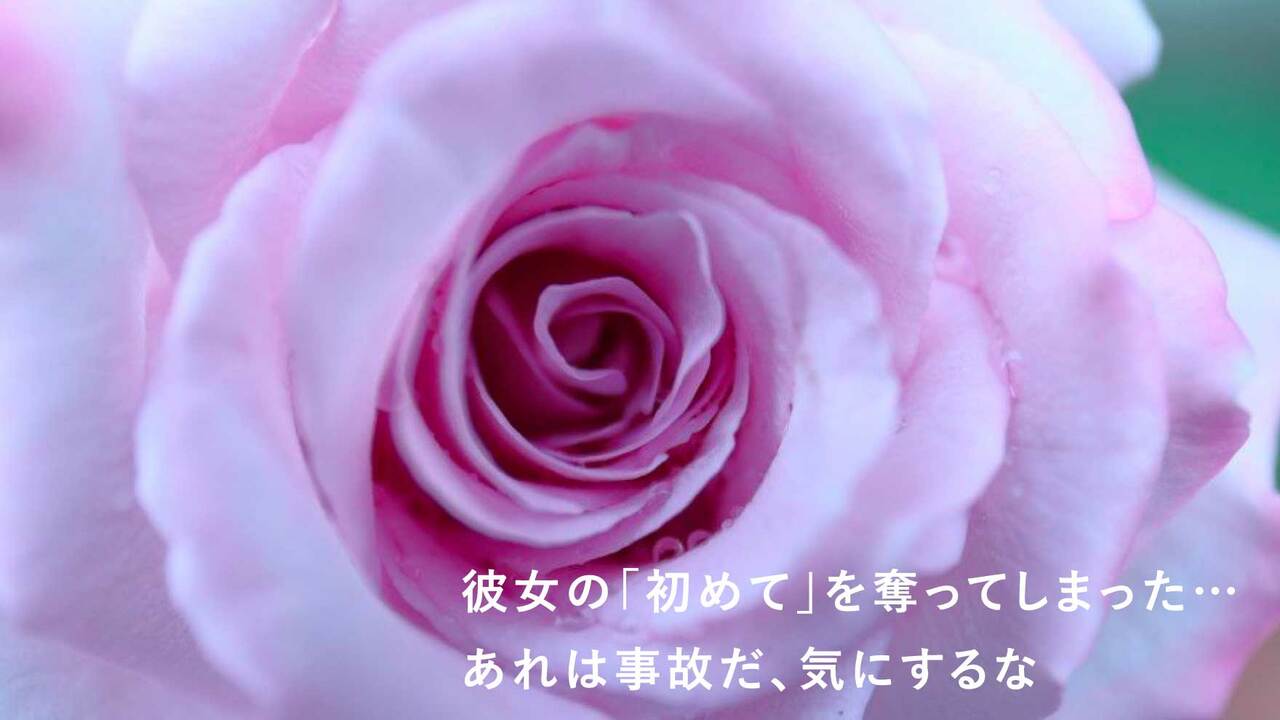1章 まやかしの織姫と彦星
「んん……、ん」
まどろみの中の暗闇に一点の光が差し込み、あやふやな意識が呼び起こされ、目が覚める。おかしい、寝てから時間は経っていないのに。時計は見ずとも直感的にわかる。とはいえ現時刻を一応はチェックしようと、玲人は枕元にあるスマートフォンに手を伸ばそうとした。だがここで、自身の取る体勢の異変に気づく。
「あれ、え?」
うつ伏せの姿勢なのだ。いや、ただのうつ伏せであれば、寝返りを打ったということで話は終わり。しかし腕に覚える感触はベッドの柔らかさからはかけ離れ、まるで机に伏せているときに感じるような硬さだ。
(……まるで?)
玲人はやおら顔を上げ、目を擦ってから視線を下げる。
─学習机だ。ぼやける視界を瞬きでクリアにして、なんとなしに目の向きを横に移してみる。ノートにペンを走らせる着座した制服姿の男女が、揃って前方を向いていた。味気ないチョークの音が鳴るこの光景は、紛れもない授業中の教室の風景そのもの。
(しまった、授業中だった!?)
授業中の居眠りなど、いったいいつ以来か。それを防ぐために日々の睡眠時間を確保しているというのに。
(あれ、たしかにベッドに転がったと思ったんだけど。夢か現実か、区別がついてないのか?)
奏空と顔を合わせ、上野先生に新聞記事の執筆を依頼され、帰宅してからベッドに入った一連の流れはすべて夢だった、ということか。気を引き締めねばと玲人は反省しつつも、やっぱり掴みどころのない違和感が脳裏にへばりつく。
玲人は手元のシャープペンシルを握り、別の手で頭を抱える。しかし髪の質が常々と違うことに気づいたのは、髪に触れる機会が何かと多いからであろう。
(毛先が少ない?それに……柔らかい?)
親指と人差し指で髪をより合わせる。反発が少ない。背中に沿って掌を下ろしてみても、艶やかな髪の感触が掌に残る。もしや手肌に異常が?それを懸念した玲人は目の前で手を広げた。細い五本指がしなやかに伸びる。綺麗な肌だ。言ってしまえば、見慣れた自分の手ではない。
(……)
両手で顔を包む。肌の滑りがよく、顔の骨格も自らとは別。そもそも男のそれではない。
(もしかして……)
玲人は斜めに落としていた視線を、いっそう下げてみた。膨らみがある─胸元に。目をごしごし擦ってもやはり膨らみはそこにあって、だから持ち上げるようにそれを掌で包んでみる。制服や下着でごわごわしているが、確かな肉の柔らかさが手の中にあった。冷たい汗が全身から滲み出る。
(か、顔が見たい。僕の顔は……どうなって……ッ)
窓はここから遠く、何か顔を確認できるものは……と机の中を探ってみたら、都合よくコンパクトミラーを引っ張り出せた。これで顔を見ろって? 開いた鏡を恐る恐る覗いた玲人。
「……」