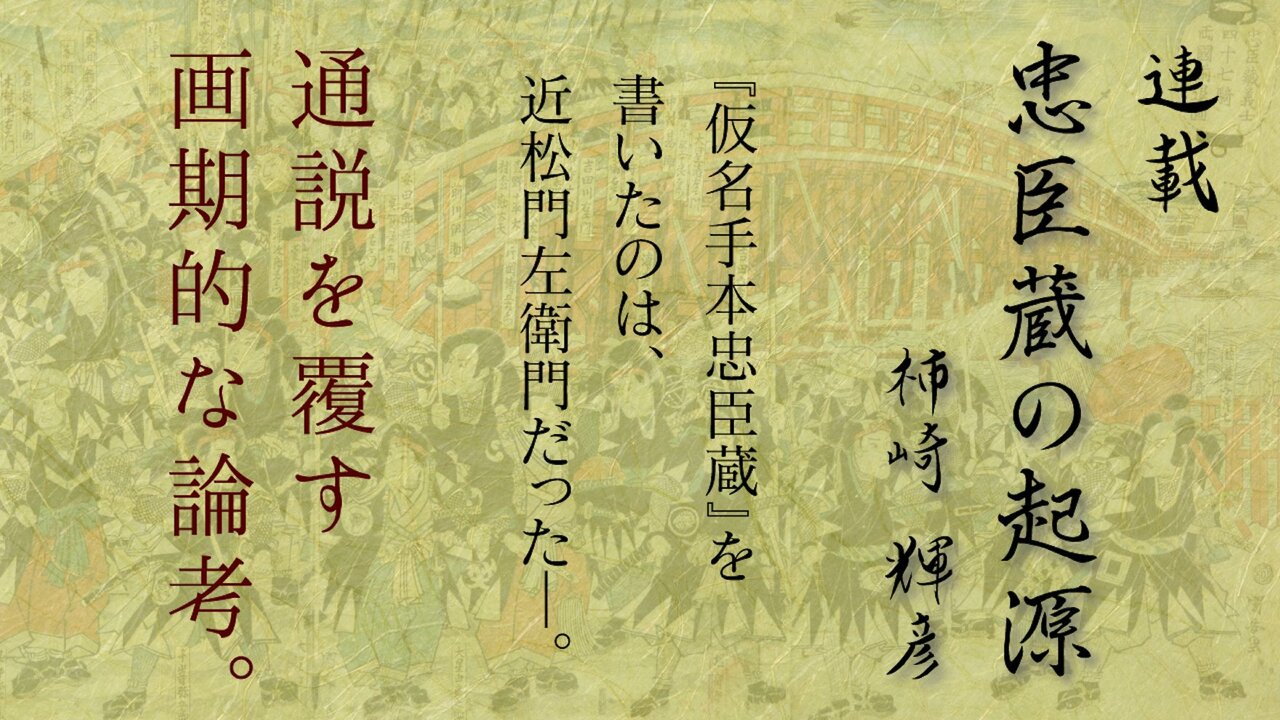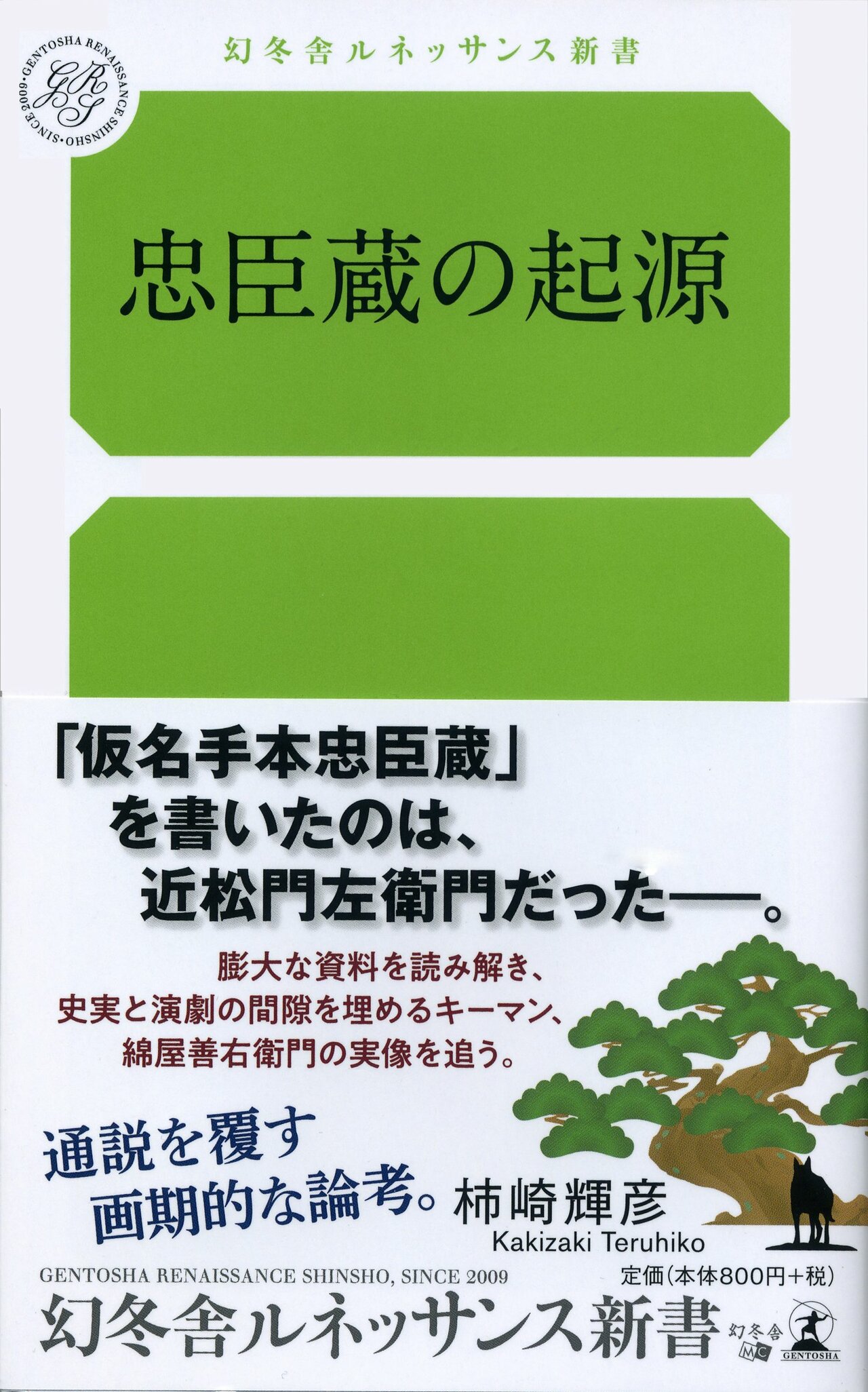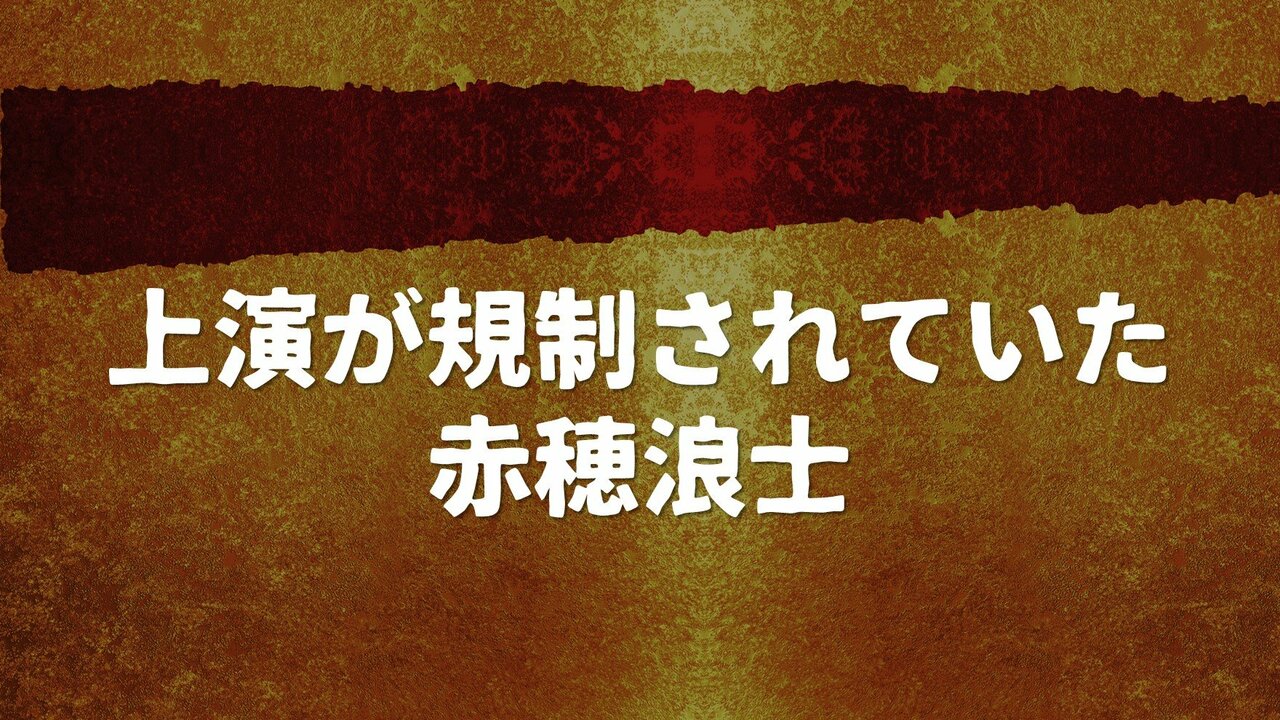第三章 芝居に潜む謎
題名の変更と内容のすり替えの謎
上演時期については現在次のようなことが有力である。宝永六年(一七〇九)一月の五代将軍徳川綱吉崩御並びに徳川家宣六代将軍就任にともなう将軍恩赦により、同年二月三十日に吉良邸討入りに連座した赤穂浪士らの遺児に対する刑が御赦免となり、八月二十日には浅野内匠頭の刃傷事件に連座した実弟で養嗣子の浅野大学長広も御赦免となっている。
翌宝永七年(一七一〇)九月十六日、浅野大学は将軍家宣に拝謁し安房(千葉県)朝夷郡と平郡に新知五百石を拝領し旗本寄合に列せられている。このことにより元禄赤穂事件関係者への連座はすべて解かれ関係者全員が無罪放免となっている。ここに、大石の念願でもあった旧赤穂浅野家の再興が叶っている。
これら一連の背景が、『碁盤太平記』を上演する動機の一つであったとするのが演劇界における見解である。ところが、当時は今日のように新聞やニュースが存在していたわけでもなく、旧赤穂浅野家再興に関する情報が、いったいどのような経緯を辿り、いつ頃近松やその他の芝居小屋にまで届いていたかについては不明だが、このタイミングを待ちかねていたように宝永七年(一七一〇)には歌舞伎と浄瑠璃双方において赤穂浪士が組み込まれた芝居が相次いで上演されている。
宝永七年六月に大阪篠塚庄松座で吾妻三八作の歌舞伎『鬼鹿毛武蔵鐙』が、翌七月には京都夷屋松太夫座で『太平記さざれ石』が上演されている。とくに『鬼鹿毛武蔵鐙』は、篠塚次郎左衛門が演じた大石内蔵助役の大石宮内が評判となり、六月十日から九月十一日まで百二十日間に渡り大当たりしたとの記録が残されていることから、浅野大学が御赦免になった宝永六年八月を解禁とした場合、上演までに十分時間的余裕はあるが、浅野大学が旗本に列した翌宝永七年九月を解禁の根拠とした場合には歌舞伎の『鬼鹿毛武蔵鐙』や『太平記さざれ石』は勇み足となる。
『碁盤太平記』と『鬼鹿毛無佐志鐙』は、宝永七年の何月に上演されたのかが正確には解明されておらず、上演順序の後先が判定できないものの、少なくとも『鬼鹿毛武蔵鐙』の上演を待ってから作品の制作に取りかかったのでは実際の上演には間に合わない。近松は以前に『曽根崎心中』を事件から一ヶ月程で書き上げたとの実績はあるものの、元禄赤穂事件と曽根崎の心中事件とではスケールが違い過ぎる。
そこで近松らは、恩赦などによって急遽赤穂浪士を取り上げた芝居が解禁されるであろうことを見越して、予め『碁盤太平記』の作品化を粛々と進めていたと考えられる。また、紀海音作『鬼鹿毛無佐志鐙』の台本は残っているものの、歌舞伎の『鬼鹿毛武蔵鐙』については台本が残されていないことから、演劇界の見解としては、歌舞伎の方が先行作品であり、それを紀海音が浄瑠璃作品として引き継いだものとしている。
また、宝永七年秋に京都夷屋松太夫座で上演されたとする『太平記さざれ石』では大石内蔵助役が大石宮内で、しかも題名に太平記と冠され、『碁盤太平記』と同じ塩冶判官と高師直が浅野内匠頭と吉良上野介に仮託して登場している。この演出については、京都夷屋松太夫座と近松のどちらの発想が先であったかについては特定することができていないものの、近松は『碁盤太平記』以前に太平記を舞台とした『兼好法師物見車』をすでに上演しており考慮の余地が残る。
急遽上演することになった『碁盤太平記』ではあったが、期待したほど話題にはならず、作品の出来映えとしても特筆するほどではなかった。それでは、『碁盤太平記』の上演には、いったいどのような意義があったのかについて迫ってみたい。
『碁盤太平記』の上演時期については、演劇関係によると浅野家の再興が叶ったことで、元禄赤穂事件に対する規制緩和を先読みした興行側によって俄に演じられたものとしており、この状況をひとつのブームとしているが、この時期においては、興行側も依然取り扱いには慎重であったはずである。その証拠に、この時期の仇討ち劇は一過性のものであり、その後ブームが勢いを増したとする記録はない。
実際に『碁盤太平記』はじめ初期の頃は全ての作品に仇討ち劇としての遠慮があり、討入りの場面を組み入れてはいるものの、赤穂浪士による吉良邸討入りが世間に衝撃を与えた時ほどのインパクトは感じられない。要するに芝居が実際の事件を超えていない。
言い換えれば、この時期の元禄赤穂事件を取り入れた作品は、題材は一級であったが作品としての完成度はそれほどではなかったことから、この時のブームは、作り手によるものであったと言える。その後『忠臣金短冊』や『大矢数四十七本』などの同類の作品が上演されるが、赤穂浪士による仇討ち劇に火をつけたのは寛延元年(一七四八)に登場する『仮名手本忠臣蔵』ということになる。
登場人物の謎
『碁盤太平記』の中に気になる人物が登場している。岡平こと寺岡平右衛門で準主役級として抜擢され、芝居のなかでは旧塩冶家足軽寺岡平蔵の倅に設定されている。名前の文字面や役柄の階級からして赤穂浪士の一人寺坂吉右衛門をヒントにしていることは疑う余地が無い。しかも、のちの大作『仮名手本忠臣蔵』にも同名の寺岡平右衛門として登場する。
この寺坂吉右衛門とは、吉良邸討入りに参加したのち切腹の刑を免れ、そのまま生き延びたことから四十七人目の赤穂浪士とされ、同志の中では最も階級の低い足軽であった。この寺坂については、特別な功名功績があったわけではなく、浅野家改易後も常に元主人吉田忠左衛門の側に仕え、これといった活躍もなく目立った存在ではなかった。言わば元禄赤穂事件においては陰の存在であった人物であったにも関わらず、唯一生き延びた四十七士の一人としてからか芝居のなかでは伜が主役級の扱いで登場している。
この奇妙ともいえる歴史上の不一致については、今まで演芸評論家などからは問題視されることなく見過ごされてきた。一方の史実派としては芝居のなかでのことでもあり、最早範疇外のこととして取り立てて指摘することはなく、著者自身も、この件については以前から承知はしていたものの、長い間腑に落ちず違和感だけを抱いていた。
フィクションである忠臣蔵はあくまでも娯楽であり、明らかな嘘偽りがない限り、多少の脚色については許容しながら受け入れられてきた。史実派も芝居のなかでの出来事ともなると、たとえそこに事実との齟齬があったとしてもそれほど目くじらを立てることはしない。それこそが長い年月をかけて史実と文芸の双方に依存しながら発展してきた忠臣蔵文化の独特の感覚でもあるのだが、逆に寺岡平右衛門の存在こそが史実とフィクションが融合しない不連続の象徴とも言える。