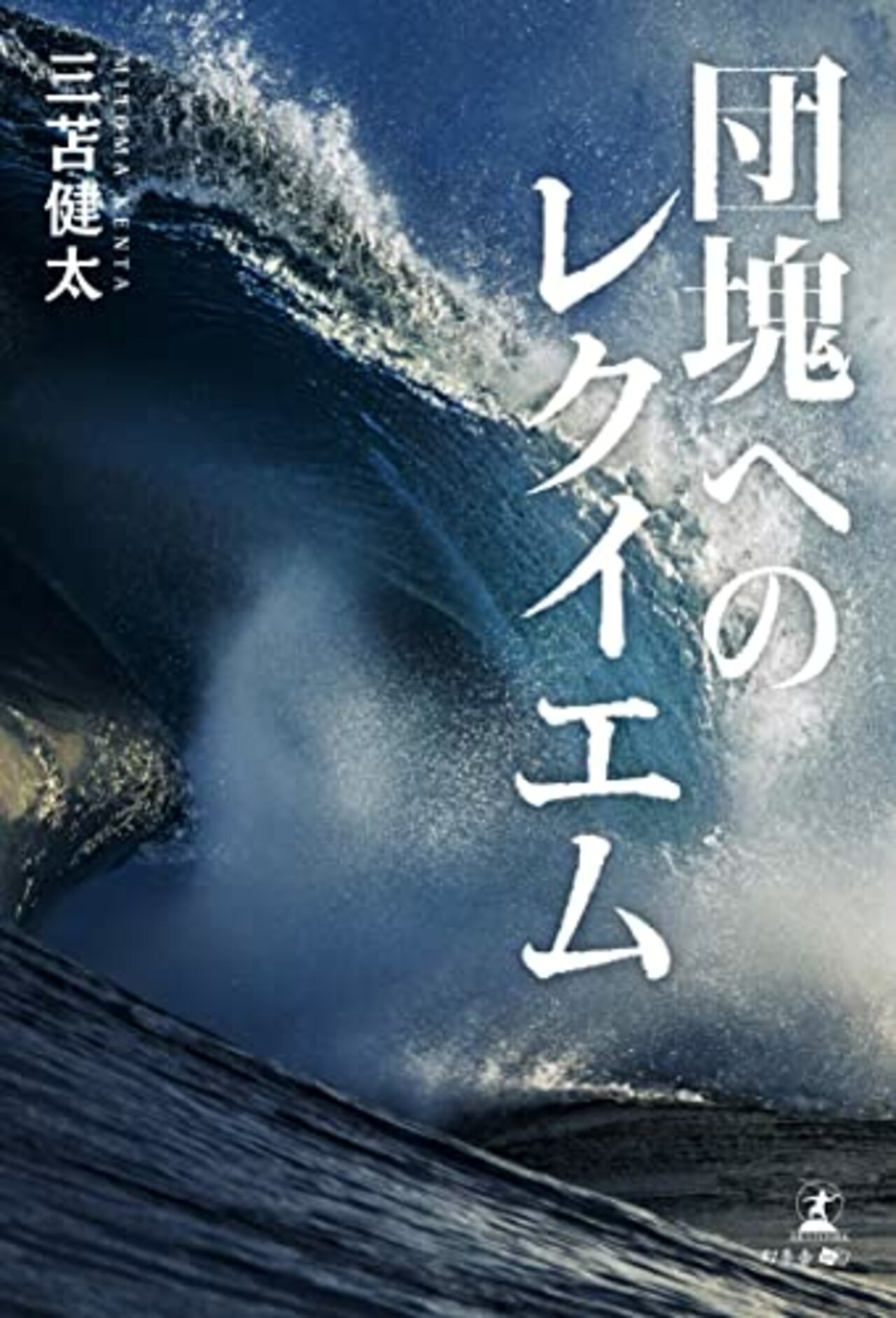講習期間中のある土曜の夕方だった。偶然、新橋駅前の広場で周平を見つけ、行きつけの居酒屋に誘った。周平は、左沢の誘いに二つ返事で同意したから、てっきり酒は飲めるものと思ったが、まったくの下戸だった。飯が食いたいというから海鮮丼を注文し、ひとりが丼にかぶりつき、ひとりがチーズを肴にビールをあおる珍妙な構図になった。
周平は、一杯目をぺろりと平らげ、おかわりはどうだと水を向けるとうれしそうにうなずいた。左沢は、この男をなんとか一人前のプログラマーに育てようと、二杯目を大事そうに食べる横顔を見ながら思ったものだった。
「で、左沢さんのビジネスパートナーさなったわけですね。すかす、講習さ受けただけで、すぐ仕事さできるようになるものですか」
「もちろん、最初のうちはプログラマーだけではやっていけません。彼もしばらくは週の半分ぐらいはコンビニで働いていました」
「左沢さんちのマンションのコンビニですね」
「そうです。でも周平は一年ぐらいで一人前のプログラマーに育ちました。最近では、スマホのプログラムの技術もマスターして仕事がかなり増えていました。当然、収入も段違いに増えていたはずです」
「それで心中か、やっぱ納得できねぇですな」
多門は小さくハンドルをたたき、ひとりごちた。
マークXは山あいを抜けて丘陵地に出た。太陽の光が強くなったような気がした。左右に収穫を待つ蕎麦やジャガイモの畑が続いている。前方のうろこ雲の下は太平洋のはずだ。車は、小さな町をふたつ通りぬけ、ガソリンスタンドの手前を右に曲がって間道に入り、二百メートルほど走って停車した。
「あれが周平さんの生家です」
多門が指差す先に青瓦の平屋が見えた。それは、左沢たちが立つ県道から十メートルほど奥まったところ、県道より三メートルほど高いところに建っていた。しかし、雨戸は締め切ったままで、その雨戸も色褪せて、ところどころ合板部分が剥離し捲れあがっている。コブシやヤツデなどの庭木も、飛び枝がピンピンと立って、無様な樹形になっている。
「人さ住まねば、こげださなるもんだ」
突然、しわ枯れた声がした。声のほうを振り向くと杖代わりの手押し車にすがるようにしてこちらにやって来る老婆が見えた。隣には、制服の巡査が原付バイクを手押ししながら付き添っている。巡査はさきほど通った町の駐在らしかった。
「栗原家はもともと富岡の出ですから近くに親類はいません。すかす、この婆さま、栗原さんちと親しくしていたようです。栗原周平さんのこともうんと知っています。遠くの親戚より近くの他人ってやつです」、と巡査は言い、ヘルメットを脱いで額の汗を拭った。