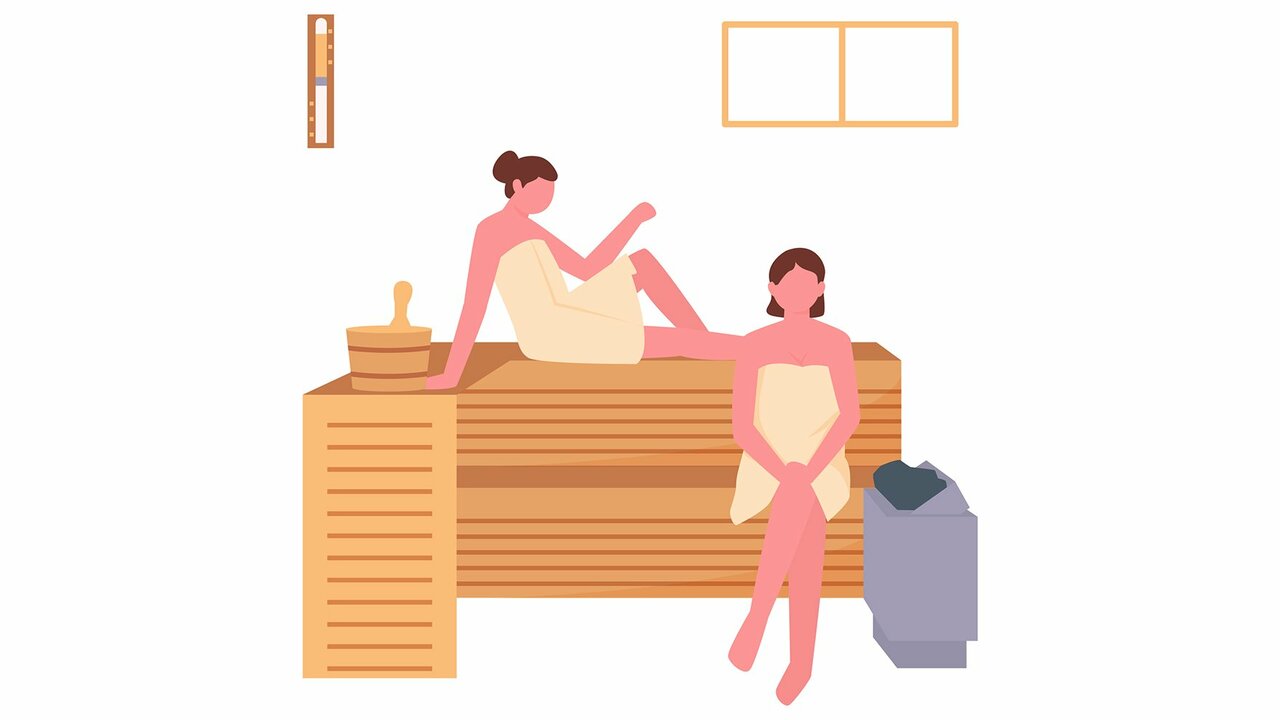「ああ、でも若い研究員がよくやってくれるけん、俺が少々留守にしても支障はないんや。ま、そうそう都合のいいデータが簡単に揃うわけやないけん、急には何も動かんけど」
「そうか。今はどげな研究をしよるんか」
「大きなテーマをやりよるで。嵯峨野医大の山村先生がノーベル賞取った再生細胞、名前くらいは知っちょるやろ。成熟細胞の初期化、いうやつや。あれを使った内臓疾患の治療可能性を研究しよる」
「成熟細胞の初期化てか。戦後すぐの教育受けただけの高校生物教師上がりの爺さんには、ちいと難しいごたるな。健太は医療器械の会社に入ったんやろが。お前の影響かのう?」
「さあな、あんまり関係ねえと思うけどな。あいつは経済学部やけん、医療がビジネスとして伸びる分野やとは思うたんやろうけど。家を出て一人暮らししよるけん、詳しいことは俺も知らん。まあ元気にはしちょるよ。美咲もな」
「内臓疾患の治療か…あと何年かしたら、母さんのような病気も、それで治せるようになるんかも知れんのう……」
修治の言葉を借りるまでもなく、再生細胞によって母親の内臓を健康にすることができるのではないかというのは、この研究に関わることになって以来、純平自身が期待してきたことである。だがその母親が臨終を迎えようかという状況に至りながら、未だに効果的な方法論を掴めていないことが歯がゆく、悔しく、情けなく思えてしまう。
もちろんそんな画期的な医療方法が簡単に確立されるはずもなく、また自分を過大評価しているつもりもないのだが、目を閉じたままの淑子の顔を見ていると、「母さん、すまない」という思いが湧いてくるのはどうしようもない。
ふと修治に視線を転じると、純平は修治の眉毛がすっかり白くなっていることに今さらながら気がついた。元々修治は白髪になるのが早かったが、そうか、眉毛もか。
――仕方がないな、トシを取ることだけは防げない。孫が二人とも社会人になってるんだ。父さんがすっかり老け込み、体の弱かった母さんが死んでしまうかも知れないというのも、今の医療技術では避けようのないことなんだ。