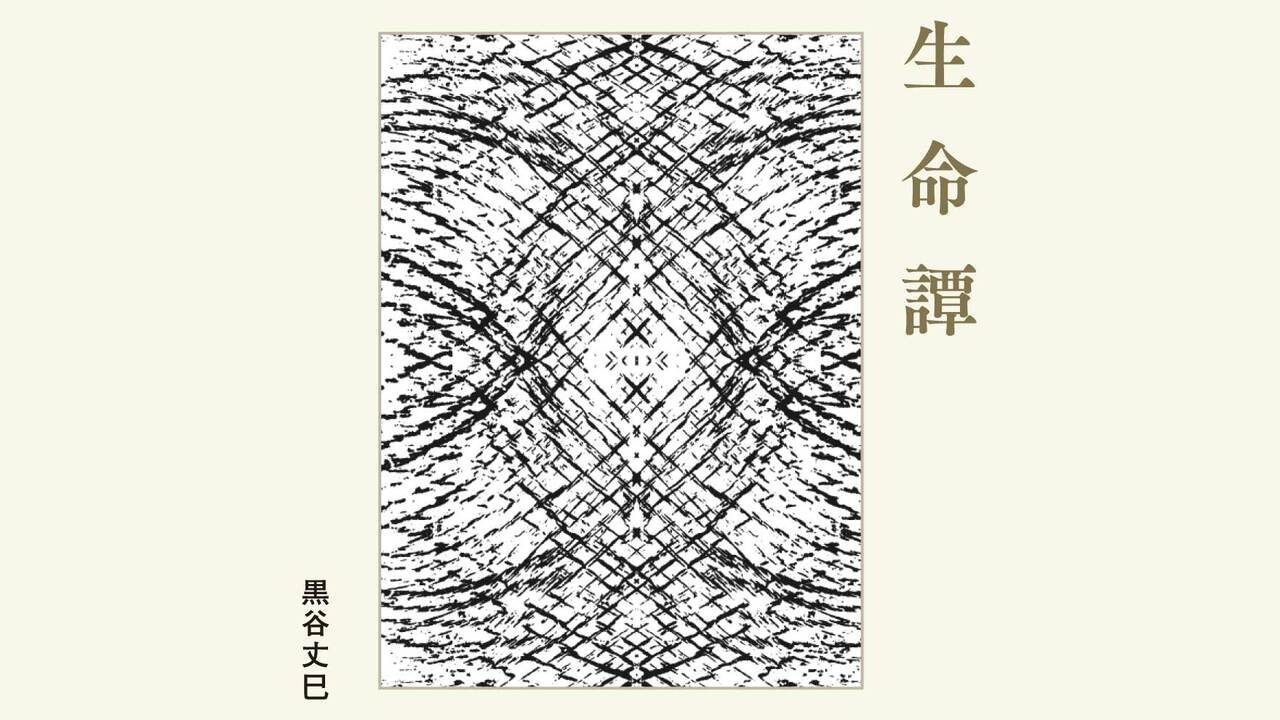二〇一六年 秋 ─大分─
淑子の状態には特に変わりがないまま、その日の夕方、香織叔母はいったん帰宅することになった。
叔父の昇一は、今では珍しい部類であろうが、自分からは一切家事に手を出さない。先祖は豊後臼杵藩の国家老だったそうで、子供の頃から「男子厨房に入らず」を厳しく言われ続けて育ったと言っているが、体のいい言い訳かも知れない。とにかく香織としては、実の姉の容態は心配だが、亭主の晩飯の支度も気になるということなのだろう。
「ほんならうちはいっぺん帰るけど、姉さんの様子が変わったらすぐ知らせちょくれな。今日は明日の朝ご飯の支度も一緒にしちょくけん。……姉さん、気がついてくれるといいんやけどなあ……」
「大丈夫や、おばちゃん。父さんも俺もおるけん、安心して家のこと済ませてきていいで」
「ごめんなあ、ほしたらな、お義兄さんも純ちゃんも、よろしくお願いします」
修治と純平に頭を下げてドアに向かいかけた香織は、もう一度踵を返し、淑子の傍に寄ると話し掛けた。
「姉さん、しゃんとせなで。純ちゃんも帰ってきてくれちょる。ちゃんと目を覚まして、声掛けてあげよえ」
後ろ髪を引かれつつ病室を出た香織の軽自動車が病院の玄関を出ていくのを窓から眺めていた修治が、再びベッドの淑子のほうに向き直った。横顔にはさすがに疲れが見える。
「お前も忙しいんやろうが、よう帰っちきちくれたの」
パイプ椅子に腰掛けた修治が、淑子を見つめたまま純平に話し掛ける。敢えて淑子の容態に触れないでいるのは、修治は改めてその話をするのは避けたいからだろうと純平には思えた。