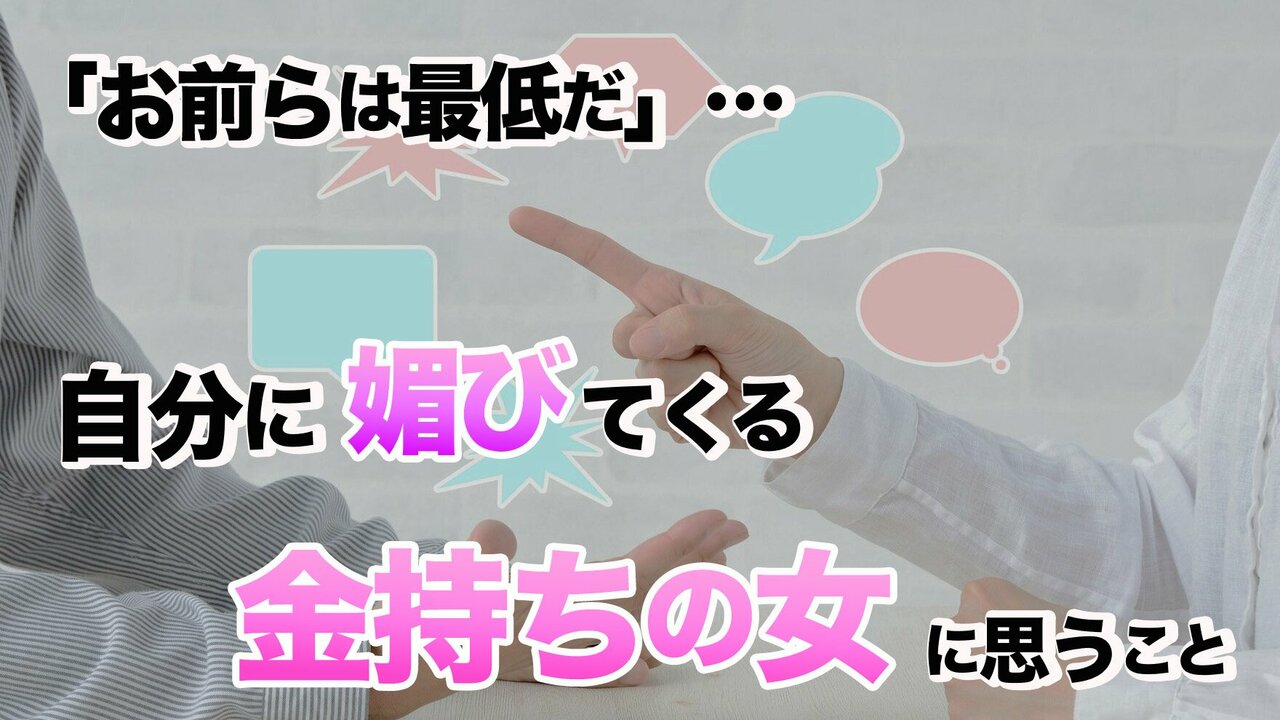1996年 夏の久へ
波が大きくうねって、久の前で崩れた。今日は波に上手く乗れない。進む速度も去年に比べると大分遅くなった気がする。身体はこちらの都合などお構いなしに勝手に壊れる。しなびた皮膚、ゆるんだ筋肉、その下の骨格もすかすかだろう。
午前中仕事。昼飯の後、一時から泳ぎ、三時過ぎからまた机に向かう。判を押したような生活だ。
「機械じゃねえんだぞ、俺たちは」
新村の声が聞こえるようだ。泳ぐのは仕事をスムーズに進めるためで、健康のためでも楽しみのためでもない。なら仕事がそれほど大事かと言われれば、そういう訳でもない。何のために泳ぐのかは何のために生きるのかに繋がって、答えが出ない。水の中に何かある。白いもの。
腸だ! ぬらぬらした白い腸。慌てて思い切り水を掻いて、前に進む。がむしゃらに泳いで振り返ると、松林が緑の線になって見えた。周りには海に仕切られた空が広がっている。この海をずっと水平線を目指して泳ぎ続ければ、ぐるっと回ってまたここ、か。輪廻転生はあるかもしれないと思った。水が変に冷たい。かなり沖まで来たらしい。大きく海水が膨れ、波が光った。気配がある。
「コウか」
死んで五十年以上経つのにコウは今でもそばにいる。戻れと言うように波が動いて身体を持ち上げ、一掻き一掻き、波に押されるようにゆっくり岸へ向かい、重い荷物を引き上げるみたいに自分の身体を海から引き出した。波打ち際で子供たちが水を掛け合って、甲高い笑い声を立てている。ただ水を掛け合うだけであれだけ笑える子供っていうのは、全く生きる天才だ。
天才じゃなかった自分は、ろくに笑った記憶もないし、こんな子供の間でいつも浮いていた。この世に間違って送り込まれた気がして、外も人も怖かった。身体が弱かったせいもあるんだろう。喘息気味で風邪をこじらせては母親を心配させてばかりいた。妹がいたが歳も離れていたし、ひとりっ子のようなものだった。具合の悪い時はよく二階の部屋の窓からぼんやり外を見て過ごした。
あの窓からは大きな柿の木が見えた。秋になるとたくさん実がなった。柿の実は橙色で夕日の色だと母に言われたが、窓から見る夕日は、時々血のように赤かった。あの時見たのは柿の実なのに、柿を見つめる自分の背中を見た気がするのは何故だろう。また甲高い声がして、細い棒みたいな腕を振り回しながら、子供たちが海に飛び込んでいった。贅肉のない彼等の薄い背が、海の中に影になって浮かんでいる。