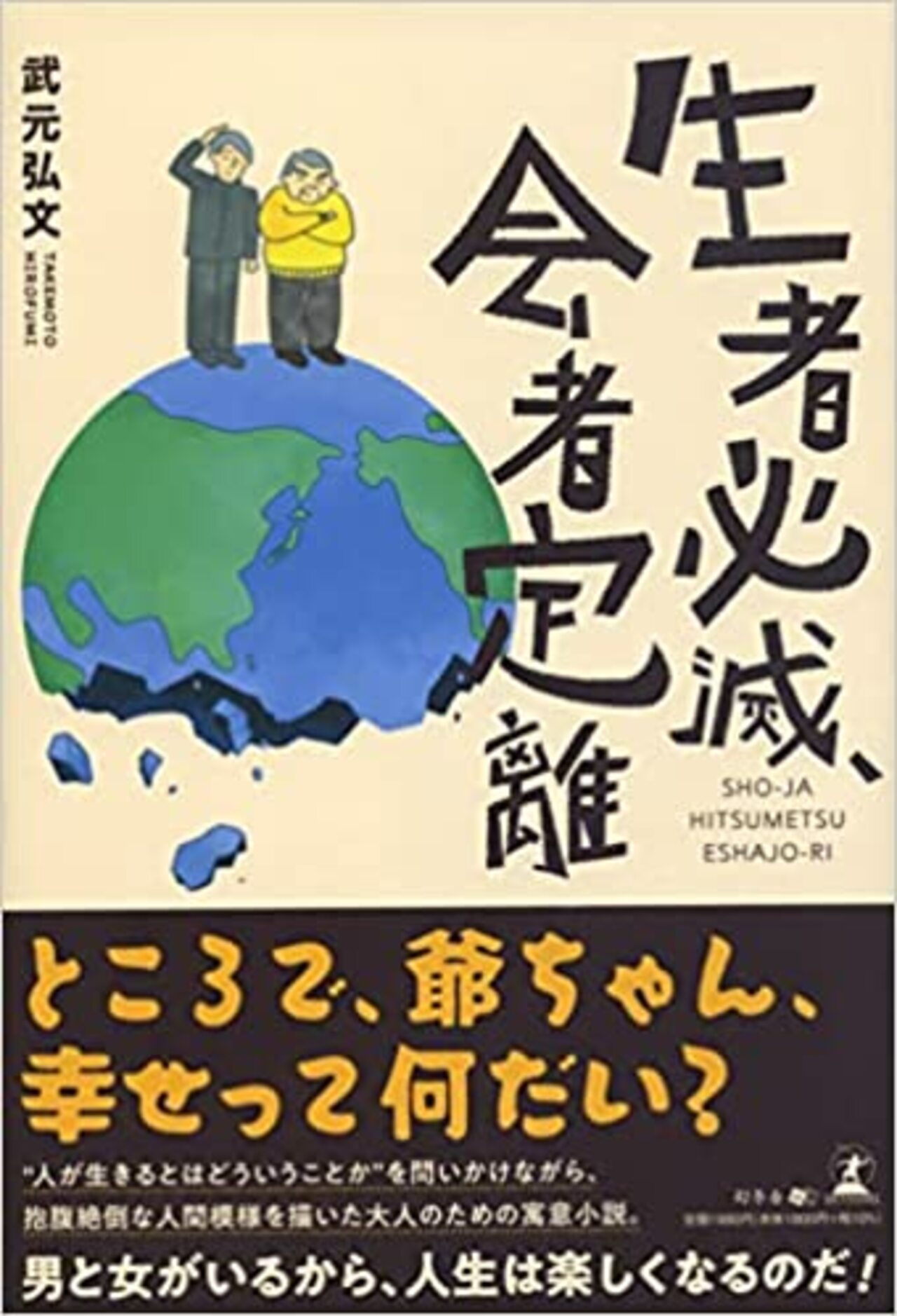壱之夢 ユニークな生い立ち
第2話 果てしなき夢
そんなある日のこと。
「のう、加奈。今、世の中は大きく変わっている。これからはもっと変わっていくだろう。儂は、今すぐにでも東京へ行きたい」
(鹿児島に来るだけでも清水の舞台から飛び降りるような思いでしたのに、東京だなんて、そりゃ、無茶苦茶でござります)と、加奈は胸の内で呟いたが「旦那さまのおいでになるところ、地の果てまでもお供いたします」と、夫唱婦随の加奈。
「それでこそ儂の妻じゃ。また、苦労をかけることになって済まぬが、必ずや、幸せにしてみせるぞ!」と、喜ぶ文左衛門。大正元年、二十五歳になった文左衛門。ついに、大志を胸に東京へ出ることを決心する。
家業を弟の源左衛門にゆだね、薩摩藩校の先輩、伊集院九郎衛門が営んでいる東京は日本橋の兜町にある廻船問屋〈北前屋〉に丁稚として住み込む。加奈も三歳になった長女、茜の手を引き、生まれたばかりの次女、小百合を背中に負ぶい、夫共々住み込み女中として雑用をこなし、家計を助ける。
二人は鹿児島弁丸出しで話をするので、周りの者には何を言っているのか、さっぱりわからない。まずは、言葉で苦労する二人。働き者の加奈は、身を粉にして働いた。女中頭のお熊ばあさんから「若いのに、よう精が出るのう」と、可愛がられる。
一方、身の丈六尺、声の大きい文左衛門は、立会場の場立にピッタリ。気が利き、勘が良く、相場の見通しをよく的中させたので、ほどなくして手代に取り立てられる。
「旦那様、柳橋あたりで少し息抜きをしてきんしゃい」と、加奈が手綱を緩めても「そなたと、娘たちに囲まれていれば、それで十分じゃ」と、好色漢の文左衛門にしては珍しく、脇目も振らずに働く。
株式相場の世界に身を置くと、政治経済のことはもとより、諸事万般のニュースが耳に入ってくる。過去を知り、将来がどう変わっていくのか、世上の変化に人一倍関心の強い文左衛門にとって、相場師は天職であった。もろもろの情報を収集し、深夜に至るまで罫線を引くと、面白いように相場の見通しが当たった。
財を成した文左衛門、変動の激しい相場の世界から足を洗い、二十九歳にして大阪で大栄商会を創業。実業家として一歩を踏み出し、憧れの芦屋の六麓荘に移り住む。事業は日清戦争の終結以後、景気低迷の中での厳しい船出となる。そこで、まずは基幹産業への進出を考え、筑豊炭坑を買収し、ひとまず鉱山の経営に専念する。