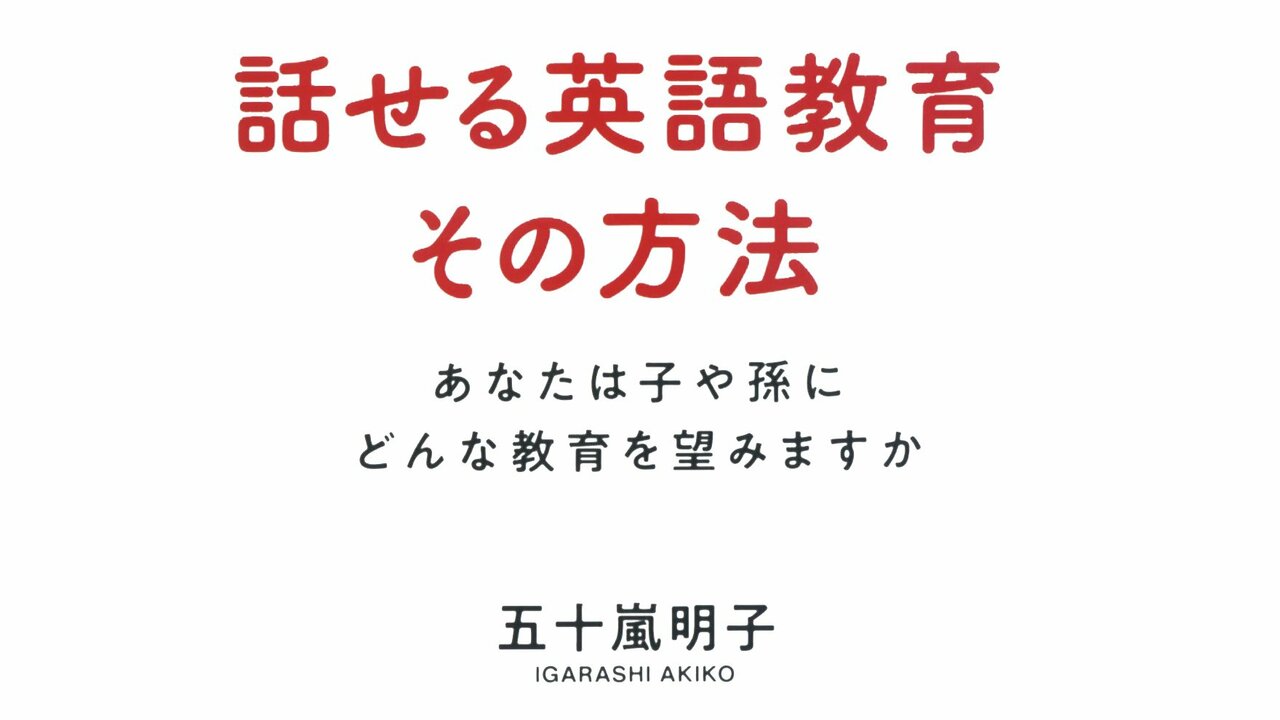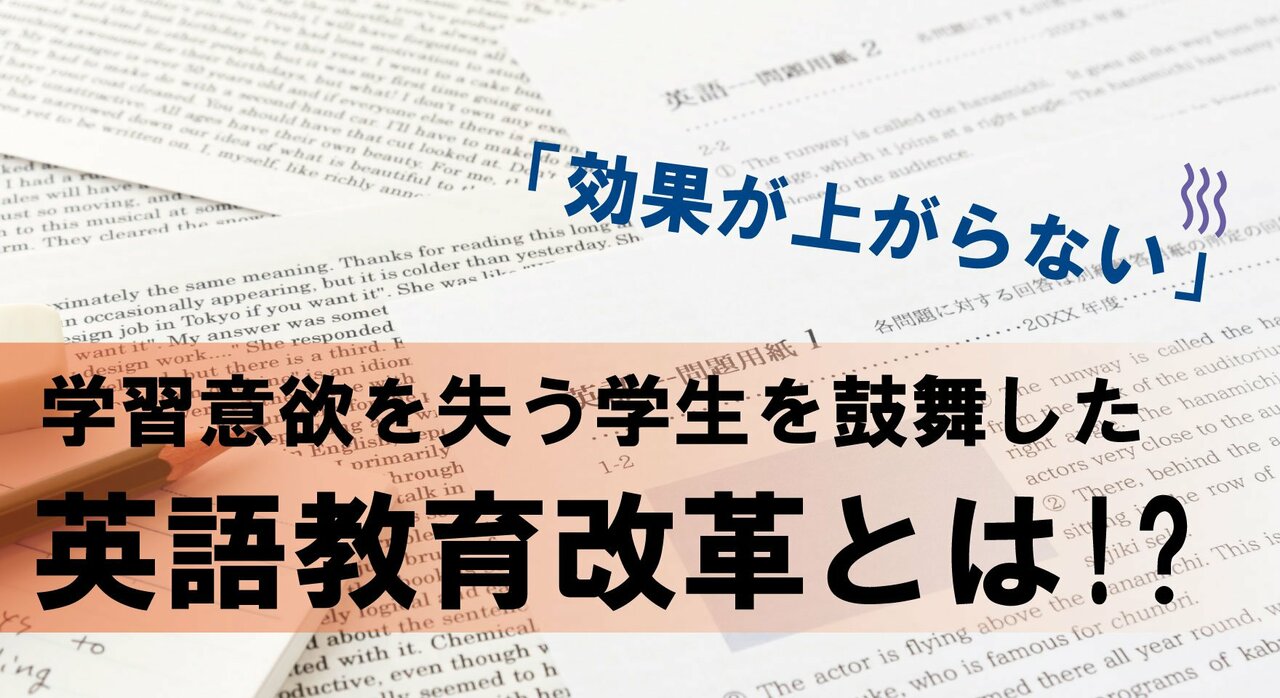【前回の記事を読む】【衝撃】昭和初期「中学校英語科全廃論」が世論の支持を得た理由
再び強まった英語教育への風当たり
1945(昭和20)年、第2次世界大戦で敗戦して終戦を迎えると、英語ブームが起こりました。1947(昭和22)年には学制が改められて、義務教育として男女共学の新制中学校が設置され、英語も教えられることになりました。選択科目での導入でしたが、高校入試科目に英語があったため、ほとんど必修科目として扱われました。
しかし、授業数は週平均3時間となっており、明治時代の半分しかおこなわれませんでした。戦後しばらくは国民的英語ブームに押されて、英語教育の現場は落ち着きを取り戻したかのようでしたが、1955(昭和30)年になると、今度は新制中学校の英語必修化の是非をめぐる議論が起こり、加藤周一が「信州の旅から─英語の義務教育化に対する疑問」と題した評論を『世界』12月号に発表。再び英語教育への風当たりが強まりました。
その時に発表された評論の趣旨は、次のようなものでした。
(1)日本の中学生の圧倒的多数は、仕事の上で将来英語を実用に供する機会をもたない。
(2)実用に供する必要のある場合には、今の中学校はもとより高等学校卒業生の知識でも不充分至極である。国際会議に至っては大学卒業生の大部分がゼロである。
(3)従って、全国の中学生に漫然と不充分な教育をほどこす代わりに、一部の生徒をもう少し徹底的に教育できるような方法を、何とかして編みだしてゆく必要がある。(『日本の英語教育200年』伊村元道著/大修館書店2003年刊/282~283頁より)
5改革の波
加藤が評論を発表した翌年の1956(昭和31)年には、アメリカのロックフェラー財団が、日本の英語教育改革援助に乗り出しました。日本は独立を回復していましたが、アメリカは、日本の英語教育改革を占領政策のやり残しと考えていたのです。
この時、日本英語教育研究委員会(ELEC:現在の英語教育協議会)はミシガン大学の教授であったフリーズを顧問に迎えました。教授は講演などをとおして自らが作り上げた「オーラル・アプローチ」という英語教授法の普及に努めました。
戦後に導入された「オーラル・アプローチ」法
フリーズが提唱した英語教授法とは、次のようなものでした。
1.音声言語、話し言葉(つまり生きた英語)を優先。
2.リスニング→スピーキング→リーディング→ライティングの順序で学習する。
3.音声・文型・文法などの言語構造の学習が中心。
4.文法は帰納的に教える。
5.学習作業の中心は、口頭による反復練習のドリル。(耳・口中心)
6.模倣・反復・強化により言語習慣の形成を図る。
7.授業は原則として英語で行う。
8.意味の理解は、日本語を介在させないで、絵や実物を通して直接行う。語彙の拡大よりも、まず発音・文型の完全学習を優先する。
9.授業は教師主導型。予習は前提としない。
10.既習事項との対比を重視し、前時の復習から始める。(『日本の英語教育200年』伊村元道著/大修館書店2003年刊/72頁より)
このフリーズの「オーラル・アプローチ」は、英文を簡略化して、パターン・プラクティス(文型練習)で覚えるもので、日本人の指導者でも訓練すればできることから広い支持を得るようになりました。