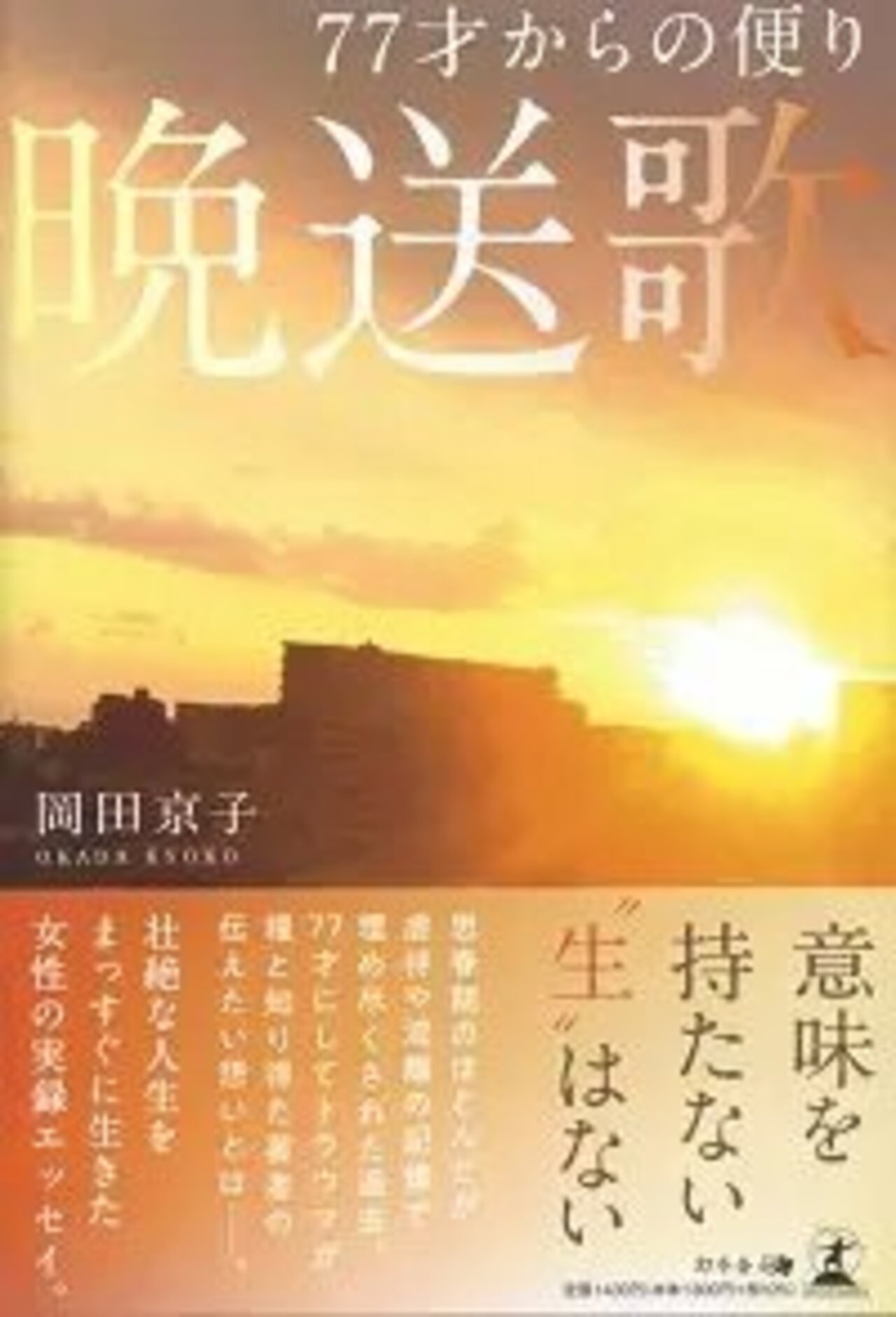序章 熱き想いは運命に流れ
都の西北 早稲田の森に 聳ゆる甍は われらが母校
空気を揺るがし、大戦の最中というのに何者をも恐れぬ怒号に近い歓喜の雄叫びはその日大学構内にこだまし、飛び交う帽子、マントで黒い華を咲かせた。
一人一人の若者は死を背負いつつもそれゆえの熱き想いを堂々と獅子のごとく吠えた。その中でも優秀な成績で卒業し弁論大会でも優勝し、まるでこの世の栄華をすでに手中に収めた様な学生が一人、然し彼の歓びは露程もそこには無かった。まるで、珠玉の様な女性との未来のみがこれからの世界だった。
その女性は年上、海軍士官であった夫を亡くした、然も3才の子の母でもある。この広き世界になぜ二人なのか、なぜ未来ある若者がそこに我が身を踏み込ませたのか、それが恋、男と女の何ものをも恐れぬ何も見えぬ只一筋の熱き炎だったのだろう。東京で過ごした蜜月の日々、只見つめ合い、あつく抱きしめ、共にふれ合う空気が全てだった。
未だ生まれもしない私が何故、父と母の来し方を書けるのか……それは逝くまでの父が、義理叔母が、垣間聞かせてくれた私のために遺された二人の証明と思う。
人生をあざなう現実があった。大学を卒業し社会人として歩む時が訪れる。彼はもちろん、彼女の3才の前夫の子と、我が子を身籠った愛する人と大阪のわが家(尾関)に共に手をたずさえ堂々と帰省した。然しそこに待つ現実は厳しいものだった。
私の祖父の後妻や父の兄弟、そして使用人達の驚愕と蔑みの前に初めて二人の置かれた立場を知り私の両親は予知せぬ未来に怯えた。男子として兵役につけなかった父、病弱であったと聞く母も又結核と云う病に有った。つながれた絆は、やはり儚い細い縁なのだろう。
祖父より権力を持ち、マッカーサーと陰で呼び称される継母(祖父の後妻)にとって、自分を後妻として受け入れなかった父の愛する女性の、どのひとつだけでも尾関の嫁として迎え入れることなど論外なのだ。私は、それでも彼女の子宮のなかで日々育ち、思えば母とつながれている何ものにもかえがたいひと時であったと信じる。
時は経ち私はゆりかごの中で人の子として近づく誕生の日を夢見ていたはずなのに。