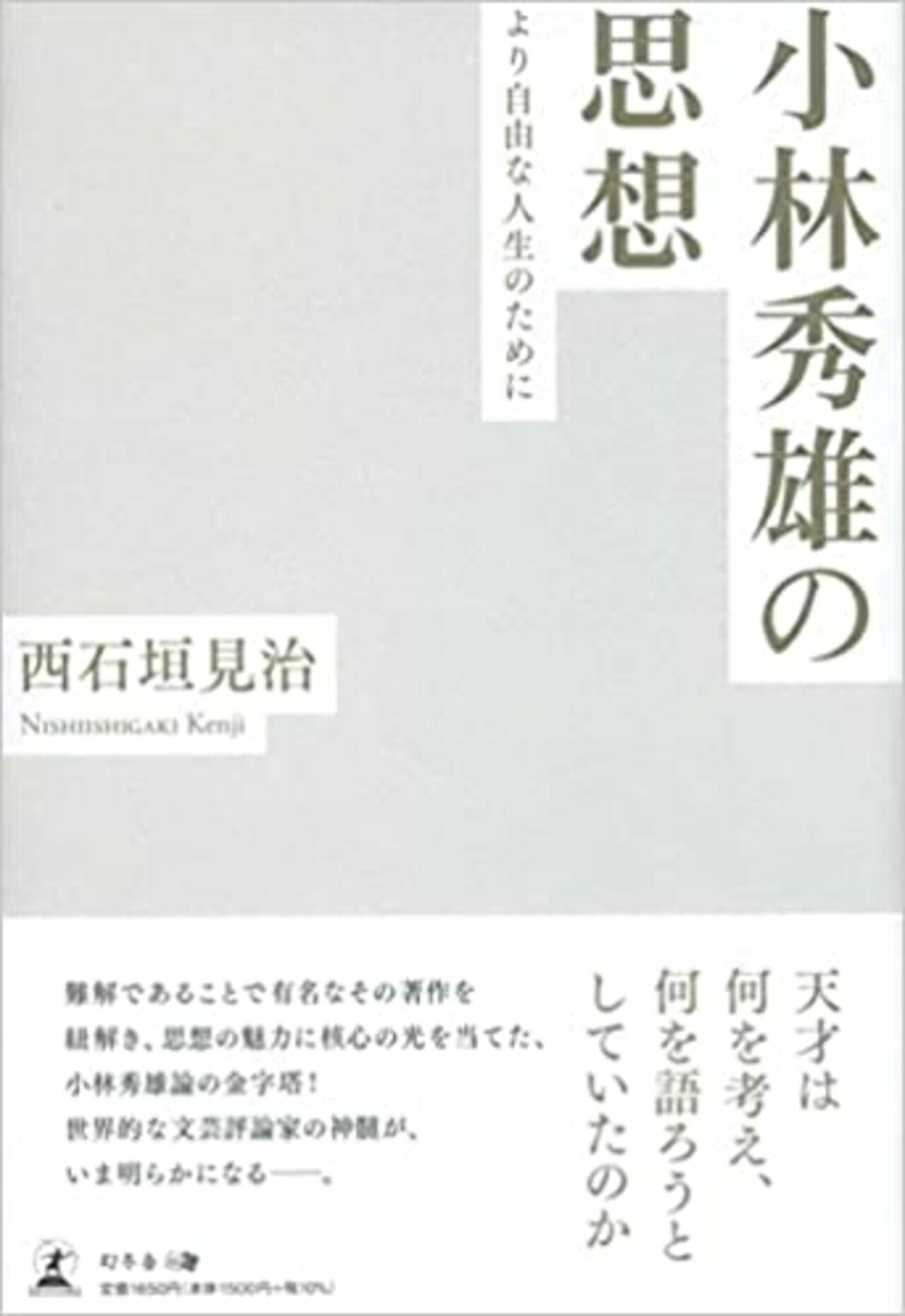「明晰なる無知」の根差した“常識”は、省みられて“自覚”となること
そして、それは、本源的無知とのほかならぬ反省的な関係を物語ることから、科学にしろ、文学や学問、芸術にしろ、およそ考えるという行為に関わる一切は、“自覚”の問題を抜きにしては成り立たないのである。
そもそも小林自身が、その文壇デビュー作『様々なる意匠』において、詩人のボードレールの批評の魔力を、その“自覚”に求めたのである。
「彼の批評の魔力は、彼が批評するとは自覺する事である事を明瞭に悟つた點に存する。批評の対象が己れであると他人であるとは一つの事であつて二つの事ではない。」(『様々なる意匠』小林秀雄全集第一巻「様々なる意匠」新潮社)
これは、「明晰なる無知」と同一の起源の光に負う“自覚”が、批評の実践の個別性に投げ込まれているのである。
しかし、それは、その内実において、通念の「自覚」との間に大きな懸隔をはらんでいるのである。後者では、自己を多少なりと突き放して、第三者的な関係を求めるにしても、その基準は、自己の判断や裁量に委ねられざるを得ないからである。
そのため、その判断自体が、先入見や因襲的な通念に浸かって、その無意識の枠組みから抜け出さないことは、普通にあり得るのである。あげく、その枠内での関係のみが、スポットライトを当てられたように、反射的に浮き彫りになるのである。
それに対し、ボードレールの自覚においては、作品鑑賞という具体的な認識経験への、本物の他者の参加が前提にされているのである。
いったい、作品制作において、読者と「自他が一つになる」ことを期するのは当然としても、しかしそれは、読者によって追体験される必要があるのである。それは、作品制作から始まって、読者の鑑賞にいたるまでの、自他の相対立さえする、一連の内的過程を包括した、批評の全体的営為なのである。
そしてそれが、作品に「自他が一つになる」認識経験をもたらすのは、それが、遠慮のない他者にとっても、明証的─つまり、直接的な確実性ないしリアリティをもって存在するからなのである。