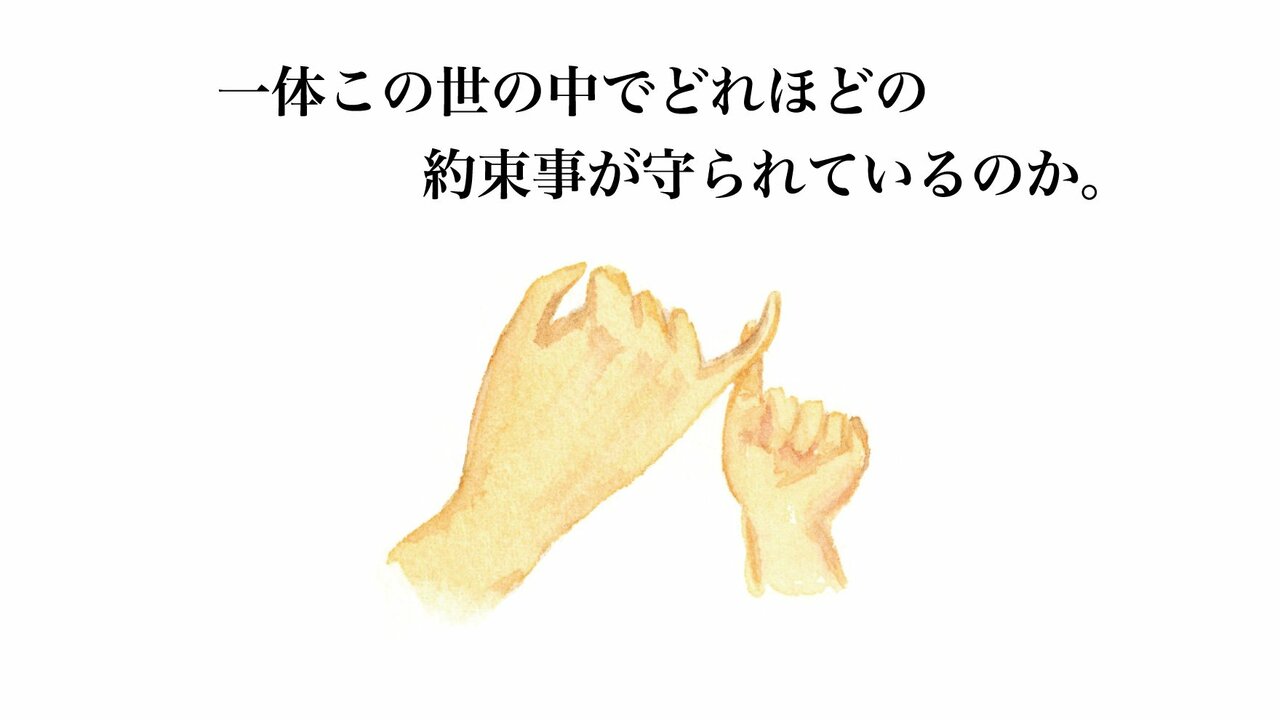また「子どもたちを呼ばなくていいの?」と沙織が聞くと、諭は「一昨日メールで目のことを説明し、今後はメールのやり取りができなくなると連絡したので、来たければ自分で来るだろう」と言っているらしい。
沙織は自分から洸太たちに上手に伝える自信がないので、「いつでもお父さんに会いに来て」と布由子から伝えてくれないか、と依頼してきた。布由子は陸を通じて洸太と連絡を取り、翌日曜日の昼に会うことになった。陸が選んだ西新宿のレストランでピザを食べながら話したところ、洸太はしばらくの間大学院の入試で忙しく、病院に行っていなかったと言う。
入試にはパスしたので、今週にでも病院に行きたいと言ったが、諭の視力がなくなるという話には「お父さんにどんな言葉をかけたらいいかわからない」と意気消沈していた。沙織に対しては「どう思われているのか、気まずい」と口にしていたので、いつでも来ていいという沙織の言葉を布由子から伝えた。それ以降子どもたちは再び病院を訪れるようになり、沙織との距離も少しずつ近づいていったようだ。
沙織を通して聞いた医師の話では、視神経を圧迫しているカビの感染を抑えるためにはステロイド投与を控えめにしなくてはならないが、そうすると高熱や倦怠感で本人の辛さが増すので、感染症が一気に悪化するリスクを承知の上でステロイドを強化する方針とのこと。本人の苦痛を少しでも和らげる方向の治療、つまり終末期ケアに移行するという宣告がされたのだ。布由子は両腕に鳥肌が立つのを感じたが、今までの経過からそれを覚悟しなければならない時期が来たのだと知った。
その数日後の土曜日に沙織から諭の容体の急変を知らされた。諭はここ数日、三十九度から四十度の発熱が続いた。カビによる炎症反応に加え、白血病細胞の増加による腫瘍熱で、夜中には酸素も足りなくなり鼻から吸入を始めた。「あと二、三日が山だ」と医師から伝えられた。
たまたまその日に面会に来た子どもたちから「沙織さんに感謝しています」と言われて、沙織もまた泣いてしまった、とのこと。布由子は急遽、日曜日朝の高速バスの予約をした。「場合によっては数日宿泊するかもしれない」と職場の上司や部下にも連絡を済ませ、諭の症状が落ち着いたとしても沙織と付き添いを交代するつもりだった。
今までもそれは考えていたが、会う度に諭の意識が鮮明であったため、申し出る機会を失っていた。