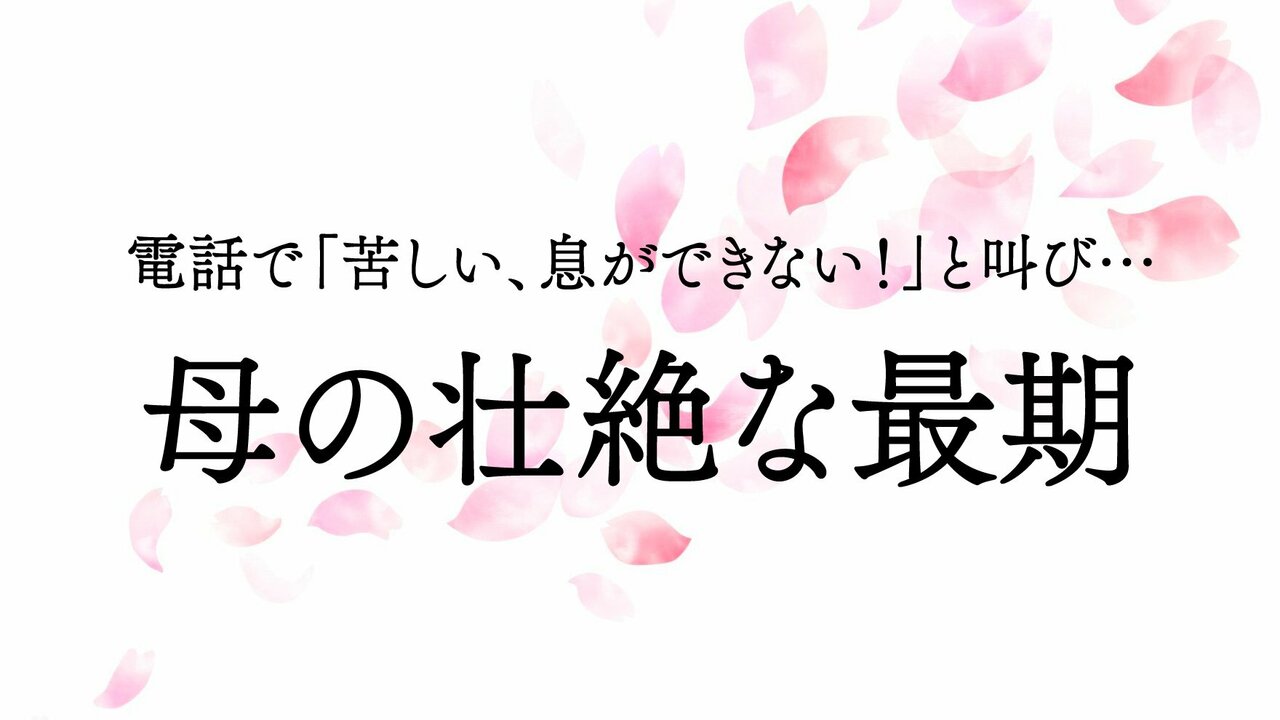【前回の記事を読む】私は彼の冷たい手を握り、「ごめんね」と耳元でささやいた。
Passengers ――過ぎ去りし人たちへのレクイエム
事実の重み
あれからもう何年経っただろうか。確か、私が医者になってやっと1年が過ぎた頃だった。紹介状を持って一人の大柄な男と妻が共に緊張した面持ちで外来診察室に入って来た。
その日は教授外来で、最も若い医局員、つまり私が筆記係として教授の前に座っていた。外来看護師が教授に紹介状を手渡し、持参した胸部レントゲン写真をシャーカステン(X線写真を掲げて観察する明るく光る器具のこと)にかけた。右の横隔膜角に液体の貯留が見られ、一年目の私にもわかる腫瘤影が右肺の中央にぼんやりと認められた。
問診が始まった。教授が低い声で男にいろいろと質問していく。
私は要点を書き留め、文章にしていく。
男は1カ月前から胸痛と血痰を認め、この3カ月で体重が5kgも減少したことを訴えた。
私は教授が指示する検査の申し込み用紙を書きながら患者の横顔をうかがった。不安に青ざめ、傍らに立つ妻の表情もこわばっていた。
新米医師の私にさえその病名とおおよその予後の見当がついた。つまり、癌性胸膜炎を伴った肺腺癌で予後は不良、おそらく余命は1年以内。
その人の運命を知った瞬間から医者と患者は対等の関係ではなくなるが、その頃の私には他人の運命を知ってしまうことの重みはまだわからなかった。
男に寄り添う妻は心配そうに診察を見守っている。
「彼らはまだ何も知らない」のに、初対面の医師二人は素知らぬ顔をしながらその運命を読み、思い描いている。これは授業でもドラマでもなく、目の前で展開されている現実であることに何か不思議な後ろめたさを感じた。