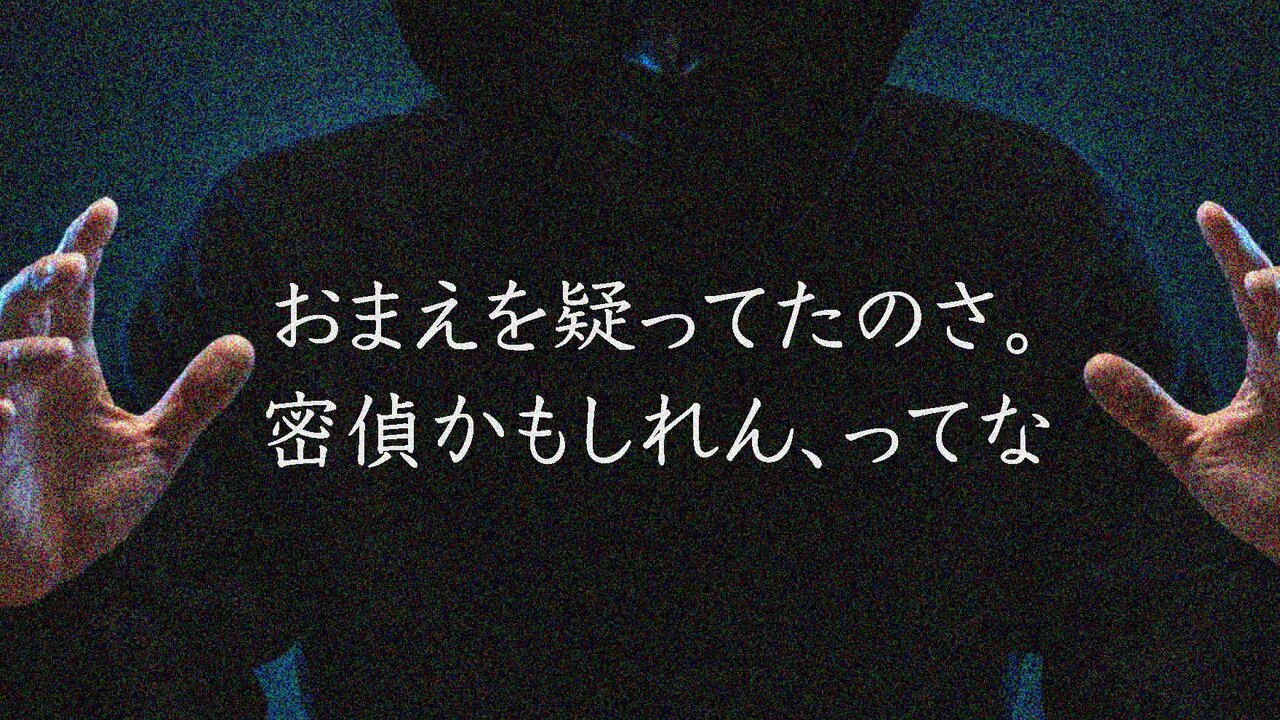壱─嘉靖十年、漁覇翁(イーバーウェン)のもとに投じ、初めて曹洛瑩(ツァオルオイン)にまみえるの事
(2)
「残念です。働き口がみつかって、喜んでいたところだったのに……」
「うーん、おれに言われてもなあ」
このままここに居すわって、ねばっても、漁覇翁(イーバーウェン)に面会できないのではどうしようもない。今日のところは、
帰ろうか……。
「出なおして来ます」
「そのほうがいいだろ。また来ることがあったら、顔を出してくれ。何か力になってやれることがあるかもしれん。おれのことは、羊七(ヤンチー)といえば、知ってる人がいるだろうよ」
「ひとつ、訊きたいことがあるんですが」
「なんだ」
「こんなに建物が建ち並んでいるのに、まったく人の気配がないのは、いったいどういうわけなんで?」
「昼間はな」
「夜はちがうんですか」
「ここで本当にはたらくことになったら、そのうちわかるさ」
「それと、見張りの子たちは、どうしてあんなに、棒みたいに突っ立ってるんですか? こっちが声をかけても、うんともすんとも言わないで逃げちまう。まるで飛蝗(バッタ)だ」
「それはだな……」
言いかけた羊七(ヤンチー)が、言葉を呑み込んだ。ふり返ると、先ほどの飛蝗(バッタ)少年が、昨晩会った浅黒い宦官――段惇敬(トゥアンドゥンジン)――といっしょに、立っていた。鍛えあげられた筋骨が、りゅうりゅうと盛り上がっている。
「仕事中に、井戸端会議か?」
「いえ……」
「むだ口をたたくな」
「すいません」
「夏言邸(シアユエン)には、いつもの分量だ。それと、厳嵩邸(イエンソン)から、豕(ぶた)の半身と、鶏(とり)を二十本ばかり、追加でとどけてくれとの依頼があった。急ぎのようだから、すぐに行け」
羊七(ヤンチー)が、沈黙したまま荷車に手をかけ、貯蔵庫に入って行った。
「さて」
ぎょろりとした目が、私にむけられた。
「おまえは、誰だ」
思わぬ言葉に、あっけにとられた。
「昨晩、お目にかかった王暢(ワンチャン)でございます。漁覇翁(イーバーウェン)様から、ここへ来いと言われて、参上つかまつりました」
「ほう」
いま、初めて聞いたといったふぜいである。
「何ができる」
「食事の席にて披露いたしましたとおり、計算はできます。読み書きも、一通りのことは」
「よし」
段惇敬(トゥアンドゥンジン)は、おうようにうなずいた。
「おまえの働き場所は、この豕小屋だ」
ぶ、豕小屋?
「あ、あの」
「なんだ?」
「漁覇翁(イーバーウェン)様は、いまどちらに? ひとこと、ご挨拶を」
あるじに面会して、昨日の一件を思い出してもらおうと思ったが、段惇敬(トゥアンドゥンジン)は冷徹に言い放った。
「貴様ごとき軽輩に会うほど、大翁はヒマではない。新参者の処遇は、おれに一任されている。おれの命令が、すなわち翁の意向だ。従えぬというのなら、ここで働く資格はない。去れ」
「し、従います」
首をすくめてこたえると、彼は、肉をかついで出てゆこうとする羊七(ヤンチー)を呼び止めた。
「おい、今日から、これがおまえの下で働く。ちょうどいい機会だ、得意先をまわるのなら、これも連れて行け。荷車を押すんだ」
否(いや)も応(おう)もなかった。羊七(ヤンチー)のうしろにつき、肉を満載した荷車を力いっぱい押して、門外に出た。するすると近よって来る女がいる。ここへ入るときに声をかけて来た、ゴマ塩頭の女であった。
「どうだった? 漁覇翁(イーバーウェン)」
「会えませんでした」
「やっぱりね。そんな気がしてたのさ。あっはっはっ。で、羊七(ヤンチー)を紹介されて、一緒にはたらくように言われたわけね? 今日の卸先は、どこなんだい?」
羊七(ヤンチー)が、ぶっきらぼうに、こたえた。
「夏言邸(シアユエン)と、厳嵩邸(イエンソン)だ」
「あーら、そう。よりによって、仲のわるい二人に」
「どういう人なんですか?」
「二人とも、勢力ある政治家だよ。夏言(シアユエン)様は侍読学士、つまり皇帝の先生だわね。うわさじゃ、日の出の勢いなんだってね。皇上のおぼえもめでたくて、さいきんは廷臣の長老格でも、彼の鼻息をうかがっているとか。厳嵩(イエンソン)様のほうは南京の礼部尚書になったはずだけど、こんなにいっぱい肉をつかうってことは、いま、こっちに帰って来てるのかねえ? ま、注文を出したのは、伜(せがれ)のほうだろうけど」
「伜?」
「そう。父親がむこうに行ってるから、その留守番。この伜がまた、子供のころから手癖がわるくてねえ。人のものをぬすんで来ては、罪を他人になすりつけたり、村の娘をかどわかして来ては、かたっぱしから手をつけたり」
「はあ」
「あんた、肉の配達にまわるのなら、まず顧客の名前と家をおぼえることだね。でなきゃ仕事にならないよ。ところであんた、いま、どこで寝泊まりしてるの?」
「寺に間借りをしたり、先輩のところにころがり込んだりしています」
「じゃ、あたしのところに来なさいよ。空いてる部屋があるから、都合してあげてもいいよ。漁門ではたらくのなら、近いほうがよくないかい?」
「えっ、いいんですか?」
住む場所が確保できるなんて、そんなありがたい話はない。
「もちろん。配達がおわったら、ここへもどって来て、顔をお出し。荷物をまとめて来るんだよ」
羊七(ヤンチー)は、私とゴマ塩女とのやりとりのあいだ、ずっと黙っていた。肉をはこぶ道中も無言、夏言邸(シアユエン)で受け取りの記帳をしてもらうときも、無言であった。話しかけても、返事もしなかった。どうして、こんなに黙りこくっているのだろう? 漁門でみた飛蝗(バッタ)少年といい、どうも、もの言わぬ人が多い。
謎は、厳嵩邸(イエンソン)の中庭を出て、二門をくぐったときに解けた。そこは四方を壁にかこまれており、外からの視線がさえぎられる場所であった。
「おれが、ずっと黙っているのを、けげんに思ってたろう」
押し黙っていた羊七(ヤンチー)が、口をひらいた。
「おまえを疑ってたのさ。密偵かもしれん、ってな」
「み、密偵?」