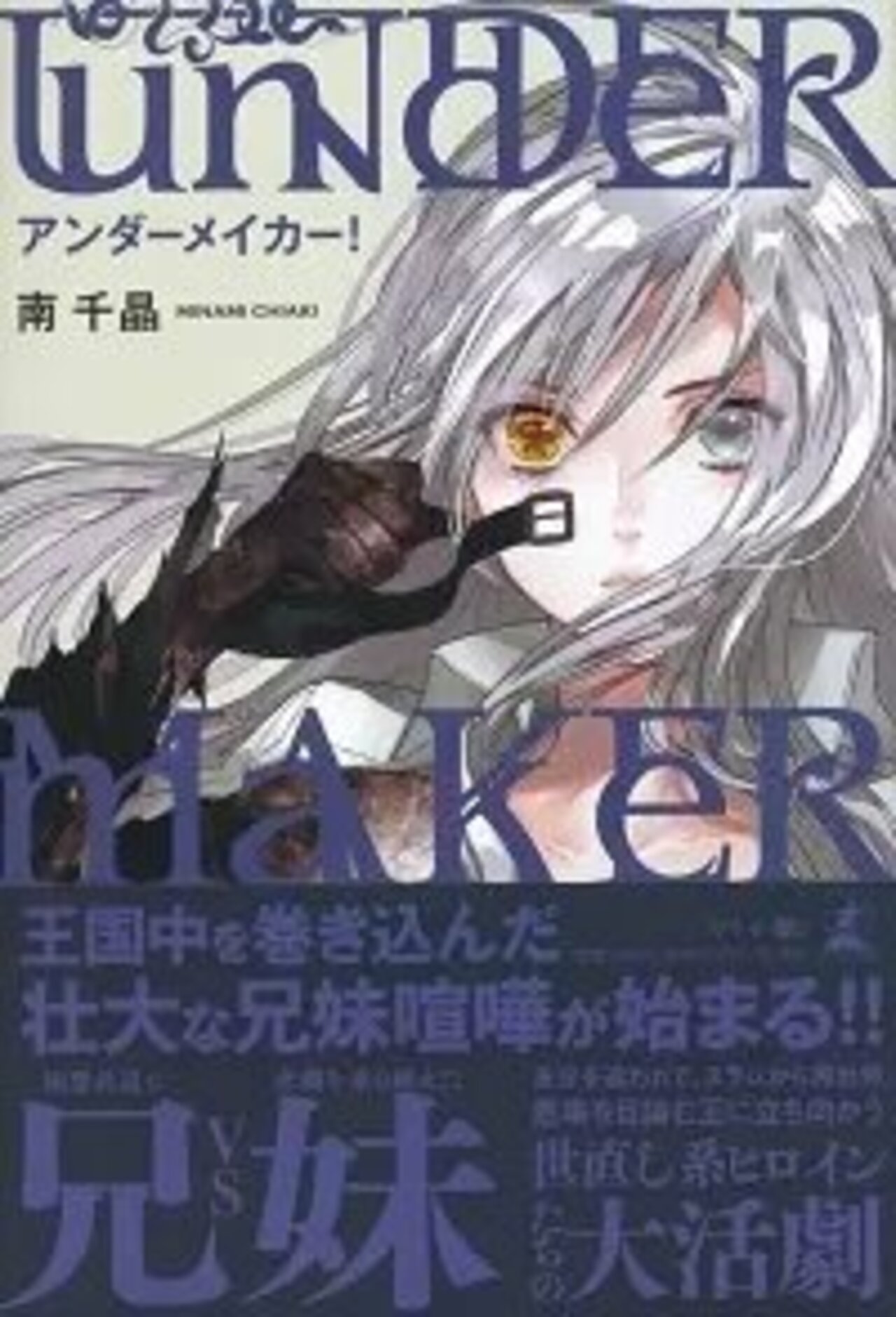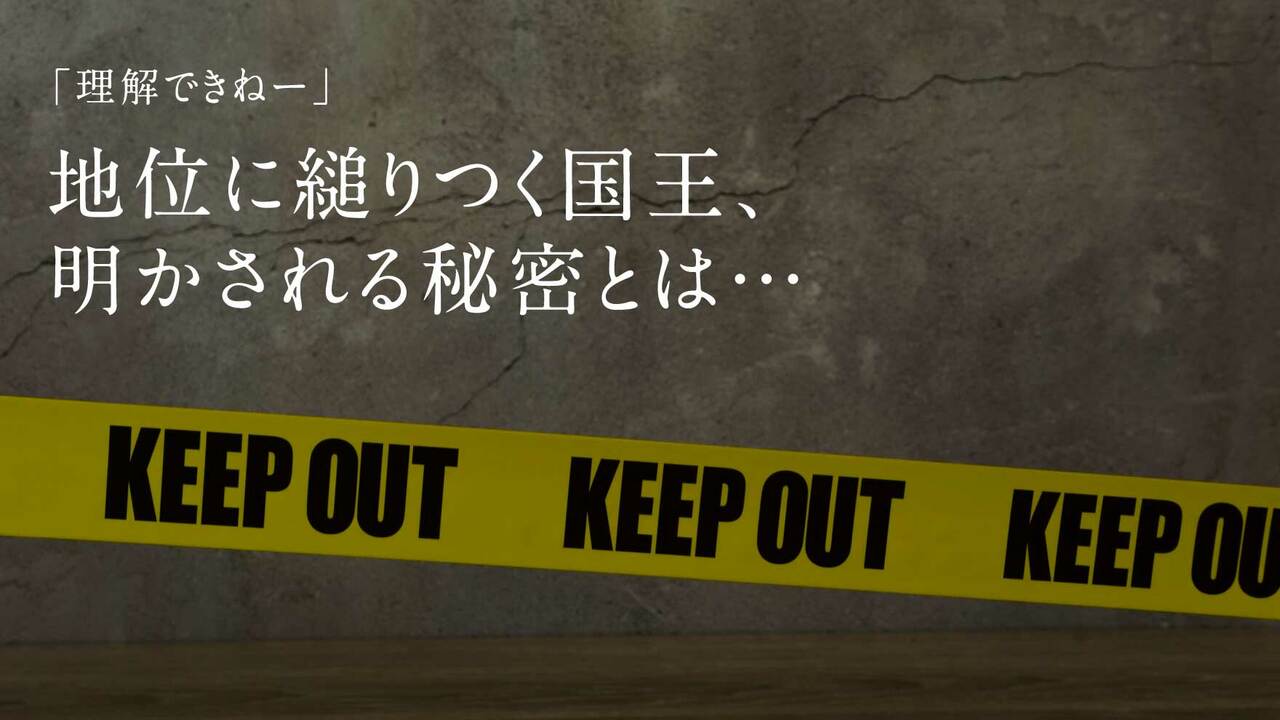【前回の記事を読む】「……お兄ちゃん。何、してるの?」燃え盛る炎の向こう、血まみれの刀を握る兄に…
葬儀屋の居候
「ふああぁぁ、ねみ……」
広さにして十五畳程のスペースだろうか、事務所として構えられているこの一室はスラム世界の片隅に存在していた。
地獄町四十九丁目、廃墟となった三階建てのビルの名は“葬儀屋~UNDERMAKER~”。それがここの主人の住処である。ビルの入り口には“依頼は二階までお越しください”という紙切れが貼ってあったが、長い間さらされているのだろう、紙は若干黄ばんでいた。そして何か建設予定でもあったのかその廃墟ビルの前には広大な空き地があるものの、広すぎる駐車場として使用しているようだった。
葬儀屋主人は長い銀髪を後頭部から晒しを巻いて結い、所長専用の椅子に凭れかかって窓際に足をかけた。歳にして十六歳ぐらいだろうか、まだ少女という呼称が合う風貌だ。右目にはベルト式の黒い眼帯を着けている。
「お嬢。お行儀が悪いですよ」
昼食の準備ができたのだろう、その所長専用の机に内側からスプーンやフォークを並べていき、執事は前菜を中央に置いた。
「良い食材が手に入りませんでしたので、前菜はスープに致しました」
「胃に入りゃなんでもいいさ。殺女と浩輔は?」
「上の階の雑務倉庫の整理をさせております。御呼び致しますか?」
「そうだな、あいつらも腹が減ってる頃だろ」
「では、暫し失礼させて頂きます」
従者の執事が去って、彼女は再び窓の外に広がる空き地に視界を移した。
―あれから七年。追手が来る様子はない。だが、油断はできない。張りつめた神経で目を閉じ、周囲を感覚だけで警戒してみる。読めたのは、上の階にいる三人分の気配だけだ。そして再び目を開け、壁にかけられた白いロングコートを視界に入れ、何を思うのか無表情でそれから視線を机の上に戻し、今度こそ前菜を口に入れた。
「……ん、うま」
一人の食事にはもう慣れた。誰かがいると、あの日の朝を思い出しそうで怖かった。あの頃のような豪華な食事なんて求めてはいない。ただでさえ流通の乏しいスラム世界だ、食材を手に入れるだけでも大変だというのに、執事の栗栖はあの頃と何も変わらない。不満なんてこれっぽっちもないのに、自分の為にあれやこれやと手を尽くしてくれている。
「礼を言うのは……最期の時でいいよな」
ぽつりと呟いた本音は、まるで自分に言い聞かせるようだった。この生活にもいつか終わりが訪れる。追手から逃げ惑う日々も、いつか終わりが来る。
葬儀屋なんて職業を勝手に名乗っているが、全ては利用する為に始めた事業だ。そう、人の魂を喰らって利用している。昨夜仕留めた二人の男の魂も、右腕に喰わせた。その痕を隠す為に、黒い生地で右腕を肩から隠している。ファッションだといえばそれまでなので、誰もそれに気づかない。勿論、それを知る人物も片手で数えられるだけの人数しかいない。