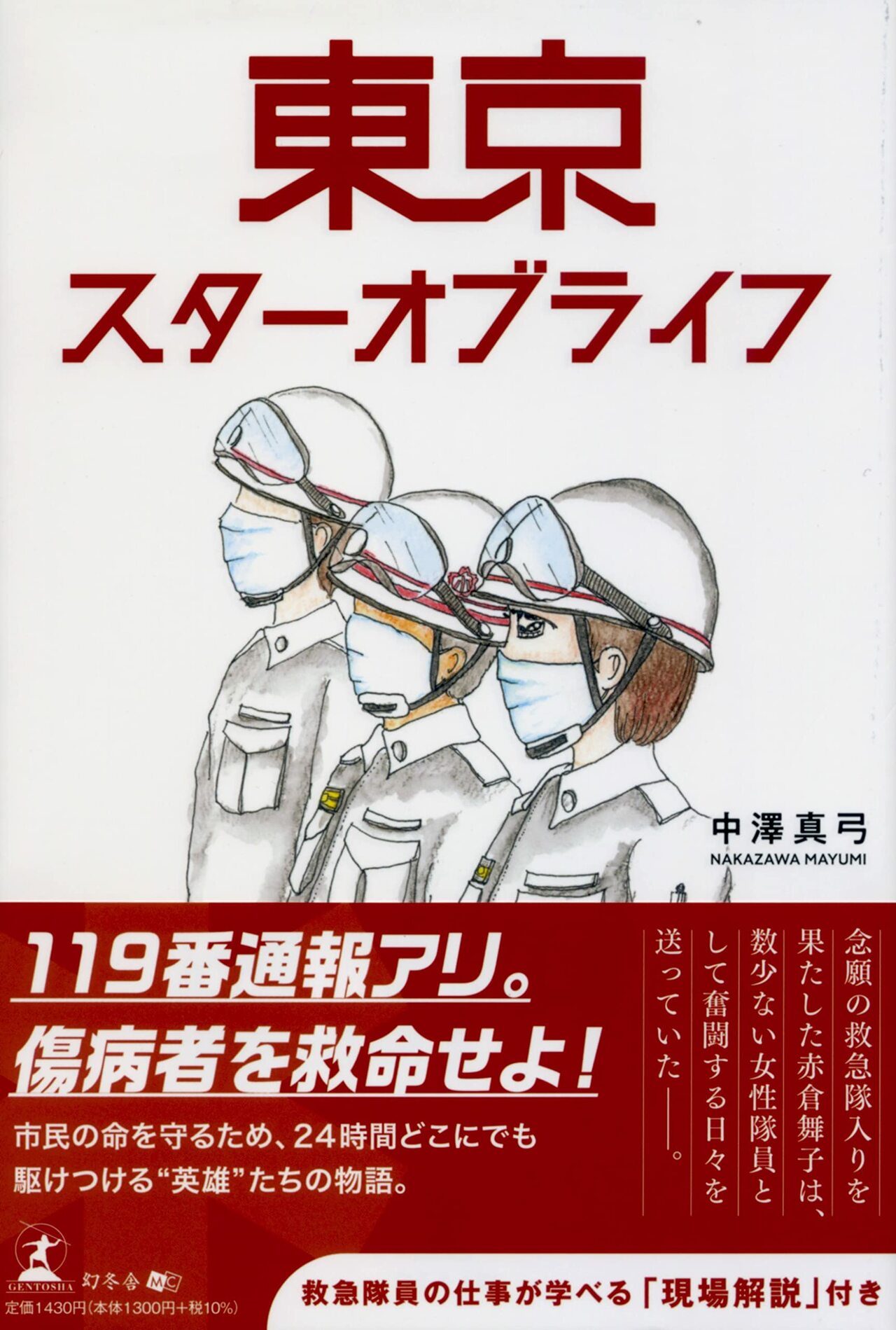瑞穂は、舞子より十五歳年上の四十歳。小柄で華奢ではあるが、いつもシャキッとしている。二十歳で東京消防庁に入庁し、救急隊員の経験を積んで救急救命士の資格を取った。救急隊長としても勤務していたが、五年前に突然消防を退職し、大学教員に転職した。当時、女性の隊長は片手で数えられるほど少ない人数しかいなかったから、退職の理由については様々な憶測が飛び交ったという。
「私は、どうしても納得がいかないの」
瑞穂の思いは大学の講義で何度となく聴いていたので、舞子には話の続きがわかっていた。
「日本の救命率……いえ、心停止傷病者の社会復帰率を上げたいっていう話、ですよね?」
「そう。日本は先進国で、心肺蘇生教育も普及している。車の免許を取るときや、中学校や高校でも実施されているし、街中にはたくさんのAEDが備えてある。でも、それをつなぐ仕組みが、まだまだ足りないと思う。やっぱり、日本を世界一、安全安心の国にしたい。私たち救急救命士が、しっかりと現場のデータを分析していかなくてはいけないの」
「それで、先生は研究者の道に転職をしたんでしたよね」
舞子は、大学時代の瑞穂の講義を思い出していた。現場の経験を重ねることはもちろん大切だけど、何も考えずに過ごしてはいけない。現場で学ばせていただいていることを、将来の傷病者のために、一つ一つを振り返って、反省し、分析する。舞子が若手隊員の勉強会を提案したのも、その教えに基づくものであった。
「それで、さっそく明日のスケジュールだけど……」
明日、九月の第一火曜日は、「火曜シリーズ」の聴講が計画されていた。毎月、第一火曜日に開催されるキング郡のカンファレンスである。
いつかは、私もここで日本の救急救命士について発表をしたい……。
世界最高峰のパラメディックのカンファレンスに登壇する舞子の夢は、まだ心の内にしまっておいた。